訂正公開買付届出書
- 【提出】
- 2021/10/11 15:10
- 【資料】
- PDFをみる
脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、LINE Digital Frontier株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社イーブックイニシアティブジャパンをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社イーブックイニシアティブジャパンをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
対象者名
株式会社イーブックイニシアティブジャパン
買付け等をする株券等の種類
(1) 普通株式
(2) 新株予約権
① 2012年4月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第10回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年5月26日から2022年4月25日まで)
② 2012年4月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第11回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年5月26日から2022年4月25日まで)
③ 2013年10月4日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第12回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年10月30日から2023年9月29日まで)
④ 2013年10月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第13回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年11月23日から2023年9月29日まで)
⑤ 2014年10月9日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第14回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年11月1日から2024年10月31日まで)
⑥ 2015年10月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第15回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年11月1日から2025年10月31日まで)
⑦ 2019年7月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第16回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年8月16日から2029年7月24日まで)
⑧ 2020年6月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第17回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年7月16日から2030年6月21日まで)
なお、第10回新株予約権、第11回新株予約権、第12回新株予約権、第13回新株予約権、第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権及び第17回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。
(2) 新株予約権
① 2012年4月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第10回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年5月26日から2022年4月25日まで)
② 2012年4月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第11回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年5月26日から2022年4月25日まで)
③ 2013年10月4日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第12回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年10月30日から2023年9月29日まで)
④ 2013年10月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第13回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年11月23日から2023年9月29日まで)
⑤ 2014年10月9日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第14回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年11月1日から2024年10月31日まで)
⑥ 2015年10月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第15回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年11月1日から2025年10月31日まで)
⑦ 2019年7月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第16回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年8月16日から2029年7月24日まで)
⑧ 2020年6月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第17回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年7月16日から2030年6月21日まで)
なお、第10回新株予約権、第11回新株予約権、第12回新株予約権、第13回新株予約権、第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権及び第17回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。
買付け等の目的
(1) 本公開買付けの概要
公開買付者は、2021年9月30日開催の公開買付者の取締役会において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に上場している対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を非公開化することを前提として行われる一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、対象者株式の全て(本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、ヤフー株式会社(以下「ヤフー」といいます。なお、本書提出日現在、ヤフーは、Zホールディングス株式会社(以下「Zホールディングス」といいます。)の完全子会社です。)が本書提出日現在所有する対象者株式(所有株式数2,443,600株、所有割合(注1):43.18%)(以下「本不応募株式」といいます。)及び対象者が所有する自己株式を除きます。以下「本対象者株式」といいます。)及び本新株予約権の全てを対象にした公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施することを決議いたしました。なお、本書提出日現在、公開買付者は、対象者株式を所有しておりません。
(注1) 「所有割合」とは、対象者が2021年7月30日に公表した「2022年3月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)」(以下「対象者第1四半期決算短信」といいます。)に記載された2021年6月30日現在の発行済株式総数(5,712,700株)に、(ⅰ)同日以降本書提出日までに行使された新株予約権(対象者によれば第10回新株予約権(7個)及び第12回新株予約権(10個))の目的となる対象者株式数(2,400株)及び(ⅱ)同日現在現存し、本書提出日現在行使可能な第10回新株予約権(30個)、第11回新株予約権(8個)、第12回新株予約権(60個)、第13回新株予約権(62個)及び第16回新株予約権(42個)の目的となる対象者株式数(24,000株)を加えた数から、対象者第1四半期決算短信に記載された2021年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(80,518株)を控除した株式数(5,658,582株)(以下「潜在株式勘案後対象者株式総数」といいます。)に対する対象者株式の割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。
本取引は、以下の各取引から構成されます。
① 本公開買付け
② 本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの公開買付期間(以下「公開買付期間」といいます。)の末日以後、本公開買付けの決済の開始日前に実施される、NAVER Corporation(以下「NAVER」といいます。)からその子会社であるWEBTOON Entertainment Inc.(以下「WEBTOON Entertainment」といい、公開買付者、NAVER及びWEBTOON Entertainmentを総称して「公開買付者ら」といいます。)(注2)への払込総額16,049,000千円を限度とする出資、WEBTOON Entertainmentからその完全子会社であるNAVER WEBTOON Limited(以下「NAVER WEBTOON」といいます。)への払込総額4,814,700千円を限度とする出資、WEBTOON Entertainmentからその子会社である公開買付者への払込総額11,234,300千円を限度とする出資、及びNAVER WEBTOONから公開買付者への払込総額4,814,700千円を限度とする出資(これら一連の出資を総称して、以下「本出資」といいます。)
(注2) WEBTOON Entertainmentは、本公開買付け公表日において、(ⅰ)NAVER及び(ⅱ)Zホールディングスの完全子会社であるLINE株式会社(以下「LINE」といいます。)が(ⅰ):(ⅱ)=66.6%:33.4%の比率で出資を行う、NAVERとZホールディングスの合弁会社です。
③ 本公開買付けが成立し、本対象者株式及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合に、対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすることを目的として対象者が実施する対象者株式の株式併合(以下「本株式併合」といい、本公開買付けと併せて「本非公開化取引」といいます。)
④ 下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の、対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとするための一連の手続き(以下「本スクイーズアウト」といいます。)の完了を条件として実施される、対象者の株主を公開買付者のみとするための、公開買付者を株式交換完全親会社、対象者を株式交換完全子会社とし、WEBTOON Entertainment株式を対価とする三角株式交換(以下「本三角株式交換」といいます。)
⑤ 下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の、本三角株式交換の効力発生を条件として行われる、本三角株式交換の対価としてヤフーに交付されたWEBTOON Entertainment株式の、ヤフーからその完全親会社であるZホールディングスへの現物配当その他の方法による移転(以下「本グループ内移転」といいます。)
⑥ 下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の、WEBTOON Entertainmentの株主である(ⅰ)NAVER、並びに、(ⅱ)LINE及びその完全親会社であるZホールディングス(Zホールディングス並びにその子会社であるヤフー及びLINEを合わせて、以下「Zホールディングスグループ」といいます。)間のWEBTOON Entertainmentへの出資比率を、本公開買付け公表日における出資比率((ⅰ):(ⅱ)=66.6%:33.4%)と等しくなるように調整し、もって本取引を通じたNAVER及びZホールディングスグループによるWEBTOON Entertainment株式の取得が出資比率に応じた比例的なものとなることを確保するために行われる、NAVERからWEBTOON Entertainmentに対する追加出資(以下「本追加出資」といいます。)
本公開買付けに際し、公開買付者は、2021年9月30日付で、NAVER及びZホールディングスとの間で、①本不応募株式について、本公開買付けに応募させないこと、②本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの公開買付期間末日以後、決済の開始日前にNAVERがWEBTOON Entertainmentを通じて公開買付者に対して本出資を行うこと、③本公開買付けの成立後に、本株式併合により対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすること、④本スクイーズアウトの完了後に、本三角株式交換を実行すること等を含めた、本取引に係る諸条件を内容とする取引契約(以下「本取引契約」といいます。)を締結しております。なお、本取引契約の締結にあたっては、Zホールディングスがヤフー及びLINEの完全親会社であり、意思決定を実質的に支配していると考えられることから、Zホールディングスのみを契約当事者としております。本取引契約の詳細については、下記「(4)本公開買付けに関する重要な合意」をご参照ください。
本公開買付けにおいては、公開買付者は、対象者株式を非公開化することを目的としておりますところ、下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の本株式併合の手続きを実施する際には、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることから、本取引を着実に遂行すべく、本公開買付け後に公開買付者及びヤフーが対象者の議決権数の3分の2以上を所有することとなるようにするため、1,328,800株(注3)(所有割合:23.48%)を買付予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(1,328,800株)に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行いません。
(注3) 買付予定数の下限(1,328,800株)は、潜在株式勘案後対象者株式総数(5,658,582株)に係る議決権数(56,585個)の3分の2以上となる議決権数(37,724個)に対象者株式1単元(100株)を乗じた株式数(3,772,400株)から、本不応募株式(2,443,600株)を控除した株式数です。
一方、上記のとおり、本公開買付けにおいて、公開買付者は本対象者株式の全てを取得して、対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすることを企図していることから、買付予定数の上限を設定しておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(1,328,800株)以上の場合は、応募株券等の全ての買付け等を行います。
公開買付者は、下記「8 買付け等に要する資金」の「(2) 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等」の「④その他資金調達方法」に記載のとおり、本公開買付けに係る決済に要する資金を、本出資により賄うことを予定しております。また、公開買付者は、「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、本公開買付けにおいて、本対象者株式及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、対象者に対し、本取引の一環として本株式併合の実施を要請する予定ですが、本株式併合により生じる端数の合計額に相当する対象者株式の取得にかかる資金についても、本出資により賄うことを予定しております。
なお、本取引を図で表示すると大要以下のとおりです。
Ⅰ.本公開買付けの実施前
本書提出日現在において、ヤフーが2,443,600株(所有割合:43.18%)、少数株主が残りの3,214,982株(所有割合:56.82%)を所有。
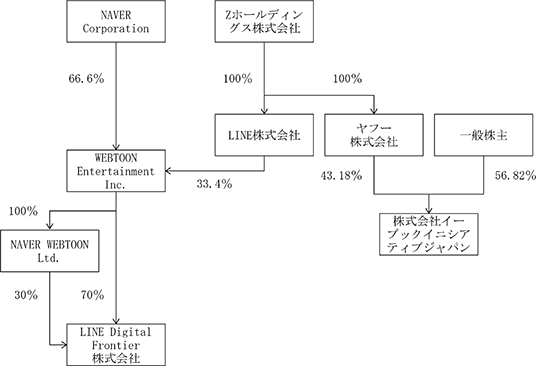
Ⅱ.本公開買付け(2021年10月1日~2021年11月15日(予定))
公開買付者は、本対象者株式及び本新株予約権の全てを対象に本公開買付けを実施(対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)は4,750円、本新株予約権1個当たりの買付け等の価格(以下「本新株予約権買付価格」といいます。)は本公開買付価格と各本新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者株式数の個数を乗じた金額。)。
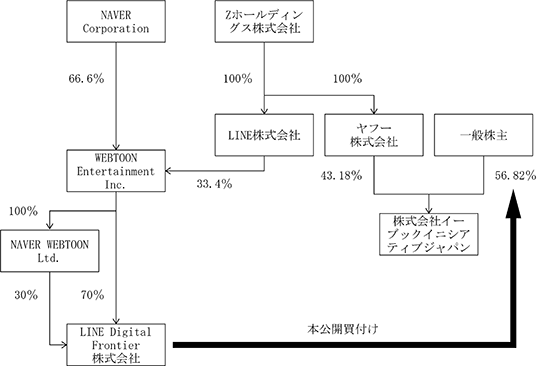
Ⅲ.本公開買付けの成立後
① 本出資(2021年11月中旬~下旬(予定))
公開買付期間末日以後、本公開買付けの決済の開始日前に実施される、NAVERからその子会社であるWEBTOON Entertainmentへの払込総額16,049,000千円を限度とする出資、WEBTOON Entertainmentからその完全子会社であるNAVER WEBTOONへの払込総額4,814,700千円を限度とする出資、WEBTOON Entertainmentからその子会社である公開買付者への払込総額11,234,300千円を限度とする出資、及びNAVER WEBTOONから公開買付者への払込総額4,814,700千円を限度とする出資。
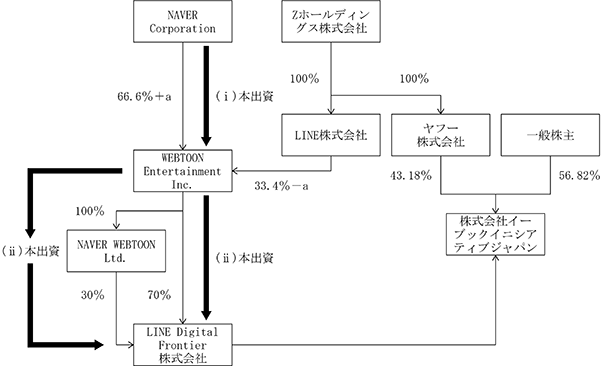
② 本株式併合(2022年1月頃(予定))
本公開買付けが成立し、本対象者株式及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合に対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすることを目的として対象者が実施する株式併合。
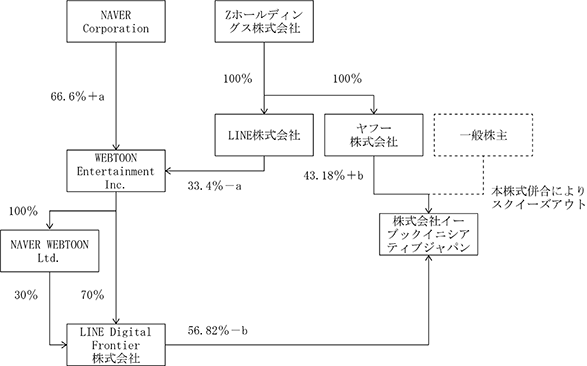
③ 本三角株式交換(2022年3月頃(予定))
本スクイーズアウトの完了を条件として実施される、公開買付者を株式交換完全親会社、対象者を株式交換完全子会社とし、WEBTOON Entertainment株式を対価とする三角株式交換。本三角株式交換は、本スクイーズアウトの完了後に、ヤフーが所有する対象者株式(1株未満の端数を除く。)を公開買付者が取得し、対象者の株主を公開買付者のみとすることを目的として実施されるものであり、本三角株式交換によって、対象者の株主は公開買付者のみとなります。本三角株式交換における対価の決定方法については、下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。
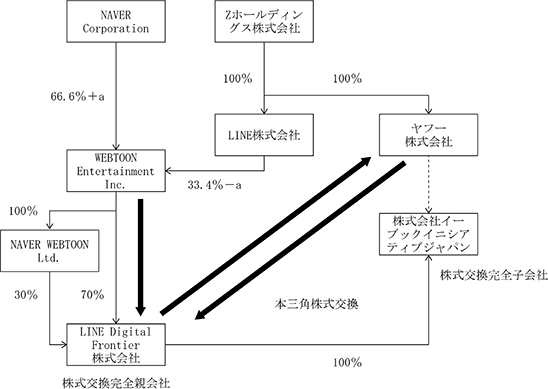
(本三角株式交換実行後)
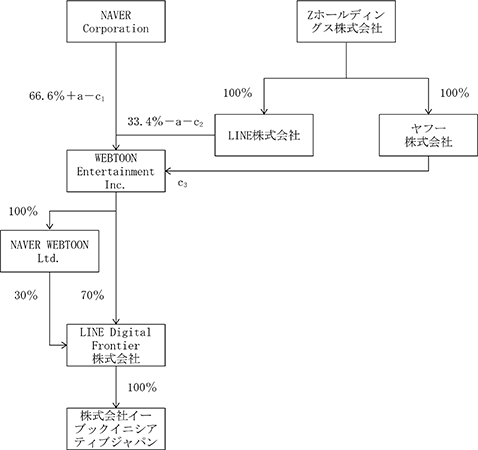
④ 本グループ内移転(2022年3月頃(予定))
本三角株式交換の効力発生を条件として行われる、本三角株式交換の対価としてヤフーに交付されたWEBTOON Entertainment株式の、ヤフーからその完全親会社であるZホールディングスへの現物配当その他の方法による移転。
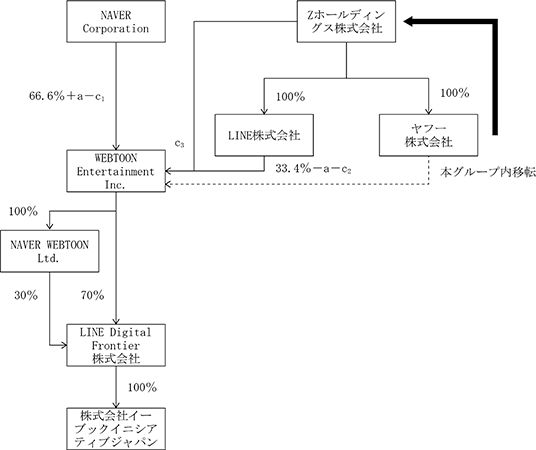
⑤ 本追加出資(2022年3月頃(予定))
本三角株式交換の効力発生を条件として行われる、WEBTOON Entertainmentの株主である(ⅰ)NAVER及び(ⅱ)Zホールディングスグループ間のWEBTOON Entertainmentへの出資比率が本公開買付け公表日における出資比率((ⅰ):(ⅱ)=66.6%:33.4%)と等しくなるように調整し、もって本取引を通じたNAVER及びZホールディングスグループによるWEBTOON Entertainment株式の取得が出資比率に応じた比例的なものとなることを確保するために行われる、NAVERからWEBTOON Entertainmentへの追加出資。本追加出資における出資額の決定方法については、下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。

対象者が2021年9月30日に公表した「LINE Digital Frontier株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けに関し、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
かかる対象者取締役会の決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2) 本公開買付けを実施するに至った背景、目的並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの目的及び背景
公開買付者は2018年に設立以来、LINEの子会社として日本国内において電子コミック事業を運営しておりましたが、2020年8月、同事業を日本だけではなく米国・韓国を中心にグローバルに展開し、米国法人であるWEBTOON Entertainmentが所有していた電子コミックのノウハウや人材を得ることによるオリジナル作品の強化及びデジタル作家の発掘育成の強化を目指し、WEBTOON Entertainmentに対してLINEの所有していた株式が譲渡されたことにより、公開買付者はWEBTOON Entertainmentの子会社となりました。現在は、WEBTOON Entertainmentが自ら及びその完全子会社であるNAVER WEBTOONを通じて、公開買付者の発行済株式の全てを所有しております。
WEBTOON Entertainmentは韓国最大のインターネット企業であるNAVERが66.6%、LINEが33.4%の持株比率にて株式を所有しており、主にNAVER WEBTOON、WEBTOON、LINE WEBTOON、LINEマンガの電子コミック、WEBTOON(スマートフォンに最適化した縦読みのフルカラー電子コミックを指します。)サービスを世界100カ国以上の国々で提供しており、月間ユーザー数7千万人以上を有する電子書籍事業者です。WEBTOON Entertainmentグループ(WEBTOON Entertainment及びNAVER WEBTOON、 公開買付者、StudioN、LICO等により構成される企業集団をいいます。以下同じです。)は「世界中のクリエイターと読者をつなぐ最も革新的で便利なプラットフォームを作ろう。」という経営理念の下、WEBTOONを中心に電子ノベルや映像制作及び流通等も手がける総合エンターテインメントカンパニーです。
このようなWEBTOON Entertainmentグループの中で、公開買付者は、2013年4月にLINEからリリースされ、現在は公開買付者が運営する「LINEマンガ」アプリを通じて、電子書籍の配信事業と投稿プラットフォーム事業(注1)を営んでおります。その上で、公開買付者は、2020年度から「マンガの未来を創る」というビジョンを掲げ、「作品との出会い」「新しい価値の提供」「最良の作品発表の場所と環境」をミッションとし、これを達成することを通じて日本のマンガ文化を発展させ、世界へと広げていくことを目指し事業に取り組んでおります。公開買付者はこのミッションを達成していくため、まずはサービス提供を通じた利用者基盤の拡大を成長戦略の一つとして位置付けております。
(注1) 投稿プラットフォーム事業とは、アマチュア作家に対し作品を投稿すること及び投稿した作品を配信することを可能にする環境を提供するサービスを意味します。
また、対象者プレスリリースによれば、対象者は、2000年より、コミックを中心に小説、雑誌、ビジネス書等の幅広い品揃えを有する電子書店「eBookJapan」を運営し、拡大が続く電子書籍市場のパイオニアとして、積極的に事業拡大に取り組んできたとのことです。対象者の設立は、対象者の創業者が出版社に勤務していた時代に、返本された書籍の山が断裁・焼却されることによる地球環境への影響を危惧したことがそのきっかけとなっており、対象者は、「SAVE TREES!」を事業コンセプトに打ち立て、電子書籍の普及による地球環境保護を目指しているとのことです。現に、対象者は、これまで累計1億冊以上の電子書籍を販売してきましたが、これら全てを紙媒体の書籍として販売した場合には、原材料としておよそ50万本以上に相当する樹木が必要となるものと考えられることを踏まえると、対象者の事業は、上記の事業コンセプトに沿ったものになっているものと自負しているとのことです。
対象者は、2008年頃から、急速に普及が進んだスマートフォン及びタブレット端末向けの電子書籍の販売に注力することで成長を加速させ、2011年10月、東京証券取引所マザーズ市場にその株式を上場し、2013年10月には東京証券取引所市場第一部に上場したとのことです。また、対象者は、2015年5月には、オンライン書店「BOOKFAN」及び「boox」を運営する株式会社ブークスを完全子会社化(2016年5月に対象者を吸収合併存続会社、株式会社ブークスを吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施)し、紙書籍のオンライン販売も事業に加えているとのことです。
2016年6月9日には、対象者はヤフーと資本業務提携契約を締結し、ヤフーによる対象者株式に対する公開買付け並びにヤフーを割当先とする第三者割当による増資及び自己株式の処分を行いました。なお、ヤフーは、当該公開買付けに先立ち、対象者株式100株を取得しているとのことです。これにより、ヤフーは同年9月5日に、対象者株式2,443,600株(所有割合:43.18%。内訳としては、当該公開買付けにより、対象者株式2,315,700株(うち400,200株は自己株式の処分により当該公開買付けに応募)を取得し、当該第三者割当による増資により対象者株式127,800株を取得しております。)を取得するに至り、対象者はヤフー及びソフトバンクグループ株式会社の連結子会社となったとのことです。その後、対象者とヤフーが協力して運営する新たな電子書籍販売サービス「ebookjapan」を2018年10月より立ち上げ、当該サービスを移行先として、対象者がこれまで運営してきた電子書籍販売サービス「eBookJapan」よりユーザーの移行を促進した後、2019年6月には旧サービス「eBookJapan」における電子書籍販売を終了し、これにより、新サービス「ebookjapan」へのサービス統合を完了したとのことです。現在は、Zホールディングスグループとのシナジーの強化に注力し、電子書籍市場における対象者の利用者基盤を拡大することにより、電子コミック分野での国内取扱高No.1を目指して事業連携を進めているとのことです。
公開買付者らとしては、エンターテインメントサービスの源泉となる知的財産権が多く存在する日本の電子書籍市場での公開買付者の成長は、WEBTOON Entertainmentグループにとっても重要である一方で、マンガ大国といえる日本の電子書籍市場は、多数の競合他社が存在する極めて競争環境の厳しい市場であり、企業価値向上のためには有効な経営施策を断続的に打ち出す必要があると認識しておりました。
公開買付者らは、上述の戦略のもと、公開買付者の利用者基盤を強化し事業を拡大させる成長施策のひとつとして、電子書籍領域や関連する事業におけるM&Aについても常に検討しておりました。そのような状況の中、公開買付者らは、2019年11月中旬のLINEとZホールディングスの経営統合の決定を機に、グループ会社となる対象者との間で電子書籍の領域においてシナジーを生み出す可能性に関する検討を開始いたしました。そして、2020年10月上旬より、公開買付者と同じ電子書籍事業を営む対象者との間で、シナジーの創出に向けた初期的な協議を開始し、アプリを通じたコンテンツ配信に強みを持つ公開買付者とWEBを通じたコンテンツ配信に強みを持つ対象者が相互補完的に互いのプラットフォームを活用しつつ、より効率的に潜在的な顧客を獲得すると同時に、日本における優良マンガコンテンツの配信を行う対象者がコンテンツ配信を海外で展開する公開買付者らのグループに加入することで日本の優良マンガコンテンツのグローバルでの存在感の向上が可能であり、より広範な顧客層を対象として対象者のコンテンツ配信が可能になることを確認いたしました。また、特に対象者の持つバックエンド業務(注2)の仕組みを公開買付者と共通化することで、これまで以上に安定的なサービスインフラを構築し、利用者に対し、電子書籍をはじめとするコンテンツの提供スピードと安定性を兼ね備えたサービスの提供に資する可能性があるとの認識を持つに至りました。さらに、上記のような対象者及び公開買付者の間の協業の可能性に加え、公開買付者らは、①「ebookjapan」及び「LINEマンガ」の異なる2つの利用者層並びに②「ebookjapan」がマーケティングや送客、決済システム等で提携する「Yahoo!JAPAN」及び「LINEマンガ」がマーケティングや人材面等で連携する「LINE」という異なる2つのプラットフォームをより有機的に機能させるためには、バックエンドの仕組みの共通化のみならず、公開買付者が対象者を子会社化し、両サービスを共通の目的を持って事業を推進してこそ最大のシナジーを生み出すことができるとの考えを持つに至りました。そして、LINEとZホールディングスの経営統合が完了したことを受け、2021年3月上旬に、対象者の親会社であるヤフー及びZホールディングスに対して公開買付者による対象者の子会社化を行う旨の初期的な打診をいたしました。
(注2) 電子書籍事業におけるバックエンド業務とは、サービス開発業務のうち、出版社等の著作権保有者から許諾を受けた紙媒体のマンガ・書籍をデジタライズ化する作業を担う業務をいいます。他方で、バックエンド業務と対比する用語として「フロントエンド業務」があり、ユーザーへのコンテンツの提供その他サービス提供全般を意味します。
そして、2021年3月上旬に、公開買付者らは、当該打診の結果、ヤフー及びZホールディングスが、当該子会社化の協議に応じる可能性があるとの感触を得ましたが、同時に、対象者とバックエンド業務に関する業務提携については対象者の子会社化に関する協議の結果にかかわらず公開買付者の事業を推進しシナジーを生み出せる取り組みであることから当該対象者の子会社化の協議とは別途、併行して対象者との間で資本関係を伴わない業務提携の可能性についての協議を進め、対象者が2021年6月1日付で公表した「LINE Digital Frontier 株式会社との業務提携に関するお知らせ」に記載のとおり、公開買付者と対象者との間の業務提携契約を締結(以下「本業務提携」といいます。)するに至りました。
本業務提携は、対象者が「LINEマンガ」のバックエンド業務の一部を受託し、同業務の効率化を進めることで、事業効率の改善及びコンテンツ力の向上を企図したものでした。一方で、公開買付者らは、本業務提携のみでは公開買付者と対象者はあくまで同様の事業を営む競争関係に留まり、また、競争法の観点から全ての事業領域での連携を行えないとの認識のもと、2021年5月31日に、NAVERから、対象者に対して、NAVERの子会社である公開買付者による対象者の非公開化に関する取引を行うことについての初期的な打診を行ったほか、2021年6月1日の公開買付者と対象者との間の本業務提携の後も、公開買付者による対象者の子会社化を実施するべく、検討を続けてまいりました。そして、今後の成長戦略及び企業価値向上策を改めて精査・検討した結果、資本関係のない独立当事者間における事業提携では中長期的な成長を実現する上で限界があることを再認識いたしました。また、上記のような厳しい市場環境において、スピード感をもって両社の成長戦略及び企業価値向上策を一体的に実現していくためには、公開買付者が対象者を子会社化することにより、公開買付者と対象者が資本関係を共通にして、競争関係から脱却し、バックエンド業務に限らない分野も含めてより密接に連携することが不可欠であるとの考えを深化させました。
より具体的には、2021年6月1日に公表した本業務提携以降においても、①「ebookjapan」及び「LINEマンガ」の異なる2つの利用者層並びに②「ebookjapan」がマーケティングや送客、決済システム等で提携する「Yahoo!JAPAN」及び「LINEマンガ」がマーケティングや人材面等で連携する「LINE」という異なる2つのプラットフォームをより有機的に機能させることによって初めて実現するシナジーの獲得の方法として公開買付者による対象者の子会社化について継続的に検討を行っておりました。
その結果、公開買付者らは、公開買付者が対象者を子会社化することにより可能となるWEBTOON Entertainmentグループの経営資源や上記の各事業において培ったノウハウの活用により、オリジナル・コンテンツの拡大を含めた対象者の事業のさらなる発展を支援することができると考えるに至りました。また、公開買付者が対象者と資本関係を共通にし、迅速な意思決定を行う体制の確保や事業提携関係のみでは競争法の規制上実現できない営業情報の共有を通じて、公開買付者をはじめとするWEBTOON Entertainmentグループが運営する「LINEマンガ」サービスと対象者の運営する「ebookjapan」サービスの協業をより一層加速させることで、日本国内においてスケールメリットを活かしたより強固かつ広範な電子書籍プラットフォームを構築することが可能となると考えるに至りました。具体的には、公開買付者と対象者が持つサービス開発力を融合することにより、バックエンドの統合からユーザーへのコンテンツ配信に至るまで、より安定的で迅速なサービス展開が可能になり、また、公開買付者が持つアプリベースの市場戦略と対象者が持つWEBブラウザベースの市場戦略により、潜在的顧客がスマートフォンを使用するユーザーとWEBブラウザを使用するユーザーの双方をカバーすることになるものと考えております。また、公開買付者らは、これらの取り組みを通じて、両社の中長期的な企業価値の向上と日本の電子書籍サービスの利用者の総合的なユーザー体験の向上にも繋がるとも考えるに至りました。
このような検討を経て、公開買付者らは、公開買付者と対象者の市場における競争力強化及び両社の企業価値の向上を図る観点から、2021年6月18日付で対象者に対し公開買付者による対象者株式の公開買付け及びそれに引き続くスクイーズアウト手続きを通じて対象者の全株式を取得する旨の初期的な意向表明書を提出いたしました。
その後、公開買付者らは、2021年6月下旬から、対象者の事業・財務・税務・法務等に関するデュー・ディリジェンス(2021年8月中旬に終了しております。)や対象者の経営陣との面談等を実施いたしました。公開買付者らはその過程で取得した情報等を踏まえて、本取引の意義、買収ストラクチャー、本取引の実現可能性等について、さらなる分析及び検討を進めるとともに、対象者との間で本公開買付価格を含む本取引の諸条件について引き続き協議を行っておりました。その結果、2021年7月下旬に、公開買付者らは、対象者、対象者の親会社でありプラットフォームの提供を通じて対象者の事業運営上重要な役割を果たすヤフー、及び公開買付者の三者が保有する経営資源を対象者において共同活用し、互恵的にシナジーを享受するためには、公開買付者とヤフーを対象者の唯一の株主とし、さらにそれに引き続き公開買付者を対象者の唯一の株主とするための取引を実施することで、公開買付者と対象者が資本関係を共通にして両社が競争関係から脱却し、バックエンド業務に限らない分野も含めてより密接に連携することが不可欠であると認識するに至りました。具体的には、公開買付者らは対象者を公開買付者の完全子会社とすることにより、両社の特性を活かし、以下のようなシナジーの実現を目指してまいります。
(ⅰ) 公開買付者及び対象者の利用者の拡大
公開買付者は主にiOS、Androidアプリで多くの利用者を獲得しているのに対し、対象者はWEBブラウザで多くの利用者を獲得しており、利用者層においても若年層と高年層とそれぞれ異なる強みを持っております。また、公開買付者と対象者は、アプリとWEBブラウザ双方に強みを持つ電子書籍事業者として、両社の得意とする領域は相互に補完し合う関係にあるため利用者の拡大効果は高いと考えております。また、ユーザーの拡大は多様なユーザーのサービス利用データを蓄積することにも繋がります。電子書籍市場において、過去の購入作品等のサービス利用データの活用は事業運営やマーケティングのみならず、コンテンツ制作においても重要な役割を担う要素であり、より大きなシナジーを互恵的に生み出せるものと考えております。そのため、公開買付者と対象者が両社のデータをユーザーが許諾する範囲内において相互に活用することを今後検討していく予定です。
(ⅱ) 人気IP(注3)の創出と獲得
近年、電子書籍配信事業を運営するプラットフォーム事業者にとっては、自社のオリジナル作品及び独占・先行配信作品といった競合他社との差別化を図れるコンテンツの重要性が増しております。この点、公開買付者と対象者は、利用者層の違いに代表されるような異なる強みを持つプラットフォームを保有していることから、特性の異なる両プラットフォームを通じてコンテンツを配信することで、公開買付者及び対象者が独占的・先行的に配信を行うコンテンツのヒットの可能性を大きく広げることが可能になると考えております。また、コンテンツ制作において利用者を正確に把握することは、新たなヒットコンテンツを生み出すための重要なファクターとなります。そのため、両社が有するユーザーの過去の購入作品等のサービス利用データはコンテンツ制作やコンテンツマーケティングにおいても重要な要素となります。両社が今後検討していく予定のデータの相互利用を活用することでより効率的なコンテンツマーケティングや確度の高いコンテンツ制作が可能になると考えております。このことは、既存の人気IPの権利を保有する出版社その他のライセンサーとのパートナーシップにも有利に働くと考えております。
(注3) IPとは、Intellectual Propertyの略称であり、主にゲームやマンガ、アニメを題材とする知的財産コンテンツを意味します。
(ⅲ) マーケティング戦略の統一と効率化
対象者が得意とするWEBべースのマーケティング施策と公開買付者が得意とするアプリベースのマーケティング施策を最大限に活用し、マルチチャネルに対し強固で統一されたブランドマーケティングを繰り広げることができると考えております。現在の日本のデジタルマンガ市場においては、有償無償を問わずユーザーがアプリ又はWEB上でマンガを閲覧できる数多くの類似サービスが競合しており、各社がマーケティングを行うことから、より精巧に潜在顧客を絞り込んだマーケティングを展開する必要性が高まっております。両社が有するユーザーのデータベースをユーザーが許諾する範囲内において活用し、ユーザーにさらに適したコンテンツを推薦し、各媒体に合ったクリエイティブ広告を運用することでこの効率性をさらに高めることができると考えております。
(ⅳ) サービス開発、インフラ基盤の安定と強化
公開買付者と対象者の持つサービス開発力を合わせることで、効率的なサービス開発を行うことが可能になると考えております。電子書籍市場では、ユーザーがコンテンツに対して購入の都度料金を支払ってコンテンツを閲覧するモデルや、ユーザーがサービス提供者と低額課金契約を締結し対象範囲の電子書籍を制限なく読めるようになるモデル、さらにユーザーが一定期間待機すると一定量のコンテンツを無料で閲覧できるようになるモデル等、多様なビジネスモデルやサービスが生み出されており、後発のサービスであってもトレンドを生み出す可能性のある市場だと考えております。プロダクトの企画開発力や開発スピードはこうした競合他社との激しい競争環境において、いち早く新たなトレンドを生み出すための原動力になると考えております。また、本業務提携によるバックエンド業務の統合に限らず、コンテンツの獲得からユーザーへの配信に至るまで、より広い業務領域における包括的な統合を強固な形で実現していくために子会社化することで、より安定的でスピーディーなサービス展開が可能になると考えております。
そして、公開買付者ら、ヤフー及びZホールディングスは、公開買付者らによる対象者の子会社化を実現する方法として、公開買付者らが6月下旬から8月中旬にかけて対象者の事業・財務・税務・法務等に関するデュー・ディリジェンスを行うのに併行して、専門家も交えて、ヤフーがその所有する対象者株式を公開買付けに応募するスキーム、及び対象者の少数株主が所有する対象者株式の取得を目的とした公開買付けを実施し、ヤフーが所有する対象者株式を本公開買付価格より低い価格でグループ間取引もしくは現物出資・配当等を通じて公開買付者に所有させるスキームを含む様々なスキームの選択肢について議論を行いました。もっとも、対象者の現在の親会社であるヤフーが、対象者が運営する「ebookjapan」のためにプラットフォームを提供することにより対象者の事業運営上重要な役割を果たしていることを踏まえて、公開買付者らは、公開買付者らが想定する上記(ⅰ)から(ⅳ)のシナジーを実現するためには、ヤフーの提供するプラットフォームを含めた形で、Zホールディングスグループの出資比率を維持しながら、NAVERとZホールディングスグループ間の合弁会社であるWEBTOON Entertainmentの傘下に対象者を追加することができるスキームが最善であるとの判断に至りました。そこで、公開買付者らは、ヤフーがその所有する対象者株式を本公開買付けに応募せず、本公開買付け後にWEBTOON Entertainment株式を対価として三角株式交換を行わせる方法により、当該株式を対価としてWEBTOON Entertainmentに現物出資する等の方法により、WEBTOON Entertainmentに対するNAVER及びZホールディングスグループ間の出資比率を維持するスキームを採用することを決定いたしました。また、当該検討において、WEBTOON Entertainmentへの出資を間接的に継続し、本取引の実行により対象者に生まれるシナジーの一部を享受することができるZホールディングスグループと、本取引により対象者の株主ではなくなる一般株主の皆様との間で同一の価格で対象者株式を評価することは一般株主の皆様に不利益をもたらすとの考えから、本対象者株式及び本不応募株式を異なる価格で評価することが適切であると考えるに至りました。そして、2021年8月上旬に、公開買付者らは、本三角株式交換後の本取引のスキームについては対象者の完全親会社であるZホールディングスとの間で継続協議することを前提として、対象者が所有する自己株式及び本不応募株式を除く対象者株式の全てについて、①本公開買付け及びその後の②本株式併合を通じて取得し、③本不応募株式については、本株式併合の効力発生後に公開買付者を株式交換完全親会社、対象者を株式交換完全子会社とし、WEBTOON Entertainment株式を対価とする三角株式交換を実施して取得する段階的買収スキームを対象者に提案することを決定いたしました。そして、2021年8月10日に、公開買付者らは、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者からの独立性を有し、ヤフーとの間に利害関係を有しない対象者の独立社外役員によって構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)に対して、対象者株式については、2021年8月10日の過去1ヵ月間(2021年7月12日から2021年8月10日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である3,525円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値について同じです。)に対して13.48%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアム率の計算において同じです。)のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年5月11日から2021年8月10日まで)の終値単純平均値3,184円に対して25.63%、過去6ヵ月間(2021年2月12日から2021年8月10日まで)の終値単純平均値2,910円に対して37.46%のプレミアムをそれぞれ付した水準となる4,000円を本公開買付価格とする内容を含む提案を行いました。なお、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、同提案の中で本公開買付価格としていた4,000円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値単純平均値である2,589円に対して54.50%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して51.23%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して52.56%のプレミアムであることを考慮したものです。上記の公開買付価格提案において、公開買付者らは、対象者に対するデュー・ディリジェンス、対象者の財務状況及び対象者より2021年7月14日付で開示された事業計画を分析の上、過去における上場会社を完全子会社とすることを企図した類似取引におけるプレミアム水準、本公開買付けへの応募見込み、等を総合的に勘案いたしました。また、この提案の中では、公開買付者らは、対象者が発行していた本新株予約権について、本新株予約権は対象者の役職員に対するストック・オプションとして付与されたもので、権利行使の時点において、対象者又は対象者の関係会社の役職員の地位にあることが権利行使の条件とされているため、公開買付者が本新株予約権を取得したとしてもこれらを行使することができないことから、その全てを1個につき1円で買い取ることを提案いたしました。これに対し、本取引の交渉において対象者の窓口機能を担っていた本特別委員会は、公開買付者らの提案した普通株式1株当たりの公開買付価格である4,000円は公正な価格に達しておらず、対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないことに加え、対象者が発行している新株予約権を1円で買い取ることは、新株予約権者である従業員にとってモチベーションの低下につながり本取引実施後の経営にも影響を与える可能性があるため、行使条件を考慮してもなお受け入れられないとして、2021年8月13日付で公開買付者らに対し提案内容の再考を求める連絡を行いました。以降、公開買付者らと対象者は、公開買付価格について継続的に協議・交渉を行いました。
そして、2021年9月3日に、公開買付者らは対象者に対して、対象者株式については、2021年9月3日の過去1ヵ月間(2021年8月4日から2021年9月3日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である3,736円に対して13.76%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年6月4日から2021年9月3日まで)の終値単純平均値3,479円に対して22.16%のプレミアム、過去6ヵ月間(2021年3月4日から2021年9月3日まで)の終値単純平均値3,077円に対して38.12%のプレミアムをそれぞれ付した水準となる4,250円を本公開買付価格とする内容を含む提案を再度行いました。なお、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、同提案の中で本公開買付価格としていた4,250円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である2,589円に対して64.16%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して60.68%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して62.09%のプレミアムであることを考慮したものです。また、公開買付者らはこの提案の中で、行使条件が付されているために公開買付者が買付けを行った後には行使不能となる本新株予約権につき、それらを実質的に行使可能とすることで新株予約権者の経済的利益を担保するため、その全てを1個につき対象者株式の公開買付価格と種類ごとの行使価格の差額に目的株式数を乗じた金額を本新株予約権買付価格とすることを提案いたしました。このように、公開買付者らは、2021年9月3日に公開買付者が行った価格提案に際して、公開買付者らによる対象者に対する評価を十分に価格に織り込みつつ、対象者の少数株主並びに新株予約権者が経済的に不利益を被らないように配慮を行いました。しかし、本特別委員会は公開買付価格の再考を要請し公開買付者らと対象者の間で本公開買付価格についての合意には至りませんでした。このように、対象者からは2021年9月3日に行った提案に対しての回答が得られなかったため、公開買付者らは、本特別委員会からの再考の要請を受けて、本公開買付価格についての合意を取得するべく、2021年9月上旬から中旬にかけて、本取引実施後に実現されるであろう公開買付者と対象者のより強固な業務上の協力関係の帰結について再度検討を行い、過去2回の提案における価格提示を再度見直しました。そして、2021年9月24日に、公開買付者らは対象者に対して、本新株予約権買付価格については2021年9月3日に公開買付者が前提とした全ての本新株予約権1個につき対象者株式の公開買付価格と種類ごとの行使価格の差額に目的株式数を乗じた価格とするという価格試算の考え方を変更しない一方で、対象者株式1株当たり4,750円を本公開買付価格とする内容を含む最終提案を行いました。本提案における対象者株式1株当たり4,750円は、2021年9月24日の過去1ヵ月間(2021年8月25日から2021年9月24日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である3,872円に対して22.68%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年6月25日から2021年9月24日まで)の終値単純平均値3,653円に対して30.03%のプレミアム、過去6ヵ月間(2021年3月25日から2021年9月24日まで)の終値単純平均値3,231円に対して47.01%のプレミアムをそれぞれ付した水準です。また、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、同提案の中で本公開買付価格としていた4,750円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である2,589円に対して83.47%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して79.58%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して81.16%のプレミアムを考慮したものです。
また、公開買付者らは、上記対象者との協議と併行して、Zホールディングスとの間で、本三角株式交換後の本取引のスキームについても協議し、NAVER及びZホールディングスグループ間のWEBTOON Entertainmentに対する出資比率を維持する観点から、2021年9月上旬、本取引のスキームとして、本三角株式交換の効力発生後に、本グループ内移転及び本追加出資を行うことを決定いたしました。なお、本グループ内移転及び本追加出資に関する協議においては、これらの取引の当事者とならない対象者はその協議に参加しておりません。
なお、対象者は、下記「② 対象者における意思決定の過程及び理由」に記載したとおり、対象者及び本特別委員会との間での協議を重ねた結果、対象者としても本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨するに至ったとのことです。
② 対象者における意思決定の過程及び理由
対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記「① 本公開買付けの目的及び背景」に記載のとおり、2021年3月上旬、公開買付者よりバックエンド業務を中心とした本業務提携の打診を受け、公開買付者との間で協議を進めておりましたが、その結果、2021年6月1日、公開買付者との間で、電子書籍事業における業務提携を行うことを決定するに至ったとのことです(本業務提携の詳細については、対象者が2021年6月1日付で公表した「LINE Digital Frontier株式会社との業務提携に関するお知らせ」をご参照ください。)。本業務提携においては、「LINEマンガ」のバックエンド業務の一部を対象者が受託し、同業務の共通化を進めることで、事業効率の改善及びコンテンツ力の向上を目的としているとのことです。他方、バックエンド業務の共通化以外の協業について、継続して協議を行うこととしていたとのことです。
このような状況下、対象者は、2021年5月31日、NAVERより、NAVERの子会社である公開買付者による対象者の非公開化に関する取引を行うことについての初期的な打診を受けたとのことです。その後、2021年6月上旬にNAVER から、当該取引について、別途正式に提案書を提出する意向を有している旨の連絡を受けたとのことです。当該初期的な打診においては、公開買付者が対象者の親会社であるヤフーの完全親会社であるZホールディングスと合意した上で、対象者の非公開化を実施する想定となっており、ヤフー及びZホールディングスと対象者の少数株主と利害が一致しない可能性があることを踏まえ、対象者は、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、2021年6月上旬、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。)を選任したとのことです。また、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、本特別委員会を2021年6月9日に設置したとのことです。さらに、2021年7月上旬、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)を、選任したとのことです。これらの措置の詳細については、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」をご参照ください。
上記体制の下で、対象者は、ファイナンシャル・アドバイザーとしての大和証券から財務的見地等に関する助言及び支援を受け、また、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から本公開買付けにおける意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けにおける意思決定にあたっての留意点についての法的助言を受け、本取引が対象者の企業価値の向上に資するものか、また、公開買付価格を含む本取引における諸条件は妥当なものであるか等の観点から慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
上記のとおり、対象者は、NAVERより、正式に提案書を提出する意向を有している旨の連絡を受けておりましたが、その後、2021年6月18日、NAVERから、その子会社である公開買付者を通じて、対象者株式の公開買付け及びそれに引き続くスクイーズアウト手続きを通じて対象者の全株式を取得する旨の初期的な意向表明書を受領したとのことです。その後、2021年6月下旬から、公開買付者らによる、対象者の事業・財務・税務・法務等に関するデュー・ディリジェンス(2021年8月中旬に終了しております。)が実施され、また、対象者経営陣と公開買付者らとの面談等が実施された後、対象者は、同年8月10日、公開買付者より、NAVERを通じて、公開買付価格を1株当たり4,000円とすることを含む提案書を受領したとのことです。これに対し、本特別委員会は、同日、大和証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から聴取した意見を踏まえて検討を行った上で、提案された公開買付価格は公正な価格に達しておらず、対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないとして、その付与された権限に基づき、直接の交渉主体として、NAVERに対し公開買付価格の再検討を要請したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、公開買付価格を1株当たり4,250円とする提案を受領したとのことです。当該提案を受け、対象者は、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである大和証券を通じて、公開買付者らとの間で協議を継続いたしましたが、本特別委員会は、当該大和証券を通じた協議の内容並びに大和証券からの財務的見地からの助言及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的見地からの助言を踏まえ、NAVERに対し、上記の提案価格は、大和証券によりディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)に基づき算定される株式価値の水準に照らし、引き続き対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないと考えていること等を理由として、再度公開買付価格の再考を依頼したとのことです。
その後も公開買付者との間で、対象者のファイナンシャル・アドバイザーを通じて、継続的に協議及び交渉を行い、その結果、本特別委員会は、2021年9月24日、公開買付者から、本公開買付価格を4,750円とすることを含む提案を受けるに至ったとのことです。
また、対象者及び本特別委員会は、公開買付者らとの間で、本新株予約権買付価格についても、協議・交渉を行っているとのことです。具体的には、対象者は、公開買付者らより、上記の2021年8月10日付の提案書において、本新株予約権買付価格について、新株予約権1個につき1円とする提案を受けたとのことです。これに対し、本特別委員会は、2021年8月13日、公開買付者らに対し、当該新株予約権は、対象者役職員に対する報酬制度として付与しているものであり、特に、当該新株予約権の内、現時点では行使不可であるものの、保有者に多大な経済的価値が見込まれる新株予約権を適切な価格で買い取らないとすると、保有者である対象者従業員のモチベーションが大きく低下し、非公開化後の経営統合プロセスに支障をきたす事が想定されることから、権利行使をした場合に利益が出る状態にある新株予約権については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とするように再考を依頼したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、新株予約権に係る買付価格については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とする旨の提案を受けるに至ったとのことです。
以上の検討・交渉過程において本特別委員会は、まず、大和証券による対象者株式の価値算定の基礎ともなる2022年3月期から2027年3月期までの事業計画(以下「本事業計画」といいます。)の内容、重要な前提条件及び作成経緯等の合理性について、対象者から説明を受け、確認及び承認しているとのことです。また、公開買付者から公開買付価格を含む本取引の条件についての提案を受領する都度、本特別委員会は、大和証券から受けた財務的見地からの助言を踏まえ、公開買付者からより高い価格を引き出すために、相互に独立した第三者間のM&Aで行われる一般的な交渉プロセスに即して十分な交渉を実施することを含む交渉方針について審議・検討した上で、公開買付者と直接書面のやり取りを行うこと等により、公開買付者との間で公開買付価格に関する協議・交渉を行っているとのことです。当該協議を踏まえた本特別委員会の答申の概要については、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「① 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。
その後、対象者は、2021年9月29日付で大和証券より株式価値算定書(以下「大和証券株式価値算定書」といいます。)を取得し、2021年9月30日、本特別委員会から、(a)対象者取締役会は、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨するべきであると考えられ、(b)対象者取締役会が、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を決定することは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられ、また、対象者取締役会が、本取引において予定されている方法によることを前提に、本公開買付け成立後の本株式併合による対象者の非公開化についての決定をすることは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられる旨の答申書(以下「本答申書」といいます。)の提出を受けているとのことです(なお、本答申書の概要については、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「① 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)。
その上で、対象者取締役会は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点についての法的助言、大和証券から受けた財務的見地からの助言及び大和証券株式価値算定書の内容を踏まえつつ、本特別委員会から取得した本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引により対象者の企業価値の向上を図ることができるか、公開買付価格を含む本取引における諸条件は妥当なものであるか等の観点から慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
上記の検討及び交渉の結果、対象者は、2021年9月30日、本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、引き続き対象者とヤフーとの間の資本関係を維持することにより対象者とヤフーとの間の協業関係を継続して発展させつつ、公開買付者との間の連携を強化し、協業を推進することにより、以下のシナジーを見込むことができ、対象者の収益基盤と事業競争力の強化が図られ、中長期的にも対象者の企業価値の向上に資するとの結論に至ったとのことです。
まず、対象者としては、競争の激しい国内電子書籍市場において、国内取扱高No.1という対象者の目標を達成するためには、(a)競合他社を上回る規模・効率での広告・販促活動や投資の継続、(b)対象者が競合他社と比較して補強が必要であると認識している領域(サービスに対する認知の向上、若年層利用者の取り込み、電子書籍アプリの強化、先行・独占・オリジナル等のコンテンツ強化等)への投資、(c)消費者ニーズの変化に対する迅速な対応(スマートフォンに特化した縦スクロールのカラーコンテンツの拡充、無料で読めるコンテンツの拡充等)及び(d)今後成長が見込まれるグローバル市場への積極的な展開といった各課題を解決していく必要があるものと認識しているとのことです。これらの各課題については、早期の解決を図っていくことが必要であるものの、他方、現状のヤフー及びZホールディングスとの間の提携関係のみでは、その実現に相応の期間が必要となるものと考えており、対象者としても、外部企業との間の資本提携を含むパートナーシップの構築の必要性について検討を行っていたとのことです。そのような状況下、上記のとおり、2021年6月1日、公開買付者との間で、本業務提携を開始いたしましたが、対象者としては、公開買付者との間には資本関係はなく独立した当事者間の協業であることや上場を維持することにより一般株主の皆様の利益に配慮する必要性があること等から、本業務提携に関し、経営資源・人材の相互活用や意思決定のスピードなどにおいて、一定の限界があるものと認識しているとのことです。そこで、対象者は、本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、以下のメリットをより効率的に享受できることが見込まれ、対象者の収益基盤と事業競争力の強化に繋がり、中長期的にも対象者の企業価値の持続的な向上に資するとの結論に至ったとのことです。
(ⅰ) バックエンド業務の共通化による経営の強化
公開買付者との間で、既に2021年6月、公開買付者が運営する「LINEマンガ」のバックエンド業務の一部を対象者が受託する本業務提携を実施しているとのことです。本業務提携におけるバックエンド業務は、電子書籍配信に関するバックエンドシステムの開発・運用、配信コンテンツの入稿、書誌データ管理に関するオペレーション、電子書籍コンテンツの調達及び提供を指しており、「LINEマンガ」の同業務を対象者が受託するとともに、「ebookjapan」の同業務との共通化を進めることを目指しているとのことです。本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、意思決定の迅速化や公開買付者と対象者間での人員交流等が促進され、バックエンド業務の共通化に向けた連携がより強固なものとなり、取扱規模の拡大及び出版社窓口の一本化の結果、事業効率の改善及び出版社への営業力の強化、並びにコンテンツ力の向上を着実に図ることを見込んでいるとのことです。
(ⅱ) 販売作品数の増加によるユーザーの獲得
公開買付者が運営する「LINEマンガ」は、配信作品数約60万点の国内最大級のコミックサービスであり、特にオリジナル・独占・先行配信作品を480タイトル以上取り揃えているとのことです。グローバル市場で多くのユーザーの人気を得ている縦スクロールのカラー作品であるWEBTOON等、対象者には少ないオリジナル作品を多数有しており、これらを「ebookjapan」でも販売可能とすることにより、ユーザーの獲得並びに収益の拡大に繋がると考えているとのことです。
(ⅲ) マーケットにおける利用者層の拡大
「LINEマンガ」は主にiOS、Androidアプリで多くの利用者を獲得しているのに対し、「ebookjapan」は WEB ブラウザで多くの利用者を獲得しており、また、利用者層においても比較的若年層が多い「LINEマンガ」と、中高年層を含めた幅広い利用者を持つ「ebookjapan」とで、それぞれ異なる強みを持っているとのことです。これらは、相互に補完し合う関係にあり、今後両社が持つマーケティングソリューションを最大限活用し、統一されたブランドマーケティングを行うことで、WEBブラウザ、アプリの両方に強みを持ち、若年層から中高年層まで幅広い年齢層の利用者に支持される国内随一の電子書籍サービスグループとなることが可能と考えているとのことです。
以上の点を踏まえて、対象者は、2021年9月30日、本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、公開買付者との間で電子書籍事業の幅広い分野において互いの強みを活かし、さらなる連携強化を図ることは、対象者の中長期的な企業価値向上に資するものであるとの考えに至ったとのことです。
さらに、(a)本公開買付価格が、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の大和証券による対象者株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価平均法に基づく算定結果の上限を上回るものであり、かつ、以下DCF法に基づく評価レンジの範囲内であり、かつ中央値(DCF法による算定の基礎となる割引率及び永久成長率について、その感応度分析において用いた数値の中央値を使用して算出された対象者株式の1株当たりの株式価値)の4,788円と遜色ない価格であると認められること、(b)本公開買付価格が、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日(なお、対象者は、公開買付者らから、2021年6月1日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せているとの説明を受けていたとのことですが、対象者としては、当該可能性を合理的に検証することができないことから、他の同種の案件において一般的である、公表日の前営業日を基準とした一定期間の株価のプレミアムを考慮しているとのことです。)である2021年9月29日の直近1ヵ月間の終値単純平均値4,000円に対して18.75%のプレミアムを加えた価格、直近3ヵ月間の終値単純平均値3,697円に対して28.48%のプレミアムを加えた価格、直近6ヵ月間の終値単純平均値3,274円に対して45.08%のプレミアムを加えた価格であり、このうち、直近1ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアム率を取り上げると、直近約2年間(2019年8月以降)に公表された公開買付けを利用した支配株主による完全子会社化事例におけるプレミアム水準(中央値が36%程度から41%程度)に照らして、必ずしも高い水準であるとは言い難いものの、直近3ヵ月間の終値単純平均値及び直近6ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアムに鑑みれば、本公開買付価格は相応のプレミアムが付された価格であると評価できること、(c)本公開買付価格は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値4,510円に対して5.32%のプレミアムを加えた価格であり、当該プレミアムについては、非公開化を目的とした他の公開買付けの事例におけるプレミアム水準との比較において低水準であると考えられるものの、2021年9月27日以降、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日までの3日間において対象者株式の株価が急激に変動していること、及び、本公開買付価格は、対象者が2011年10月に東京証券取引所マザーズ市場にその株式を上場して以来の市場株価の最高値を超える水準であることを勘案すると、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日における対象者株式の終値に対するプレミアムが低水準であることをもって、本公開買付価格の合理性が欠けることになるものではないと考えられること、(d) 本公開買付価格の決定に際しては、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置が採られており、少数株主の利益への配慮がなされていると認められること、(d)本公開買付価格が、上記の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置が採られた上で、公開買付者らと対象者との間で、それぞれ独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が行われた上で決定された価格であること等を踏まえ、対象者は、2021年9月30日、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
同様に、本新株予約権買付価格についても、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者株式数(第10回新株予約権及び第11回新株予約権については200、第12回新株予約権ないし第17回新株予約権については100)を乗じた金額をもとに算定されているものであるため、本公開買付けは、対象者の新株予約権者の皆様に対して合理的な本新株予約権の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
以上より、対象者は、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。対象者取締役会決議の詳細については、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
③ 本公開買付け後の経営方針
本公開買付け後の対象者の事業に係る公開買付者らの戦略や将来の事業戦略については、上記「① 本公開買付けの目的及び背景」の(ⅰ)ないし(ⅳ)の期待される事業シナジーをもとに、公開買付者らと対象者との間で今後協議の上、決定していくことになります。なお、公開買付者らは、本公開買付け後も、対象者の事業の特性や対象者の強みを十分に活かした経営を行い、対象者の事業の強化を図ってまいります。また、公開買付者らは、本公開買付け後の対象者の経営体制に関して、現状の対象者の経営体制を尊重しつつ、これを維持すること及びこれに加えて公開買付者らから対象者への役員の派遣を想定しておりますが、公開買付者らから対象者へ派遣する役員の人数等を含め現時点で具体的に決定された事実はございません。
下記「(4) 本公開買付けに関する重要な合意」に記載のとおり、公開買付者、NAVER及びZホールディングスは、本公開買付けの成立後、今後の「ebookjapan」の運営につき、その見直し・改定の要否を含め、誠実に協議する予定です。
(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
本書提出日現在において、対象者は公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当いたしませんが、公開買付者は、本公開買付け後、本書提出日現在対象者株式2,443,600株(所有割合43.18%)を所有し対象者を連結子会社としているヤフーを株主として残して、本スクイーズアウトを実施することを予定していることから、対象者の少数株主と利害が一致しない可能性があることを踏まえ、公開買付者及び対象者は、対象者の少数株主の皆様への影響に配慮し、本公開買付価格の公正性を担保しつつ、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、以下のような措置を実施いたしました。
なお、以下の記載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。また、公開買付者は、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」の応募を本公開買付け成立の条件とはしておりませんが、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、ヤフーは、本書提出日現在、対象者株式を2,443,600株(所有割合:43.18%)所有していることから、本公開買付けにおいて、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」の買付予定数の下限を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応募することを希望する一般株主の皆様の利益に資さない可能性もあるものと考えております。また、公開買付者及び対象者において以下①ないし⑤の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
① 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、2021年6月9日、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、東京証券取引所に独立役員として届け出ている対象者の社外取締役及び社外監査役のうち、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立した、寺田航平氏(対象者独立社外取締役、寺田倉庫株式会社代表取締役社長)、小林雅人氏(対象者独立社外取締役、シティユーワ法律事務所パートナー)、高橋鉄氏(対象者独立社外監査役、ITN法律事務所代表パートナー)の3名から構成される本特別委員会を設置したとのことです。なお、本特別委員会の委員は設置当初から変更されていないとのことです。本特別委員会の委員長については、対象者取締役会の構成員として経営判断に直接関与する立場にあり、対象者の事業に相当程度の知見を有していること、また、本公開買付けを含む本取引を検討する見識・適格性を有すること等を踏まえ、委員の互選に基づき、寺田航平氏が就任しているとのことです。また、本特別委員会の委員の報酬については、取引の成否にかかわらず時間単位の報酬のみとされており、本取引の成立を条件とする成功報酬は含まれていないとのことです。対象者取締役会は、本特別委員会設置の決定に資し、本特別委員会に対し、(a)本公開買付けについて対象者取締役会が賛同するべきか否か、及び、対象者の株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨するべきか否かを検討し、対象者取締役会に勧告を行うこと、(b)本非公開化取引についての対象者取締役会による決定((ⅰ)本公開買付けに賛同の意見を表明し、対象者の株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決定、及び、(ⅱ)本公開買付け後に行われる株式の併合等による非公開化手続きに係る決定をいう。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでないかを検討し、対象者取締役会に意見を述べること(上記の勧告及び意見に際しては、①本非公開化取引の目的が正当性を有するか、②本非公開化取引に係る手続きの公正性が確保されているか、③本非公開化取引の取引条件の妥当性が担保されているかについて検討するものとする。また、本非公開化取引に関する交渉状況等に応じて、本特別委員会が必要又は適切と認める場合は、本特別委員会は、上記諮問事項を追加又は変更することができる。)を諮問(以下「本諮問事項」といいます。)し、これらの点についての答申書を対象者に提出することを委嘱したとのことです。また、対象者は、2021年6月9日付の上記取締役会において、(a)取締役会における本取引に関する意思決定は、本公開買付けへの賛否及び応募推奨の有無を含め、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うこと、(b)本特別委員会が本非公開化取引の取引条件が妥当でないと判断した場合、対象者取締役会は本取引の承認を行わないこととすることを併せて決議しているとのことです。さらに、対象者は、上記取締役会において、本特別委員会に対し、(a)対象者が公開買付者らとの間で行う交渉の過程に実質的に関与すること(必要に応じて公開買付者らとの交渉方針に関して指示又は要請を行うこと、及び、自ら公開買付者らとの交渉を行うことを含みます。)、(b)本諮問事項に関する答申を行うに際し、必要に応じ、自らの財務もしくは法務等に関するアドバイザーを選任し(この場合の費用は対象者が負担する。)、又は、対象者の財務もしくは法務等に関するアドバイザーを指名しもしくは承認(事後承認を含みます。)すること、(c)必要に応じ、対象者の役職員から本非公開化取引に関する検討及び判断に必要な情報を受領すること及び(d)その他本非公開化取引に関する検討及び判断に際して必要と本特別委員会が認める事項に関する権限を付与したとのことです。
本特別委員会は、2021年6月16日より2021年9月30日までの間に合計20回、合計約24時間開催され、本諮問事項についての協議及び検討が慎重に行われたとのことです。具体的には、本特別委員会は、対象者の第三者算定機関かつファイナンシャル・アドバイザーである大和証券及びリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所につき、いずれも独立性及び専門性に問題がないことから、それぞれ対象者のファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザーとして承認したとのことです。
その後の具体的な審議状況として、本特別委員会は、①対象者に対して質問事項を提示し、対象者との間で、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等についてインタビュー形式により質疑応答を実施し、②別の会合において、NAVERに対して質問事項を提示し、同社との間で、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等についてインタビュー形式により質疑応答を実施したとのことです。
また、本特別委員会は、対象者が作成した本事業計画について、対象者からその内容及び作成経緯等について説明を受けるとともに、これらの事項について合理性を確認しているとのことです。そして、大和証券からの、本事業計画を基礎として行った株式価値算定の内容、DCF法及びDCF法における割引率の計算根拠を含む重要な前提条件についての説明も踏まえて、質疑応答及び審議・検討を行った上で、これらの事項について合理性を確認しております。
さらに、本特別委員会は、対象者、大和証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、本取引の手続面における公正性を担保するための措置並びに本取引に係る対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の利益相反を回避するための措置の内容について説明を受け、本取引において手続きの公正性を確保するために講じるべき措置について審議・検討を行っているとのことです。
また、本特別委員会は、大和証券から受けた財務的見地からの助言を踏まえ、公開買付者からより高い価格を引き出すために、相互に独立した第三者間のM&Aで行われる一般的な交渉プロセスに即して十分な交渉を実施することを含む交渉方針について審議・検討するとともに、本特別委員会が公開買付者らから公開買付価格に関する提案を受領する都度、大和証券から受けた財務的見地からの助言も踏まえて公開買付者らに対する交渉方針を審議・検討した上で、公開買付者らと直接書面のやり取りを行うこと等により、公開買付者らとの間で公開買付価格に関する協議・交渉を行ったとのことです。
具体的には、2021年8月10日に公開買付者らより公開買付価格を1株当たり4,000円とすることを含む提案書を受領したのに対し、本特別委員会は、大和証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から聴取した意見を踏まえて検討を行った上で、提案された公開買付価格は公正な価格に達しておらず、対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないとして、公開買付者らに対し公開買付価格の再検討を要請したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、公開買付価格を1株当たり4,250円とする提案を受領したとのことです。当該提案を受け、対象者は、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである大和証券を通じて、公開買付者らとの間で協議を継続いたしましたが、本特別委員会は、当該大和証券を通じた協議の内容並びに大和証券からの財務的見地からの助言及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的見地からの助言を踏まえ、NAVERに対し、上記の提案価格は、大和証券によりDCF法に基づき算定される株式価値の水準に照らし、引き続き対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないと考えていること等を理由として、再度公開買付価格の再考を依頼したとのことです。その後も公開買付者らとの間で、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである大和証券を通じて、継続的に協議及び交渉を行い、その結果、本特別委員会は、2021年9月24日、公開買付者らから、本公開買付価格を4,750円とすることを含む最終提案を受けるに至ったとのことです。
また、本特別委員会は、公開買付者らとの間で、本新株予約権買付価格についても、協議・交渉を行っているとのことです。具体的には、対象者は、公開買付者らより、上記の2021年8月10日付の提案書において、本新株予約権買付価格について、新株予約権1個につき1円とする提案を受けたとのことです。これに対し、本特別委員会は、2021年8月13日、公開買付者らに対し、当該新株予約権は、対象者役職員に対する報酬制度として付与しているものであり、特に、当該新株予約権の内、現時点では行使不可であるものの、保有者に多大な経済的価値が見込まれる新株予約権を適切な価格で買い取らないとすると、保有者である対象者従業員のモチベーションが大きく低下し、非公開化後の経営統合プロセスに支障をきたす事が想定されることから、権利行使をした場合に利益が出る状態にある新株予約権については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とするように再考を依頼したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、新株予約権に係る買付価格については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とする旨の提案を受けるに至ったとのことです。
本特別委員会は、以上の経緯の下、大和証券株式価値算定書等も考慮し、本諮問事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、2021年9月30日付で、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の答申書を提出しているとのことです。
(ⅰ) 答申内容
a 対象者取締役会は、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者株主及び本新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨するべきであると考えられる。
b 対象者取締役会が、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を決定することは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられる。また、対象者取締役会が、本取引において予定されている方法によることを前提に、本公開買付け成立後の本株式併合による対象者の非公開化についての決定をすることは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられる。
(ⅱ) 答申理由
ⅰ 本取引が対象者の企業価値向上に資するものであり、その目的は正当なものであると認められるかについて
・世界的にみても市場規模が大きく、また、エンターテインメントサービスの源泉となる知的財産権が多く存在する日本の電子コミック市場は、多数の競合他社が存在する極めて競争環境の厳しい市場である。対象者は、かかる厳しい競争環境を勝ち抜き、電子書籍分野での国内取扱高No.1を獲得するためには、収益基盤と事業競争力の強化がその経営課題であると認識し、現在、Zホールディングスグループとのシナジー強化に取り組んでいる。もっとも、対象者によれば、競争の激しい国内電子コミック市場において、国内取扱高No.1という対象者の目標を達成するためには、(a)競合他社を上回る規模・効率での広告・販促活動や投資の継続、(b)対象者が競合他社と比較して補強が必要であると認識している領域(サービスに対する認知の向上、若年層利用者の取り込み、電子書籍アプリの強化、先行・独占・オリジナル等のコンテンツ強化等)への投資、(c)消費者ニーズの変化に対する迅速な対応(スマートフォンに特化した縦スクロールのカラーコンテンツの拡充、無料で読めるコンテンツの拡充等)及び(d)今後成長が見込まれるグローバル市場への積極的な展開といった各課題を解決していく必要があり、これらの各課題については、早期の解決を図っていくことが必要である一方で、現状のヤフー及びZホールディングスとの間の提携関係のみでは、その実現に相応の期間が必要となるものと考えており、外部企業との間の資本提携を含むパートナーシップの構築の必要性について検討を行っていたとのことである。
・公開買付者らの提案する、①公開買付者及び対象者の利用者の拡大、②人気IPの創出と獲得、③マーケティング戦略の統一と効率化、④サービス開発、インフラ基盤の安定と強化等の本取引によるシナジー及び本取引後の企業価値向上施策は、上記の対象者の経営課題の解決に資するものである。また、アプリを通じたコンテンツ配信に強みを持つ公開買付者とWEBを通じたコンテンツ配信に強みを持つ対象者が相互補完的に互いのプラットフォームを活用しつつ、より効率的に潜在的な顧客を獲得すると同時に、日本における優良マンガコンテンツの配信を行う対象者がコンテンツ配信を海外で展開する公開買付者らのグループに加入することで日本の優良マンガコンテンツのグローバルでの存在感の向上が可能であり、より広範な顧客層を対象として対象者のコンテンツ配信が可能になるという公開買付者らの説明は合理的であり、対象者にとって、本取引は、国内市場における競争力強化のみならず、グローバル市場への展開にも資するものと評価し得る。
・本取引後の各施策については、対象者は既に公開買付者との間でバックエンド業務に関する業務提携を実施しており、現在の資本構成の下でも実施可能なのではないかとの点が問題となり得るが、対象者によれば、公開買付者との間には資本関係はなく独立した当事者間の協業であることや上場を維持することにより一般株主の利益に配慮する必要性があること等から、当該業務提携に関しては、経営資源・人材の相互活用や意思決定のスピードなどにおいて、中長期的な成長を実現する上で一定の限界があると認識していたとのことである。本取引を実施して対象者が公開買付者の完全子会社となり、バックエンド業務に限らない分野も含めて両社がより密接に連携することで、上記のような厳しい市場環境において、対象者の収益基盤と事業競争力の強化に繋がり、スピード感をもって中長期的にも両社の成長戦略及び企業価値向上策を一体的に実現していくことが可能になるとのことである。
・公開買付者らの提案に対し、対象者の経営陣からは、①本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、意思決定の迅速化や公開買付者と対象者間での人員交流等が促進され、バックエンド業務の共通化に向けた連携がより強固なものとなり、取扱規模の拡大及び出版社窓口の一本化の結果、事業効率の改善及び出版社への営業力の強化、並びにコンテンツ力の向上を着実に図ることができること、②公開買付者が運営する「LINEマンガ」のオリジナル作品を「ebookjapan」でも販売可能とすることにより、ユーザーの獲得及び収益の拡大に繋がること、③アプリで多くの利用者を獲得し、利用者層においても比較的若年層が多い「LINEマンガ」と、WEB ブラウザで多くの利用者を獲得し、中高年層を含めた幅広い利用者を持つ「ebookjapan」は利用者層が異なり、相互に補完し合う関係にあるところ、今後両社が持つマーケティングソリューションを最大限活用し、統一されたブランドマーケティングを行うことで、WEBブラウザ、アプリの両方に強みを持ち、若年層から中高年層まで幅広い年齢層の利用者に支持される国内随一の電子書籍サービスグループとなることが可能となること等から、本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、公開買付者との間で電子書籍事業の幅広い分野において互いの強みを活かし、さらなる連携強化を図ることは、対象者の中長期的な企業価値の向上に資するものと考えているとの見解が示された。
・公開買付者らによれば、対象者及び公開買付者らの間でのシナジーを最大限発揮していく観点からは、対象者と密接な競業関係にあるヤフー及びその親会社であるZホールディングスとこれまで以上に緊密に連携していくことが不可欠であり、本取引後もヤフー及びZホールディングスと対象者の既存の協業関係は維持・継続する方針とのことである。
・対象者の親会社であるヤフーは本公開買付けに応募しないことが予定されているが、公開買付者らによれば、その目的は、本取引後もWEBTOON Entertainmentへの出資を間接的に継続し、本取引の実行により対象者に生まれるシナジーの一部を享受することができるZホールディングスグループと、本取引により対象者の株主ではなくなる一般株主との間で同一の価格で対象者株式を評価することは一般株主に不利益をもたらすとの考えから、ヤフーが所有する対象者株式を本公開買付価格より低い価格で評価するため、公開買付者がまず対象者が所有する自己株式及びヤフーの所有する株式を除く対象者株式の全てを本公開買付け及び株式併合により取得し、その後ヤフーが所有する対象者株式を本三角株式交換により取得するスキームを採用することとしたものであり、かかる説明に特段不合理な点は認められない。
・対象者は、本取引によって対象者は非公開化されることとなるが、韓国最大のインターネット・サービス企業である公開買付者らのグループの一員として十分な社会的信用力、知名度を維持するものであるから、資本市場からのエクイティによる資金調達の容易性が失われることによる影響や優れた人材の確保及び取引先の拡大等に与える影響は限定的であり、対象者の企業価値を毀損するものではないと考えられる。
ⅱ 本取引に係る手続きの公正性は確保されていると認められるかについて
・本取引においては、公開買付者、対象者、NAVER、ヤフー及びZホールディングスから独立した本特別委員会が、本取引に係る取引条件等の形成過程の初期段階から設置され、アドバイザー等の選任・承認権限や本取引の取引条件等の交渉過程に実質的に関与する権限が付与された上、本特別委員会の答申内容を最大限尊重して本取引に係る意思決定を行うものと決議されているところ、本特別委員会はこれらの権限を行使して、直接の交渉主体として、公開買付者との間の取引条件に関する交渉を行った。
・本特別委員会及び対象者は、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、各種のアドバイスを受けている。
・特別委員会及び対象者は、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したファイナンシャル・アドバイザーである大和証券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼し、2021年9月29日付で大和証券株式価値算定書を取得している。
・対象者においては、利害関係を有する取締役等を本取引の検討・交渉過程から除外し、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立した立場で検討・交渉等を行うことができる体制が構築されていたものと認められる。
・本公開買付けにおいては、いわゆる間接的なマーケット・チェックが行われているものと認められる。
・本公開買付けにおいては、公開買付期間が法令に定められた最短期間である20営業日を超える31営業日に設定されている。
・本公開買付けにおいては、一般株主による十分な情報に基づく適切な判断の機会が確保される予定であると認められる。
・本取引においては、本公開買付けの決済完了後、公開買付者は速やかに本株式併合にかかる臨時株主総会の開催を対象者に要請し、また、本株式併合に際して株主に交付される予定の金銭の額を本公開買付価格と同額に設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定であることから、強圧性が排除されているものと認められる。
・本公開買付けにおいては、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)条件が設定されていないものの、本公開買付けが成立した場合に公開買付者及びヤフーが対象者の議決権数の3分の2以上を所有することとなるようにするため、1,328,800株(所有割合:23.48%)が買付予定数の下限として設定される予定である。かかる下限は、相当程度の一般株主の応募がなければ本公開買付けが成立しないという意味において、一定程度の公正性担保措置として機能すると考えられ、また、本取引においては、他に十分な公正性担保措置が講じられていることからすれば、マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)が設定されていないとしても、それのみにより本取引における手続きの公正性が損なわれるものではないと考えられる。
ⅲ 一般株主の利益を図る観点から、取引条件の妥当性は確保されていると認められるかについて
・本取引の買収の方法について、一段階目として本公開買付けを行い、二段階目として本株式併合を行う方法は、本取引のような非公開化の取引においては一般的に採用されている方法である。
・本取引の取引条件に係る協議・交渉過程においては、公開買付者らによる最終意向表明書の提出後も、本特別委員会の要請に基づき、これ以上の価格交渉が困難であると判断されるまで協議・交渉を繰り返し、結果として公開買付者らから有意な譲歩(当初の4,000円から750円(18.7%)増額された4,750円という提案)を引き出した本公開買付価格が提案されている等、本特別委員会の実質的な関与のもと、企業価値を高めつつ少数株主にとってできる限り有利な取引条件で本取引が行われることを目指した合理的な努力が行われる状況が確保されていたものと認められる。
・大和証券株式価値算定書におけるDCF法に基づく算定の基礎とされている対象者の事業計画の策定目的、策定手続及び内容につき特に不合理な点はないと認められる。対象者によれば、本業務提携の具体的な業務は開始していないため、その影響については引き続き精査中であること、また、本取引が実施されないとの前提を置く場合、本業務提携が解消される可能性もあることから、本業務提携が対象者の業績に与える影響については、本事業計画には織り込まれていないとのことであるが、本取引が実施されないとの前提を置く場合に本業務提携が解消される可能性があるとの対象者の説明に不合理な点はなく、リーガル・アドバイザー、ファイナンシャル・アドバイザーの助言も経た上で、対象者のスタンドアロンベースの事業計画において本業務提携の影響が織り込まれていないことに不合理な点はないと認められる。
・大和証券株式価値算定書の内容は、算定の方法及び内容のいずれにおいても不合理な点は認められず、信用できるものと判断するところ、本公開買付価格は、大和証券株式価値算定書の市場株価平均法に基づく算定結果の上限を上回り、DCF法に基づく評価レンジの範囲内にあり、かつ中央値(DCF法による算定の基礎となる割引率及び永久成長率について、その感応度分析において用いた数値の中央値を使用して算出された対象者株式の1株当たりの株式価値)の4,788円と遜色ない価格であると認められる。
・本公開買付価格は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日の直近1ヵ月間の終値単純平均値4,000円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値について同じです。)に対して18.75%のプレミアムを加えた価格、直近3ヵ月間の終値単純平均値3,697円に対して28.48%のプレミアムを加えた価格、直近6ヵ月間の終値単純平均値3,274円に対して45.08%のプレミアムを加えた価格であり、このうち、直近1ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアム率を取り上げると、直近約2年間(2019年8月以降)に公表された公開買付けを利用した支配株主による完全子会社化事例におけるプレミアム水準(中央値が36%程度から41%程度)に照らして、必ずしも高い水準であるとは言い難いものの、直近3ヵ月間の終値単純平均値及び直近6ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアムに鑑みれば、本公開買付価格は相応のプレミアムが付された価格であると評価できると考えられる。他方で、本公開買付価格は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値4,510円に対して5.32%のプレミアムを加えた価格であり、当該プレミアムについては、非公開化を目的とした他の公開買付けの事例におけるプレミアム水準との比較においてプレミアムが低水準であると考えられるものの、2021年9月27日以降、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日までの3日間において対象者株式の株価が急激に変動していること、及び、本公開買付価格は、対象者が2011年10月に東京証券取引所マザーズ市場にその株式を上場して以来の市場株価の最高値を超える水準であることを勘案すると、公表日の前営業日における対象者株式の終値に対するプレミアムが低水準であることをもって、本公開買付価格の合理性が欠けることになるものではないと認められる。
・本新株予約権買付価格は、それぞれ、本公開買付価格と行使価格の差額に目的株式数を乗じた額とされており、本公開買付価格と同等の水準にあると認められる。
・(a)本三角株式交換における株式交換比率は、①ヤフーの所有する対象者株式の1株当たり価値を、本公開買付け価格において公開買付者が市場価格に対して反映するプレミアムを考慮せず、3,529円(本公開買付価格の最終提案日である2021年9月24日までの過去1ヵ月間(2021年8月25日から2021年9月24日まで)における対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値単純平均値に対して公開買付者ら及びZホールディングス間で協議して定めた一定のディスカウントを行った価格とすること、②本三角株式交換の対価として交付されるWEBTOON Entertainment株式の1株当たり価値を、NAVERが行うWEBTOON Entertainmentへの出資における1株当たり払込価格と同額として定めること、並びに、(b)本三角株式交換の効力発生後にNAVERが所有するWEBTOON Entertainment株式及び議決権と、Zホールディングスグループが所有するWEBTOON Entertainment株式及び議決権の比率が、本公開買付け公表日における当該比率である66.6%:33.4%と等しくなるように調整し、もって本取引を通じたNAVER及びZホールディングスグループによるWEBTOON Entertainment株式の取得が出資比率に応じた比例的なものとなることが予定されており、それにより、NAVER及びZホールディングスグループの間で利益移転が生じないように配慮されており、本三角株式交換が対象者の一般株主に比して有利なものとならないことが確保されるものと評価できる。
・本公開買付価格、本新株予約権買付価格及び本三角株式交換における株式交換比率以外の本取引の取引条件に関しても、対象者の一般株主の犠牲のもとに、公開買付者ら及びZホールディングスグループが不当に利益を得るものと認めるべき事由は確認されておらず、本取引の取引条件の妥当性を害する事情は見当たらない。
・以上のとおり、対象者の一般株主の利益を図る観点から、本取引の取引条件の妥当性は確保されていると考えられる。
ⅳ 対象者取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行うことの是非について
・上記ⅰのとおり、本取引は対象者の企業価値向上に資するものと認められ、本取引の目的は正当なものと考えられるため、対象者取締役会は、本公開買付けについて賛同すべきであると考えられる。
・また、上記ⅱのとおり、本取引においては、一般株主利益を確保するための公正な手続きが実施されており、上記ⅲのとおり、本取引の取引条件の妥当性は確保されていると考えられるため、対象者取締役会は、本公開買付けへの応募を推奨すべきであると考えられる。
ⅴ 上記ⅰからⅳを踏まえて、本取引が対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考えられるかについて
・上記ⅰからⅳを踏まえれば、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を決定することは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられ、また、対象者取締役会が、本取引において予定されている方法によることを前提に、本公開買付け成立後の本株式併合についての決定をすることは、対象者の一般株主にとって不利益ではないと考えられる。
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書・意見書の取得
(ⅰ) 対象者株式に係る算定の概要
対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者から提示された本公開買付価格を検討し、本公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨を行うにあたり、公正性を担保するための措置として、対象者、ヤフー及び公開買付者から独立した第三者算定機関である大和証券に対して、対象者株式の株式価値算定を依頼し、大和証券から2021年9月29日付で大和証券株式価値算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、大和証券から本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。
大和証券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者株式が東京証券取引所市場第一部に上場していることから市場株価平均法を、対象者業績の内容や予想等を評価に反映するためにDCF法を用いて対象者株式の株式価値の算定を行い、対象者は大和証券から2021年9月29日付で、大和証券株式価値算定書を取得しているとのことです。
大和証券によれば、対象者株式の株式価値算定にあたり、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。
市場株価平均法 3,274円から4,510円
DCF法 4,043円から5,814円
市場株価平均法では、2021年9月29日を算定基準日として、対象者株式の東京証券取引所市場第一部における基準日終値4,510円、直近1ヵ月間の終値単純平均値4,000円、直近3ヵ月間の終値単純平均値3,697円及び直近6ヵ月間の終値単純平均値3,274円をもとに、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲は、3,274円から4,510円までと算定しているとのことです。
DCF法では、対象者が作成した本事業計画に基づく収益予測や投資計画等、合理的と考えられる前提を考慮した上で、対象者が2022年3月期第2四半期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を分析し、1株当たりの株式価値の範囲は、4,043円から5,814円までと算定しているとのことです。なお、割引率は9.1%~11.1%を採用しており、継続価値の算定については永久成長法を採用し、永久成長率を0.0%~1.0%として算定しているとのことです。
大和証券がDCF法において前提とした本事業計画に基づく財務予測は以下のとおりとのことです。なお、本事業計画には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2022年3月期から2027年3月期にかけて、電子書籍事業の市場拡大を背景とした電子書籍サービス「ebookjapan」の取扱高拡大により、継続的な増益を見込んでいるとのことです。2022年3月期から2024年3月期にかけては、グループシナジーのさらなる深化や広告宣伝を中心とした積極的なマーケティング投資によるユーザー獲得拡大を想定しており、アプリ及びウェブサイトの機能改善、オリジナル作品のラインアップ拡大等も相まって、継続的な取扱高の拡大を見込んでいるとのことです。その結果としての限界利益の増加、及び事業規模拡大に伴う固定費負担の軽減を踏まえ、2022年3月期及び2024年3月期は、大幅な増益を見込んでいるとのことです。その後、2025年3月期においては、ユーザー獲得のためのマーケティング投資が一巡する事に伴い売上高広告宣伝費率を抑制することで、大幅な増益を見込んでいるとのことです。また、本取引実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、本事業計画には加味していないとのことです。なお、本業務提携が業績に与える影響については、本業務提携に基づく取り組みの範囲、時期等について当事者間で協議中であり、その影響についても引き続き精査中であること、また、本取引が実施されないとの前提を置く場合には、本業務提携が解消される可能性もあることから、本事業計画には織り込んでおりません。
(単位:百万円)
(ⅱ) 本新株予約権に係る算定の概要
本新株予約権買付価格に関しては、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者株式数(第10回新株予約権及び第11回新株予約権については200、第12回新株予約権ないし第17回新株予約権については100)を乗じた金額をもとに算定されているものであるため、本公開買付けは、対象者の本新株予約権者の皆様に対して合理的な本新株予約権の売却の機会を提供するものであると判断しているとのことです。
なお、本新株予約権はいずれも、譲渡による取得については対象者取締役会の承認を要するものとされておりますが、対象者は、本新株予約権の譲渡が可能となるよう、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けの成立を条件として、本新株予約権の新株予約権者の皆様が、その所有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより公開買付者に対して譲渡することについて包括的に承認すること、及び譲渡を希望する本新株予約権者との間では新株予約権割当契約の内容を変更し譲渡可能な内容とする旨を決議しているとのことです。
③ 対象者における独立した法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定過程における透明性及び合理性を確保するため、2021年6月上旬、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けにおける意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けにおける意思決定にあたっての留意点について、必要な法的助言を受けているとのことです。また、アンダーソン・毛利・友常法律事務所は対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。
④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
対象者プレスリリースによれば、対象者は、大和証券から取得した大和証券株式価値算定書、本特別委員会から提出された答申書、アンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的助言その他の関連資料を踏まえ、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件について、慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
その結果、対象者は、2021年9月30日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
当該取締役会においては、対象者の取締役のうち、津留崎耕平氏及び秀誠氏は、ヤフーの執行役員兼任者であること、高橋将峰氏は、ヤフーの出身者(2019年4月付で対象者に転籍)であることから、利益相反のおそれを回避し、本取引の公正性を担保する観点から、(ア)まず対象者の取締役5名のうち、津留崎耕平氏、秀誠氏及び高橋将峰氏を除く、2名の取締役において審議の上、その全員一致により上記の決議を行い、さらに、対象者取締役会の定足数を確保する観点から、(イ)高橋将峰氏を加えた3名の取締役において改めて審議の上、その全員一致で再度上記の決議を行うという二段階の決議を経ているとのことです。また、上記の取締役会に出席した監査役(監査役3名中、出席監査役2名(うち社外監査役2名))の全員が上記決議につき異議はない旨の意見を述べているとのことです。
なお、対象者の取締役のうち、津留崎耕平氏及び秀誠氏の2名は、本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題による影響を受けるおそれを排除する観点から、上記2021年9月30日開催の対象者取締役会を含む本取引に係る対象者取締役会の審議及び決議には参加しておらず、かつ、対象者の立場において、本取引に係る検討並びに公開買付者との協議及び交渉に参加していないとのことです。
また、高橋将峰氏は、取締役会の定足数を確保する観点から上記取締役会の二段階目の審議及び決議に参加したものの、ヤフーの出身者であることから、利益相反のおそれを回避し、本取引の公正性を担保する観点から、対象者の立場において本取引に関する検討並びに公開買付者との協議及び交渉には参加していないとのことです。
また、対象者の監査役である鬼塚ひろみ氏はヤフーの監査役を兼務していることから、上記の取締役会の審議には一切参加しておらず、上記の取締役会の決議に対して意見を述べることを差し控えているとのことです。
⑤ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、比較的長期間である31営業日としております。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主及び新株予約権者の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、本公開買付価格の適正性も担保することを企図しております。さらに、公開買付者と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定と合わせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保にも配慮しております。
(4) 本公開買付けに関する重要な合意
本公開買付けの実施に際して、公開買付者は、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、NAVER及びZホールディングスとの間で、2021年9月30日付で本取引契約を締結しております。
本取引契約においては、①本不応募株式について、ヤフーをして本公開買付けに応募させないこと、②本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの公開買付期間末日以後、決済の開始日前にNAVERがWEBTOON Entertainmentを通じて公開買付者に対して本出資を行うこと、③本公開買付けの成立後に、本株式併合により対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすること、④本スクイーズアウトの完了後に、本三角株式交換を実行すること、⑤本三角株式交換の対価は下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり決定とすること、⑥本三角株式交換の効力発生後に、本グループ内移転を行うこと、⑦本三角株式交換の効力発生後に、本追加出資を行うこと、⑧本公開買付けの成立後、各当事者は対象者及びヤフーの間の2021年3月23日付「プラットフォームサービスの提供等に関する契約書」(「ebookjapan」の運営に関して必要となる事項を含みます。)につき、その見直し・改定の要否を含め、誠実に協議すること、⑨各当事者は、本取引の実行に関して必要となる各国における競争法令等及び投資規制法令等上の手続き(許認可等の取得及び必要な待機期間又は審査期間の経過を含みます。)を、実務上可能な限り速やかに完了させるために合理的な範囲で各自努力し、互いに協力すること、⑩Zホールディングスが、本取引契約の締結日から本取引完了日までの間、本不応募株式に係る株主としての権利に基づき合理的に可能な範囲において、本取引契約において企図される取引を除き、対象者をして、従前の慣行に従った通常の業務の範囲内において、その業務を行わせるとともに、一定の行為を実施させないこと(注1)、⑪NAVERが、本取引契約の締結日から本取引完了日までの間、本取引契約において企図される取引を除き、WEBTOON Entertainment及びその子会社をして、従前の慣行に従った通常の業務の範囲内において、その業務を行わせること、⑫各当事者は、本取引完了日をもって、対象者及びヤフーの間の2016年6月9日付「資本業務提携契約」を終了させることを相互に確認し、Zホールディングスはヤフーをして、公開買付者は対象者をして、当該終了に係る合意を行わせることを合意しております。
(注1) 対象者による実施が制限される「一定の行為」とは、(ⅰ)定款その他の重要な社内規程の変更、(ⅱ)自己株式又は自己新株予約権の取得、(ⅲ)株式、新株予約権又は社債(新株予約権付社債を含む。)の発行又は自己株式の処分、(ⅳ)株式の分割もしくは併合、又は株式もしくは新株予約権の無償割当て、(ⅴ)役員報酬等の総額の決定又は変更、(ⅵ)合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、事業の全部又は重要な一部の譲渡又は譲受その他これらに準じる行為(対象者において適時開示を要しないものを除く。)、(ⅶ)資本金もしくは準備金の額の減少、会社法第450条第1項に定める資本金の額の増加、会社法第451条第1項に定める準備金の額の増加又は会社法第452条に定める剰余金の処分、(ⅷ)剰余金の配当、(ⅸ)これらのほか、通常の業務の範囲外の行為であって、かつ、本取引の実施に重要な影響を与え、又は本取引の目的の達成を著しく困難とするおそれのあるものをいいます。
加えて、本取引契約においては、各当事者は、上記のほか、自らについての表明保証(注2)を行い、契約違反時の補償義務、秘密保持義務、本取引契約上の権利義務の譲渡禁止に係る義務、本取引契約に定めのない事項についての誠実協議義務を負担しております。
(注2) 本取引契約において、公開買付者は、(a)公開買付者の設立及び存続、(b)本取引契約の締結及び履行に係る権限の保有並びに法令及び定款その他の社内規則上必要な社内手続きの履践、(c)本取引契約の締結の有効性及び強制執行可能性、(d)本取引契約の法令、定款その他社内規則又は政府機関の判断等(政府機関等の判決、決定、命令、裁判上の和解、許可、認可、免許、承認、勧告、指導、指示その他の判断を総称していいます。以下同じです。)への違反の不存在、(e)反社会的勢力ではないことをZホールディングスに対して、NAVERは、(a)NAVERの設立及び存続、(b)本取引契約の締結及び履行に係る権限の保有並びに法令及び定款その他の社内規則上必要な社内手続の履践、(c)本取引契約の締結の有効性及び強制執行可能性、(d)本取引契約の法令、定款その他社内規則又は政府機関の判断等への違反の不存在、(e)反社会的勢力ではないことをZホールディングスに対して、Zホールディングスは、(a)Zホールディングスの設立及び存続、(b)本取引契約の締結及び履行に係る権限の保有並びに法令及び定款その他の社内規則上必要な社内手続きの履践、(c)本取引契約の締結の有効性及び強制執行可能性、(d)本取引契約の法令、定款その他社内規則又は政府機関の判断等への違反の不存在、(e)反社会的勢力ではないこと、(f)ヤフーは対象者株式を2,443,600株所有しており、Zホールディングス及びその子会社は対象者株式、新株予約権、新株予約権付社債その他当該発行会社の株式を取得できる権利を保有していないことを公開買付者及びNAVERに対して、それぞれ表明し、保証しております。
(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者は、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより、本対象者株式及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、対象者に対して以下の一連の手続きの実行を要請し、対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとするための一連の手続きを実施することを予定しております。
具体的には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を対象者に要請する予定です。なお、公開買付者及びヤフーは本臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。また、公開買付者及びヤフーは、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの成立後速やかに、対象者に対して本臨時株主総会に関する基準日設定公告(本書提出日現在においては、基準日を2021年12月上旬とすることを予定しております。)を行うことを要請する予定です。
本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認いただいた場合には、対象者の株主は、本株式併合がその効力を生ずる日において、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することになります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続きに従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります(以下「本端数処理」といいます。)。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。
また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者及びヤフーのみが対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者、ヤフー及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定です。
また、本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、株式併合がなされた場合であって、株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、対象者の株主の皆様は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求できる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められております。上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者、ヤフー及び対象者を除きます。)が所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の株主は、上記申立てを行うことができることになる予定です。
上記手続きについては、関係法令についての改正、施行及び当局の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買付者及びヤフーの株券等所有割合及び公開買付者以外の対象者の株主の対象者株式の所有状況等によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。もっとも、本株式併合についての株式買取請求に関する価格の決定の申立てがなされた場合において、対象者株式の売買価格又は株式買取請求に関する価格は、最終的に裁判所が判断することになります。
以上の各場合における具体的な手続き及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
なお、公開買付者は、本公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されず残存した場合には、対象者に対して、本新株予約権の取得、本新株予約権者に対する本新株予約権の放棄の勧奨その他本取引の実行に合理的な手続きを実施することを要請し、又は実施する予定です。
加えて、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の賛同を勧誘するものではありません。本公開買付けへの応募又は上記の各手続きにおける税務上の取扱いについては、対象者の株主が自らの責任にて税務専門家にご確認ください。
また、公開買付者及び対象者は、本スクイーズアウトの完了後、法第24条第1項但書に基づき対象者の有価証券報告書提出義務の中断申請に対する承認が得られた後に、対象者との間で本三角株式交換に係る株式交換契約を締結し、公開買付者を株式交換完全親会社、対象者を株式交換完全子会社とし、WEBTOON Entertainment株式を対価とする三角株式交換を実施することを予定しております。
本三角株式交換においては、法定の必要手続きを踏むことにより本スクイーズアウトの完了後に存在する不応募株式はWEBTOON Entertainment株式と交換され、WEBTOON Entertainment株式の1株以上が割り当てられた対象者の株主(ヤフーを意味します。)は、公開買付者の親会社であるWEBTOON Entertainmentの株主となります。
公開買付者が本三角株式交換の対価として交付するWEBTOON Entertainment株式につき、その総数は、(A)本スクイーズアウトの効力発生の直前時に存在する不応募株式数に(B)市場価格を基準に定める対象者株式1株当たりの評価額を乗じた金額から(C)本スクイーズアウトにおける本端数処理の過程でヤフーに対して交付される金銭の金額を控除し、上記で算出された金額を(D)WEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額で除して算出することを予定しております。この対価として交付する株式数の算定に際しては、本三角株式交換が本公開買付けにおける対象者の少数株主に比して有利なものとならないよう、また、その妥当性を確保するため、公開買付者は、(B)市場価格を基準に定める対象者株式1株当たりの評価額については、3,529円(本公開買付価格の最終提案日である2021年9月24日までの過去1ヵ月間(2021年8月25日から2021年9月24日まで)における対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値単純平均値に対して公開買付者ら及びZホールディングス間で協議して定めた一定のディスカウントを行った価格)とすることで本公開買付け価格において公開買付者が市場価格に対して反映するプレミアムを考慮せず、また、(D)WEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額については、WEBTOON EntertainmentがNAVER及びZホールディングスグループの合弁会社であることに鑑み、本取引の各段階におけるWEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額次第で、NAVER及びZホールディングスグループの間で利益移転が生じることがないよう、本取引を通じてNAVER及びZホールディングスグループがWEBTOON Entertainment株式を出資比率に応じて同一額で取得することが必要であるとの考えから、本出資においてNAVERからその子会社であるWEBTOON Entertainmentへの払込みを行う際の1株当たりの払込金額と同額を使用する予定です。
なお、公開買付者による本三角株式交換の効力発生後、本三角株式交換の対価としてヤフーに交付されたWEBTOON Entertainment株式は、現物配当その他の方法により、ヤフーからZホールディングスへと移転される予定です。
また、公開買付者らは、公開買付者による本三角株式交換の効力発生後、WEBTOON Entertainmentの株主である(ⅰ)NAVER及び(ⅱ)Zホールディングスグループ間のWEBTOON Entertainmentへの出資比率が本公開買付け公表日における(ⅰ)NAVER及び(ⅱ)Zホールディングスグループ間の出資比率である(ⅰ):(ⅱ)=66.6%:33.4%と等しくなるように調整し、もって本取引を通じたNAVER及びZホールディングスグループによるWEBTOON Entertainment株式の取得が出資比率に応じた比例的なものとなることを確保するため、NAVERは、WEBTOON Entertainmentに対する追加出資を実施する予定です(本追加出資)。NAVERによる追加出資の金額は、(A)本三角株式交換の対価として交付されたWEBTOON Entertainment株式数に66.6/33.4(=1.994)を乗じたものから、(B)本出資によりNAVERが取得したWEBTOON Entertainment株式数を減じ、当該計算により算出された株式数に(C)WEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額を乗じたものとなる予定です。当該(C)WEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額についても、本取引の各段階におけるWEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額次第で、NAVER及びZホールディングスグループの間で利益移転が生じることがないよう、本取引を通じてNAVER及びZホールディングスグループがWEBTOON Entertainment株式を出資比率に応じて同一額で取得することが必要であるとの考えから、本出資においてNAVERからその子会社であるWEBTOON Entertainmentへの払込みを行う際の1株当たりの払込金額と同額を使用する予定です。
(6) 上場廃止となる見込み及びその事由
対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従って、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。
また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後、上記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、公開買付者は、本スクイーズアウトを実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできません。
公開買付者は、2021年9月30日開催の公開買付者の取締役会において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に上場している対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を非公開化することを前提として行われる一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、対象者株式の全て(本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、ヤフー株式会社(以下「ヤフー」といいます。なお、本書提出日現在、ヤフーは、Zホールディングス株式会社(以下「Zホールディングス」といいます。)の完全子会社です。)が本書提出日現在所有する対象者株式(所有株式数2,443,600株、所有割合(注1):43.18%)(以下「本不応募株式」といいます。)及び対象者が所有する自己株式を除きます。以下「本対象者株式」といいます。)及び本新株予約権の全てを対象にした公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施することを決議いたしました。なお、本書提出日現在、公開買付者は、対象者株式を所有しておりません。
(注1) 「所有割合」とは、対象者が2021年7月30日に公表した「2022年3月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)」(以下「対象者第1四半期決算短信」といいます。)に記載された2021年6月30日現在の発行済株式総数(5,712,700株)に、(ⅰ)同日以降本書提出日までに行使された新株予約権(対象者によれば第10回新株予約権(7個)及び第12回新株予約権(10個))の目的となる対象者株式数(2,400株)及び(ⅱ)同日現在現存し、本書提出日現在行使可能な第10回新株予約権(30個)、第11回新株予約権(8個)、第12回新株予約権(60個)、第13回新株予約権(62個)及び第16回新株予約権(42個)の目的となる対象者株式数(24,000株)を加えた数から、対象者第1四半期決算短信に記載された2021年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(80,518株)を控除した株式数(5,658,582株)(以下「潜在株式勘案後対象者株式総数」といいます。)に対する対象者株式の割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。
本取引は、以下の各取引から構成されます。
① 本公開買付け
② 本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの公開買付期間(以下「公開買付期間」といいます。)の末日以後、本公開買付けの決済の開始日前に実施される、NAVER Corporation(以下「NAVER」といいます。)からその子会社であるWEBTOON Entertainment Inc.(以下「WEBTOON Entertainment」といい、公開買付者、NAVER及びWEBTOON Entertainmentを総称して「公開買付者ら」といいます。)(注2)への払込総額16,049,000千円を限度とする出資、WEBTOON Entertainmentからその完全子会社であるNAVER WEBTOON Limited(以下「NAVER WEBTOON」といいます。)への払込総額4,814,700千円を限度とする出資、WEBTOON Entertainmentからその子会社である公開買付者への払込総額11,234,300千円を限度とする出資、及びNAVER WEBTOONから公開買付者への払込総額4,814,700千円を限度とする出資(これら一連の出資を総称して、以下「本出資」といいます。)
(注2) WEBTOON Entertainmentは、本公開買付け公表日において、(ⅰ)NAVER及び(ⅱ)Zホールディングスの完全子会社であるLINE株式会社(以下「LINE」といいます。)が(ⅰ):(ⅱ)=66.6%:33.4%の比率で出資を行う、NAVERとZホールディングスの合弁会社です。
③ 本公開買付けが成立し、本対象者株式及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合に、対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすることを目的として対象者が実施する対象者株式の株式併合(以下「本株式併合」といい、本公開買付けと併せて「本非公開化取引」といいます。)
④ 下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の、対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとするための一連の手続き(以下「本スクイーズアウト」といいます。)の完了を条件として実施される、対象者の株主を公開買付者のみとするための、公開買付者を株式交換完全親会社、対象者を株式交換完全子会社とし、WEBTOON Entertainment株式を対価とする三角株式交換(以下「本三角株式交換」といいます。)
⑤ 下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の、本三角株式交換の効力発生を条件として行われる、本三角株式交換の対価としてヤフーに交付されたWEBTOON Entertainment株式の、ヤフーからその完全親会社であるZホールディングスへの現物配当その他の方法による移転(以下「本グループ内移転」といいます。)
⑥ 下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の、WEBTOON Entertainmentの株主である(ⅰ)NAVER、並びに、(ⅱ)LINE及びその完全親会社であるZホールディングス(Zホールディングス並びにその子会社であるヤフー及びLINEを合わせて、以下「Zホールディングスグループ」といいます。)間のWEBTOON Entertainmentへの出資比率を、本公開買付け公表日における出資比率((ⅰ):(ⅱ)=66.6%:33.4%)と等しくなるように調整し、もって本取引を通じたNAVER及びZホールディングスグループによるWEBTOON Entertainment株式の取得が出資比率に応じた比例的なものとなることを確保するために行われる、NAVERからWEBTOON Entertainmentに対する追加出資(以下「本追加出資」といいます。)
本公開買付けに際し、公開買付者は、2021年9月30日付で、NAVER及びZホールディングスとの間で、①本不応募株式について、本公開買付けに応募させないこと、②本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの公開買付期間末日以後、決済の開始日前にNAVERがWEBTOON Entertainmentを通じて公開買付者に対して本出資を行うこと、③本公開買付けの成立後に、本株式併合により対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすること、④本スクイーズアウトの完了後に、本三角株式交換を実行すること等を含めた、本取引に係る諸条件を内容とする取引契約(以下「本取引契約」といいます。)を締結しております。なお、本取引契約の締結にあたっては、Zホールディングスがヤフー及びLINEの完全親会社であり、意思決定を実質的に支配していると考えられることから、Zホールディングスのみを契約当事者としております。本取引契約の詳細については、下記「(4)本公開買付けに関する重要な合意」をご参照ください。
本公開買付けにおいては、公開買付者は、対象者株式を非公開化することを目的としておりますところ、下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の本株式併合の手続きを実施する際には、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることから、本取引を着実に遂行すべく、本公開買付け後に公開買付者及びヤフーが対象者の議決権数の3分の2以上を所有することとなるようにするため、1,328,800株(注3)(所有割合:23.48%)を買付予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(1,328,800株)に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行いません。
(注3) 買付予定数の下限(1,328,800株)は、潜在株式勘案後対象者株式総数(5,658,582株)に係る議決権数(56,585個)の3分の2以上となる議決権数(37,724個)に対象者株式1単元(100株)を乗じた株式数(3,772,400株)から、本不応募株式(2,443,600株)を控除した株式数です。
一方、上記のとおり、本公開買付けにおいて、公開買付者は本対象者株式の全てを取得して、対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすることを企図していることから、買付予定数の上限を設定しておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(1,328,800株)以上の場合は、応募株券等の全ての買付け等を行います。
公開買付者は、下記「8 買付け等に要する資金」の「(2) 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等」の「④その他資金調達方法」に記載のとおり、本公開買付けに係る決済に要する資金を、本出資により賄うことを予定しております。また、公開買付者は、「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、本公開買付けにおいて、本対象者株式及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、対象者に対し、本取引の一環として本株式併合の実施を要請する予定ですが、本株式併合により生じる端数の合計額に相当する対象者株式の取得にかかる資金についても、本出資により賄うことを予定しております。
なお、本取引を図で表示すると大要以下のとおりです。
Ⅰ.本公開買付けの実施前
本書提出日現在において、ヤフーが2,443,600株(所有割合:43.18%)、少数株主が残りの3,214,982株(所有割合:56.82%)を所有。
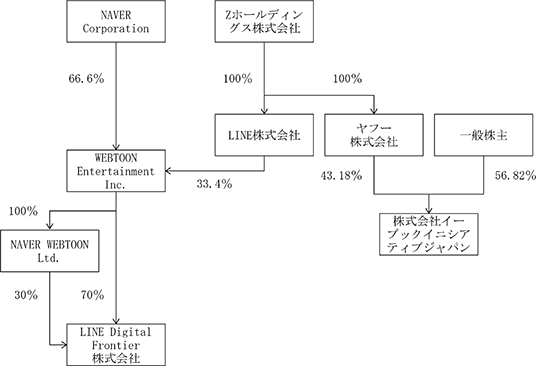
Ⅱ.本公開買付け(2021年10月1日~2021年11月15日(予定))
公開買付者は、本対象者株式及び本新株予約権の全てを対象に本公開買付けを実施(対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)は4,750円、本新株予約権1個当たりの買付け等の価格(以下「本新株予約権買付価格」といいます。)は本公開買付価格と各本新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者株式数の個数を乗じた金額。)。
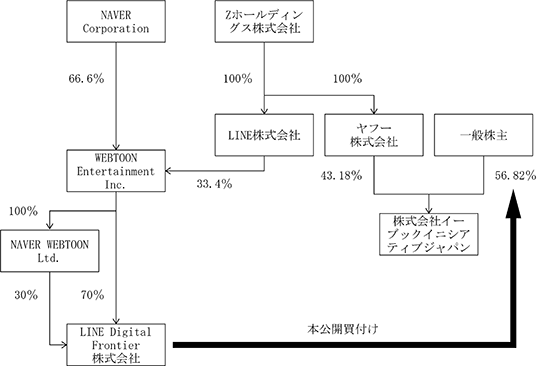
Ⅲ.本公開買付けの成立後
① 本出資(2021年11月中旬~下旬(予定))
公開買付期間末日以後、本公開買付けの決済の開始日前に実施される、NAVERからその子会社であるWEBTOON Entertainmentへの払込総額16,049,000千円を限度とする出資、WEBTOON Entertainmentからその完全子会社であるNAVER WEBTOONへの払込総額4,814,700千円を限度とする出資、WEBTOON Entertainmentからその子会社である公開買付者への払込総額11,234,300千円を限度とする出資、及びNAVER WEBTOONから公開買付者への払込総額4,814,700千円を限度とする出資。
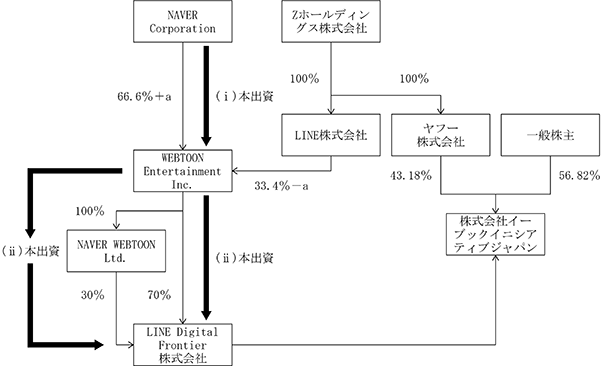
② 本株式併合(2022年1月頃(予定))
本公開買付けが成立し、本対象者株式及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合に対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすることを目的として対象者が実施する株式併合。
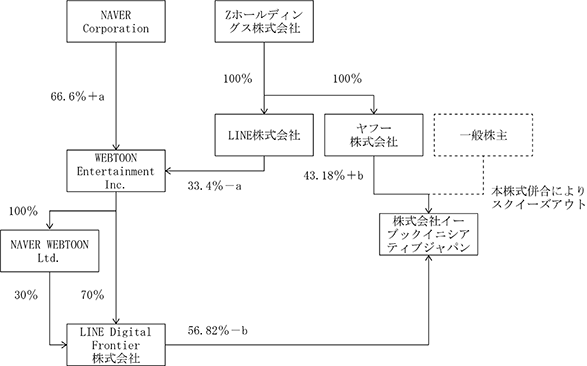
③ 本三角株式交換(2022年3月頃(予定))
本スクイーズアウトの完了を条件として実施される、公開買付者を株式交換完全親会社、対象者を株式交換完全子会社とし、WEBTOON Entertainment株式を対価とする三角株式交換。本三角株式交換は、本スクイーズアウトの完了後に、ヤフーが所有する対象者株式(1株未満の端数を除く。)を公開買付者が取得し、対象者の株主を公開買付者のみとすることを目的として実施されるものであり、本三角株式交換によって、対象者の株主は公開買付者のみとなります。本三角株式交換における対価の決定方法については、下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。
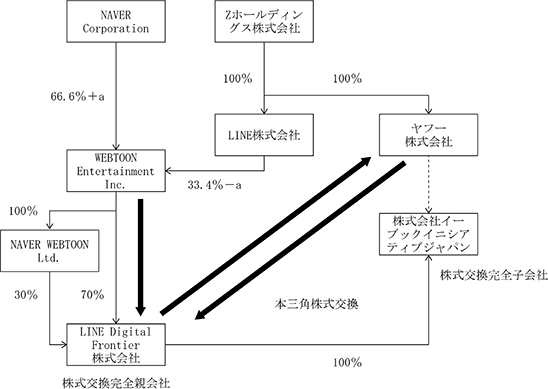
(本三角株式交換実行後)
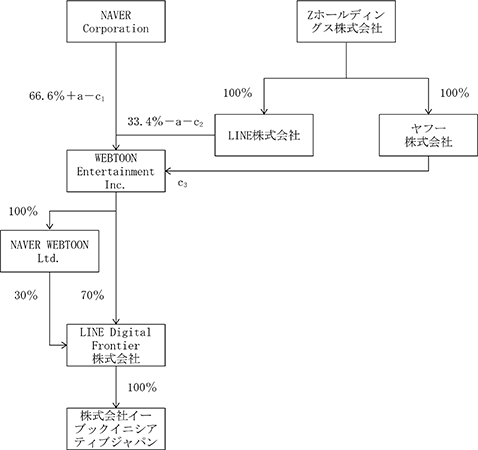
④ 本グループ内移転(2022年3月頃(予定))
本三角株式交換の効力発生を条件として行われる、本三角株式交換の対価としてヤフーに交付されたWEBTOON Entertainment株式の、ヤフーからその完全親会社であるZホールディングスへの現物配当その他の方法による移転。
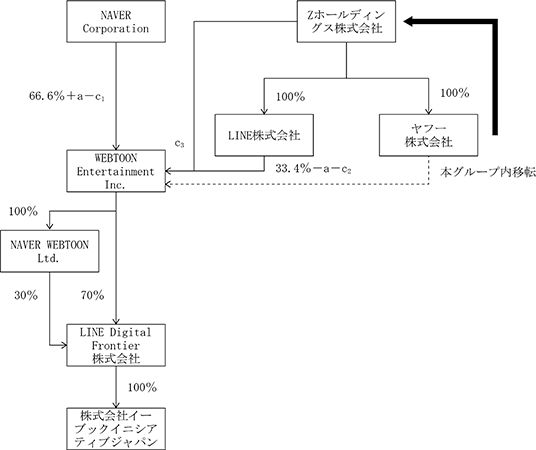
⑤ 本追加出資(2022年3月頃(予定))
本三角株式交換の効力発生を条件として行われる、WEBTOON Entertainmentの株主である(ⅰ)NAVER及び(ⅱ)Zホールディングスグループ間のWEBTOON Entertainmentへの出資比率が本公開買付け公表日における出資比率((ⅰ):(ⅱ)=66.6%:33.4%)と等しくなるように調整し、もって本取引を通じたNAVER及びZホールディングスグループによるWEBTOON Entertainment株式の取得が出資比率に応じた比例的なものとなることを確保するために行われる、NAVERからWEBTOON Entertainmentへの追加出資。本追加出資における出資額の決定方法については、下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。

対象者が2021年9月30日に公表した「LINE Digital Frontier株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けに関し、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
かかる対象者取締役会の決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2) 本公開買付けを実施するに至った背景、目的並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの目的及び背景
公開買付者は2018年に設立以来、LINEの子会社として日本国内において電子コミック事業を運営しておりましたが、2020年8月、同事業を日本だけではなく米国・韓国を中心にグローバルに展開し、米国法人であるWEBTOON Entertainmentが所有していた電子コミックのノウハウや人材を得ることによるオリジナル作品の強化及びデジタル作家の発掘育成の強化を目指し、WEBTOON Entertainmentに対してLINEの所有していた株式が譲渡されたことにより、公開買付者はWEBTOON Entertainmentの子会社となりました。現在は、WEBTOON Entertainmentが自ら及びその完全子会社であるNAVER WEBTOONを通じて、公開買付者の発行済株式の全てを所有しております。
WEBTOON Entertainmentは韓国最大のインターネット企業であるNAVERが66.6%、LINEが33.4%の持株比率にて株式を所有しており、主にNAVER WEBTOON、WEBTOON、LINE WEBTOON、LINEマンガの電子コミック、WEBTOON(スマートフォンに最適化した縦読みのフルカラー電子コミックを指します。)サービスを世界100カ国以上の国々で提供しており、月間ユーザー数7千万人以上を有する電子書籍事業者です。WEBTOON Entertainmentグループ(WEBTOON Entertainment及びNAVER WEBTOON、 公開買付者、StudioN、LICO等により構成される企業集団をいいます。以下同じです。)は「世界中のクリエイターと読者をつなぐ最も革新的で便利なプラットフォームを作ろう。」という経営理念の下、WEBTOONを中心に電子ノベルや映像制作及び流通等も手がける総合エンターテインメントカンパニーです。
このようなWEBTOON Entertainmentグループの中で、公開買付者は、2013年4月にLINEからリリースされ、現在は公開買付者が運営する「LINEマンガ」アプリを通じて、電子書籍の配信事業と投稿プラットフォーム事業(注1)を営んでおります。その上で、公開買付者は、2020年度から「マンガの未来を創る」というビジョンを掲げ、「作品との出会い」「新しい価値の提供」「最良の作品発表の場所と環境」をミッションとし、これを達成することを通じて日本のマンガ文化を発展させ、世界へと広げていくことを目指し事業に取り組んでおります。公開買付者はこのミッションを達成していくため、まずはサービス提供を通じた利用者基盤の拡大を成長戦略の一つとして位置付けております。
(注1) 投稿プラットフォーム事業とは、アマチュア作家に対し作品を投稿すること及び投稿した作品を配信することを可能にする環境を提供するサービスを意味します。
また、対象者プレスリリースによれば、対象者は、2000年より、コミックを中心に小説、雑誌、ビジネス書等の幅広い品揃えを有する電子書店「eBookJapan」を運営し、拡大が続く電子書籍市場のパイオニアとして、積極的に事業拡大に取り組んできたとのことです。対象者の設立は、対象者の創業者が出版社に勤務していた時代に、返本された書籍の山が断裁・焼却されることによる地球環境への影響を危惧したことがそのきっかけとなっており、対象者は、「SAVE TREES!」を事業コンセプトに打ち立て、電子書籍の普及による地球環境保護を目指しているとのことです。現に、対象者は、これまで累計1億冊以上の電子書籍を販売してきましたが、これら全てを紙媒体の書籍として販売した場合には、原材料としておよそ50万本以上に相当する樹木が必要となるものと考えられることを踏まえると、対象者の事業は、上記の事業コンセプトに沿ったものになっているものと自負しているとのことです。
対象者は、2008年頃から、急速に普及が進んだスマートフォン及びタブレット端末向けの電子書籍の販売に注力することで成長を加速させ、2011年10月、東京証券取引所マザーズ市場にその株式を上場し、2013年10月には東京証券取引所市場第一部に上場したとのことです。また、対象者は、2015年5月には、オンライン書店「BOOKFAN」及び「boox」を運営する株式会社ブークスを完全子会社化(2016年5月に対象者を吸収合併存続会社、株式会社ブークスを吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施)し、紙書籍のオンライン販売も事業に加えているとのことです。
2016年6月9日には、対象者はヤフーと資本業務提携契約を締結し、ヤフーによる対象者株式に対する公開買付け並びにヤフーを割当先とする第三者割当による増資及び自己株式の処分を行いました。なお、ヤフーは、当該公開買付けに先立ち、対象者株式100株を取得しているとのことです。これにより、ヤフーは同年9月5日に、対象者株式2,443,600株(所有割合:43.18%。内訳としては、当該公開買付けにより、対象者株式2,315,700株(うち400,200株は自己株式の処分により当該公開買付けに応募)を取得し、当該第三者割当による増資により対象者株式127,800株を取得しております。)を取得するに至り、対象者はヤフー及びソフトバンクグループ株式会社の連結子会社となったとのことです。その後、対象者とヤフーが協力して運営する新たな電子書籍販売サービス「ebookjapan」を2018年10月より立ち上げ、当該サービスを移行先として、対象者がこれまで運営してきた電子書籍販売サービス「eBookJapan」よりユーザーの移行を促進した後、2019年6月には旧サービス「eBookJapan」における電子書籍販売を終了し、これにより、新サービス「ebookjapan」へのサービス統合を完了したとのことです。現在は、Zホールディングスグループとのシナジーの強化に注力し、電子書籍市場における対象者の利用者基盤を拡大することにより、電子コミック分野での国内取扱高No.1を目指して事業連携を進めているとのことです。
公開買付者らとしては、エンターテインメントサービスの源泉となる知的財産権が多く存在する日本の電子書籍市場での公開買付者の成長は、WEBTOON Entertainmentグループにとっても重要である一方で、マンガ大国といえる日本の電子書籍市場は、多数の競合他社が存在する極めて競争環境の厳しい市場であり、企業価値向上のためには有効な経営施策を断続的に打ち出す必要があると認識しておりました。
公開買付者らは、上述の戦略のもと、公開買付者の利用者基盤を強化し事業を拡大させる成長施策のひとつとして、電子書籍領域や関連する事業におけるM&Aについても常に検討しておりました。そのような状況の中、公開買付者らは、2019年11月中旬のLINEとZホールディングスの経営統合の決定を機に、グループ会社となる対象者との間で電子書籍の領域においてシナジーを生み出す可能性に関する検討を開始いたしました。そして、2020年10月上旬より、公開買付者と同じ電子書籍事業を営む対象者との間で、シナジーの創出に向けた初期的な協議を開始し、アプリを通じたコンテンツ配信に強みを持つ公開買付者とWEBを通じたコンテンツ配信に強みを持つ対象者が相互補完的に互いのプラットフォームを活用しつつ、より効率的に潜在的な顧客を獲得すると同時に、日本における優良マンガコンテンツの配信を行う対象者がコンテンツ配信を海外で展開する公開買付者らのグループに加入することで日本の優良マンガコンテンツのグローバルでの存在感の向上が可能であり、より広範な顧客層を対象として対象者のコンテンツ配信が可能になることを確認いたしました。また、特に対象者の持つバックエンド業務(注2)の仕組みを公開買付者と共通化することで、これまで以上に安定的なサービスインフラを構築し、利用者に対し、電子書籍をはじめとするコンテンツの提供スピードと安定性を兼ね備えたサービスの提供に資する可能性があるとの認識を持つに至りました。さらに、上記のような対象者及び公開買付者の間の協業の可能性に加え、公開買付者らは、①「ebookjapan」及び「LINEマンガ」の異なる2つの利用者層並びに②「ebookjapan」がマーケティングや送客、決済システム等で提携する「Yahoo!JAPAN」及び「LINEマンガ」がマーケティングや人材面等で連携する「LINE」という異なる2つのプラットフォームをより有機的に機能させるためには、バックエンドの仕組みの共通化のみならず、公開買付者が対象者を子会社化し、両サービスを共通の目的を持って事業を推進してこそ最大のシナジーを生み出すことができるとの考えを持つに至りました。そして、LINEとZホールディングスの経営統合が完了したことを受け、2021年3月上旬に、対象者の親会社であるヤフー及びZホールディングスに対して公開買付者による対象者の子会社化を行う旨の初期的な打診をいたしました。
(注2) 電子書籍事業におけるバックエンド業務とは、サービス開発業務のうち、出版社等の著作権保有者から許諾を受けた紙媒体のマンガ・書籍をデジタライズ化する作業を担う業務をいいます。他方で、バックエンド業務と対比する用語として「フロントエンド業務」があり、ユーザーへのコンテンツの提供その他サービス提供全般を意味します。
そして、2021年3月上旬に、公開買付者らは、当該打診の結果、ヤフー及びZホールディングスが、当該子会社化の協議に応じる可能性があるとの感触を得ましたが、同時に、対象者とバックエンド業務に関する業務提携については対象者の子会社化に関する協議の結果にかかわらず公開買付者の事業を推進しシナジーを生み出せる取り組みであることから当該対象者の子会社化の協議とは別途、併行して対象者との間で資本関係を伴わない業務提携の可能性についての協議を進め、対象者が2021年6月1日付で公表した「LINE Digital Frontier 株式会社との業務提携に関するお知らせ」に記載のとおり、公開買付者と対象者との間の業務提携契約を締結(以下「本業務提携」といいます。)するに至りました。
本業務提携は、対象者が「LINEマンガ」のバックエンド業務の一部を受託し、同業務の効率化を進めることで、事業効率の改善及びコンテンツ力の向上を企図したものでした。一方で、公開買付者らは、本業務提携のみでは公開買付者と対象者はあくまで同様の事業を営む競争関係に留まり、また、競争法の観点から全ての事業領域での連携を行えないとの認識のもと、2021年5月31日に、NAVERから、対象者に対して、NAVERの子会社である公開買付者による対象者の非公開化に関する取引を行うことについての初期的な打診を行ったほか、2021年6月1日の公開買付者と対象者との間の本業務提携の後も、公開買付者による対象者の子会社化を実施するべく、検討を続けてまいりました。そして、今後の成長戦略及び企業価値向上策を改めて精査・検討した結果、資本関係のない独立当事者間における事業提携では中長期的な成長を実現する上で限界があることを再認識いたしました。また、上記のような厳しい市場環境において、スピード感をもって両社の成長戦略及び企業価値向上策を一体的に実現していくためには、公開買付者が対象者を子会社化することにより、公開買付者と対象者が資本関係を共通にして、競争関係から脱却し、バックエンド業務に限らない分野も含めてより密接に連携することが不可欠であるとの考えを深化させました。
より具体的には、2021年6月1日に公表した本業務提携以降においても、①「ebookjapan」及び「LINEマンガ」の異なる2つの利用者層並びに②「ebookjapan」がマーケティングや送客、決済システム等で提携する「Yahoo!JAPAN」及び「LINEマンガ」がマーケティングや人材面等で連携する「LINE」という異なる2つのプラットフォームをより有機的に機能させることによって初めて実現するシナジーの獲得の方法として公開買付者による対象者の子会社化について継続的に検討を行っておりました。
その結果、公開買付者らは、公開買付者が対象者を子会社化することにより可能となるWEBTOON Entertainmentグループの経営資源や上記の各事業において培ったノウハウの活用により、オリジナル・コンテンツの拡大を含めた対象者の事業のさらなる発展を支援することができると考えるに至りました。また、公開買付者が対象者と資本関係を共通にし、迅速な意思決定を行う体制の確保や事業提携関係のみでは競争法の規制上実現できない営業情報の共有を通じて、公開買付者をはじめとするWEBTOON Entertainmentグループが運営する「LINEマンガ」サービスと対象者の運営する「ebookjapan」サービスの協業をより一層加速させることで、日本国内においてスケールメリットを活かしたより強固かつ広範な電子書籍プラットフォームを構築することが可能となると考えるに至りました。具体的には、公開買付者と対象者が持つサービス開発力を融合することにより、バックエンドの統合からユーザーへのコンテンツ配信に至るまで、より安定的で迅速なサービス展開が可能になり、また、公開買付者が持つアプリベースの市場戦略と対象者が持つWEBブラウザベースの市場戦略により、潜在的顧客がスマートフォンを使用するユーザーとWEBブラウザを使用するユーザーの双方をカバーすることになるものと考えております。また、公開買付者らは、これらの取り組みを通じて、両社の中長期的な企業価値の向上と日本の電子書籍サービスの利用者の総合的なユーザー体験の向上にも繋がるとも考えるに至りました。
このような検討を経て、公開買付者らは、公開買付者と対象者の市場における競争力強化及び両社の企業価値の向上を図る観点から、2021年6月18日付で対象者に対し公開買付者による対象者株式の公開買付け及びそれに引き続くスクイーズアウト手続きを通じて対象者の全株式を取得する旨の初期的な意向表明書を提出いたしました。
その後、公開買付者らは、2021年6月下旬から、対象者の事業・財務・税務・法務等に関するデュー・ディリジェンス(2021年8月中旬に終了しております。)や対象者の経営陣との面談等を実施いたしました。公開買付者らはその過程で取得した情報等を踏まえて、本取引の意義、買収ストラクチャー、本取引の実現可能性等について、さらなる分析及び検討を進めるとともに、対象者との間で本公開買付価格を含む本取引の諸条件について引き続き協議を行っておりました。その結果、2021年7月下旬に、公開買付者らは、対象者、対象者の親会社でありプラットフォームの提供を通じて対象者の事業運営上重要な役割を果たすヤフー、及び公開買付者の三者が保有する経営資源を対象者において共同活用し、互恵的にシナジーを享受するためには、公開買付者とヤフーを対象者の唯一の株主とし、さらにそれに引き続き公開買付者を対象者の唯一の株主とするための取引を実施することで、公開買付者と対象者が資本関係を共通にして両社が競争関係から脱却し、バックエンド業務に限らない分野も含めてより密接に連携することが不可欠であると認識するに至りました。具体的には、公開買付者らは対象者を公開買付者の完全子会社とすることにより、両社の特性を活かし、以下のようなシナジーの実現を目指してまいります。
(ⅰ) 公開買付者及び対象者の利用者の拡大
公開買付者は主にiOS、Androidアプリで多くの利用者を獲得しているのに対し、対象者はWEBブラウザで多くの利用者を獲得しており、利用者層においても若年層と高年層とそれぞれ異なる強みを持っております。また、公開買付者と対象者は、アプリとWEBブラウザ双方に強みを持つ電子書籍事業者として、両社の得意とする領域は相互に補完し合う関係にあるため利用者の拡大効果は高いと考えております。また、ユーザーの拡大は多様なユーザーのサービス利用データを蓄積することにも繋がります。電子書籍市場において、過去の購入作品等のサービス利用データの活用は事業運営やマーケティングのみならず、コンテンツ制作においても重要な役割を担う要素であり、より大きなシナジーを互恵的に生み出せるものと考えております。そのため、公開買付者と対象者が両社のデータをユーザーが許諾する範囲内において相互に活用することを今後検討していく予定です。
(ⅱ) 人気IP(注3)の創出と獲得
近年、電子書籍配信事業を運営するプラットフォーム事業者にとっては、自社のオリジナル作品及び独占・先行配信作品といった競合他社との差別化を図れるコンテンツの重要性が増しております。この点、公開買付者と対象者は、利用者層の違いに代表されるような異なる強みを持つプラットフォームを保有していることから、特性の異なる両プラットフォームを通じてコンテンツを配信することで、公開買付者及び対象者が独占的・先行的に配信を行うコンテンツのヒットの可能性を大きく広げることが可能になると考えております。また、コンテンツ制作において利用者を正確に把握することは、新たなヒットコンテンツを生み出すための重要なファクターとなります。そのため、両社が有するユーザーの過去の購入作品等のサービス利用データはコンテンツ制作やコンテンツマーケティングにおいても重要な要素となります。両社が今後検討していく予定のデータの相互利用を活用することでより効率的なコンテンツマーケティングや確度の高いコンテンツ制作が可能になると考えております。このことは、既存の人気IPの権利を保有する出版社その他のライセンサーとのパートナーシップにも有利に働くと考えております。
(注3) IPとは、Intellectual Propertyの略称であり、主にゲームやマンガ、アニメを題材とする知的財産コンテンツを意味します。
(ⅲ) マーケティング戦略の統一と効率化
対象者が得意とするWEBべースのマーケティング施策と公開買付者が得意とするアプリベースのマーケティング施策を最大限に活用し、マルチチャネルに対し強固で統一されたブランドマーケティングを繰り広げることができると考えております。現在の日本のデジタルマンガ市場においては、有償無償を問わずユーザーがアプリ又はWEB上でマンガを閲覧できる数多くの類似サービスが競合しており、各社がマーケティングを行うことから、より精巧に潜在顧客を絞り込んだマーケティングを展開する必要性が高まっております。両社が有するユーザーのデータベースをユーザーが許諾する範囲内において活用し、ユーザーにさらに適したコンテンツを推薦し、各媒体に合ったクリエイティブ広告を運用することでこの効率性をさらに高めることができると考えております。
(ⅳ) サービス開発、インフラ基盤の安定と強化
公開買付者と対象者の持つサービス開発力を合わせることで、効率的なサービス開発を行うことが可能になると考えております。電子書籍市場では、ユーザーがコンテンツに対して購入の都度料金を支払ってコンテンツを閲覧するモデルや、ユーザーがサービス提供者と低額課金契約を締結し対象範囲の電子書籍を制限なく読めるようになるモデル、さらにユーザーが一定期間待機すると一定量のコンテンツを無料で閲覧できるようになるモデル等、多様なビジネスモデルやサービスが生み出されており、後発のサービスであってもトレンドを生み出す可能性のある市場だと考えております。プロダクトの企画開発力や開発スピードはこうした競合他社との激しい競争環境において、いち早く新たなトレンドを生み出すための原動力になると考えております。また、本業務提携によるバックエンド業務の統合に限らず、コンテンツの獲得からユーザーへの配信に至るまで、より広い業務領域における包括的な統合を強固な形で実現していくために子会社化することで、より安定的でスピーディーなサービス展開が可能になると考えております。
そして、公開買付者ら、ヤフー及びZホールディングスは、公開買付者らによる対象者の子会社化を実現する方法として、公開買付者らが6月下旬から8月中旬にかけて対象者の事業・財務・税務・法務等に関するデュー・ディリジェンスを行うのに併行して、専門家も交えて、ヤフーがその所有する対象者株式を公開買付けに応募するスキーム、及び対象者の少数株主が所有する対象者株式の取得を目的とした公開買付けを実施し、ヤフーが所有する対象者株式を本公開買付価格より低い価格でグループ間取引もしくは現物出資・配当等を通じて公開買付者に所有させるスキームを含む様々なスキームの選択肢について議論を行いました。もっとも、対象者の現在の親会社であるヤフーが、対象者が運営する「ebookjapan」のためにプラットフォームを提供することにより対象者の事業運営上重要な役割を果たしていることを踏まえて、公開買付者らは、公開買付者らが想定する上記(ⅰ)から(ⅳ)のシナジーを実現するためには、ヤフーの提供するプラットフォームを含めた形で、Zホールディングスグループの出資比率を維持しながら、NAVERとZホールディングスグループ間の合弁会社であるWEBTOON Entertainmentの傘下に対象者を追加することができるスキームが最善であるとの判断に至りました。そこで、公開買付者らは、ヤフーがその所有する対象者株式を本公開買付けに応募せず、本公開買付け後にWEBTOON Entertainment株式を対価として三角株式交換を行わせる方法により、当該株式を対価としてWEBTOON Entertainmentに現物出資する等の方法により、WEBTOON Entertainmentに対するNAVER及びZホールディングスグループ間の出資比率を維持するスキームを採用することを決定いたしました。また、当該検討において、WEBTOON Entertainmentへの出資を間接的に継続し、本取引の実行により対象者に生まれるシナジーの一部を享受することができるZホールディングスグループと、本取引により対象者の株主ではなくなる一般株主の皆様との間で同一の価格で対象者株式を評価することは一般株主の皆様に不利益をもたらすとの考えから、本対象者株式及び本不応募株式を異なる価格で評価することが適切であると考えるに至りました。そして、2021年8月上旬に、公開買付者らは、本三角株式交換後の本取引のスキームについては対象者の完全親会社であるZホールディングスとの間で継続協議することを前提として、対象者が所有する自己株式及び本不応募株式を除く対象者株式の全てについて、①本公開買付け及びその後の②本株式併合を通じて取得し、③本不応募株式については、本株式併合の効力発生後に公開買付者を株式交換完全親会社、対象者を株式交換完全子会社とし、WEBTOON Entertainment株式を対価とする三角株式交換を実施して取得する段階的買収スキームを対象者に提案することを決定いたしました。そして、2021年8月10日に、公開買付者らは、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者からの独立性を有し、ヤフーとの間に利害関係を有しない対象者の独立社外役員によって構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)に対して、対象者株式については、2021年8月10日の過去1ヵ月間(2021年7月12日から2021年8月10日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である3,525円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値について同じです。)に対して13.48%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアム率の計算において同じです。)のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年5月11日から2021年8月10日まで)の終値単純平均値3,184円に対して25.63%、過去6ヵ月間(2021年2月12日から2021年8月10日まで)の終値単純平均値2,910円に対して37.46%のプレミアムをそれぞれ付した水準となる4,000円を本公開買付価格とする内容を含む提案を行いました。なお、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、同提案の中で本公開買付価格としていた4,000円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値単純平均値である2,589円に対して54.50%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して51.23%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して52.56%のプレミアムであることを考慮したものです。上記の公開買付価格提案において、公開買付者らは、対象者に対するデュー・ディリジェンス、対象者の財務状況及び対象者より2021年7月14日付で開示された事業計画を分析の上、過去における上場会社を完全子会社とすることを企図した類似取引におけるプレミアム水準、本公開買付けへの応募見込み、等を総合的に勘案いたしました。また、この提案の中では、公開買付者らは、対象者が発行していた本新株予約権について、本新株予約権は対象者の役職員に対するストック・オプションとして付与されたもので、権利行使の時点において、対象者又は対象者の関係会社の役職員の地位にあることが権利行使の条件とされているため、公開買付者が本新株予約権を取得したとしてもこれらを行使することができないことから、その全てを1個につき1円で買い取ることを提案いたしました。これに対し、本取引の交渉において対象者の窓口機能を担っていた本特別委員会は、公開買付者らの提案した普通株式1株当たりの公開買付価格である4,000円は公正な価格に達しておらず、対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないことに加え、対象者が発行している新株予約権を1円で買い取ることは、新株予約権者である従業員にとってモチベーションの低下につながり本取引実施後の経営にも影響を与える可能性があるため、行使条件を考慮してもなお受け入れられないとして、2021年8月13日付で公開買付者らに対し提案内容の再考を求める連絡を行いました。以降、公開買付者らと対象者は、公開買付価格について継続的に協議・交渉を行いました。
そして、2021年9月3日に、公開買付者らは対象者に対して、対象者株式については、2021年9月3日の過去1ヵ月間(2021年8月4日から2021年9月3日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である3,736円に対して13.76%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年6月4日から2021年9月3日まで)の終値単純平均値3,479円に対して22.16%のプレミアム、過去6ヵ月間(2021年3月4日から2021年9月3日まで)の終値単純平均値3,077円に対して38.12%のプレミアムをそれぞれ付した水準となる4,250円を本公開買付価格とする内容を含む提案を再度行いました。なお、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、同提案の中で本公開買付価格としていた4,250円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である2,589円に対して64.16%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して60.68%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して62.09%のプレミアムであることを考慮したものです。また、公開買付者らはこの提案の中で、行使条件が付されているために公開買付者が買付けを行った後には行使不能となる本新株予約権につき、それらを実質的に行使可能とすることで新株予約権者の経済的利益を担保するため、その全てを1個につき対象者株式の公開買付価格と種類ごとの行使価格の差額に目的株式数を乗じた金額を本新株予約権買付価格とすることを提案いたしました。このように、公開買付者らは、2021年9月3日に公開買付者が行った価格提案に際して、公開買付者らによる対象者に対する評価を十分に価格に織り込みつつ、対象者の少数株主並びに新株予約権者が経済的に不利益を被らないように配慮を行いました。しかし、本特別委員会は公開買付価格の再考を要請し公開買付者らと対象者の間で本公開買付価格についての合意には至りませんでした。このように、対象者からは2021年9月3日に行った提案に対しての回答が得られなかったため、公開買付者らは、本特別委員会からの再考の要請を受けて、本公開買付価格についての合意を取得するべく、2021年9月上旬から中旬にかけて、本取引実施後に実現されるであろう公開買付者と対象者のより強固な業務上の協力関係の帰結について再度検討を行い、過去2回の提案における価格提示を再度見直しました。そして、2021年9月24日に、公開買付者らは対象者に対して、本新株予約権買付価格については2021年9月3日に公開買付者が前提とした全ての本新株予約権1個につき対象者株式の公開買付価格と種類ごとの行使価格の差額に目的株式数を乗じた価格とするという価格試算の考え方を変更しない一方で、対象者株式1株当たり4,750円を本公開買付価格とする内容を含む最終提案を行いました。本提案における対象者株式1株当たり4,750円は、2021年9月24日の過去1ヵ月間(2021年8月25日から2021年9月24日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である3,872円に対して22.68%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年6月25日から2021年9月24日まで)の終値単純平均値3,653円に対して30.03%のプレミアム、過去6ヵ月間(2021年3月25日から2021年9月24日まで)の終値単純平均値3,231円に対して47.01%のプレミアムをそれぞれ付した水準です。また、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、同提案の中で本公開買付価格としていた4,750円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である2,589円に対して83.47%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して79.58%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して81.16%のプレミアムを考慮したものです。
また、公開買付者らは、上記対象者との協議と併行して、Zホールディングスとの間で、本三角株式交換後の本取引のスキームについても協議し、NAVER及びZホールディングスグループ間のWEBTOON Entertainmentに対する出資比率を維持する観点から、2021年9月上旬、本取引のスキームとして、本三角株式交換の効力発生後に、本グループ内移転及び本追加出資を行うことを決定いたしました。なお、本グループ内移転及び本追加出資に関する協議においては、これらの取引の当事者とならない対象者はその協議に参加しておりません。
なお、対象者は、下記「② 対象者における意思決定の過程及び理由」に記載したとおり、対象者及び本特別委員会との間での協議を重ねた結果、対象者としても本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨するに至ったとのことです。
② 対象者における意思決定の過程及び理由
対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記「① 本公開買付けの目的及び背景」に記載のとおり、2021年3月上旬、公開買付者よりバックエンド業務を中心とした本業務提携の打診を受け、公開買付者との間で協議を進めておりましたが、その結果、2021年6月1日、公開買付者との間で、電子書籍事業における業務提携を行うことを決定するに至ったとのことです(本業務提携の詳細については、対象者が2021年6月1日付で公表した「LINE Digital Frontier株式会社との業務提携に関するお知らせ」をご参照ください。)。本業務提携においては、「LINEマンガ」のバックエンド業務の一部を対象者が受託し、同業務の共通化を進めることで、事業効率の改善及びコンテンツ力の向上を目的としているとのことです。他方、バックエンド業務の共通化以外の協業について、継続して協議を行うこととしていたとのことです。
このような状況下、対象者は、2021年5月31日、NAVERより、NAVERの子会社である公開買付者による対象者の非公開化に関する取引を行うことについての初期的な打診を受けたとのことです。その後、2021年6月上旬にNAVER から、当該取引について、別途正式に提案書を提出する意向を有している旨の連絡を受けたとのことです。当該初期的な打診においては、公開買付者が対象者の親会社であるヤフーの完全親会社であるZホールディングスと合意した上で、対象者の非公開化を実施する想定となっており、ヤフー及びZホールディングスと対象者の少数株主と利害が一致しない可能性があることを踏まえ、対象者は、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、2021年6月上旬、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。)を選任したとのことです。また、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、本特別委員会を2021年6月9日に設置したとのことです。さらに、2021年7月上旬、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)を、選任したとのことです。これらの措置の詳細については、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」をご参照ください。
上記体制の下で、対象者は、ファイナンシャル・アドバイザーとしての大和証券から財務的見地等に関する助言及び支援を受け、また、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から本公開買付けにおける意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けにおける意思決定にあたっての留意点についての法的助言を受け、本取引が対象者の企業価値の向上に資するものか、また、公開買付価格を含む本取引における諸条件は妥当なものであるか等の観点から慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
上記のとおり、対象者は、NAVERより、正式に提案書を提出する意向を有している旨の連絡を受けておりましたが、その後、2021年6月18日、NAVERから、その子会社である公開買付者を通じて、対象者株式の公開買付け及びそれに引き続くスクイーズアウト手続きを通じて対象者の全株式を取得する旨の初期的な意向表明書を受領したとのことです。その後、2021年6月下旬から、公開買付者らによる、対象者の事業・財務・税務・法務等に関するデュー・ディリジェンス(2021年8月中旬に終了しております。)が実施され、また、対象者経営陣と公開買付者らとの面談等が実施された後、対象者は、同年8月10日、公開買付者より、NAVERを通じて、公開買付価格を1株当たり4,000円とすることを含む提案書を受領したとのことです。これに対し、本特別委員会は、同日、大和証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から聴取した意見を踏まえて検討を行った上で、提案された公開買付価格は公正な価格に達しておらず、対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないとして、その付与された権限に基づき、直接の交渉主体として、NAVERに対し公開買付価格の再検討を要請したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、公開買付価格を1株当たり4,250円とする提案を受領したとのことです。当該提案を受け、対象者は、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである大和証券を通じて、公開買付者らとの間で協議を継続いたしましたが、本特別委員会は、当該大和証券を通じた協議の内容並びに大和証券からの財務的見地からの助言及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的見地からの助言を踏まえ、NAVERに対し、上記の提案価格は、大和証券によりディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)に基づき算定される株式価値の水準に照らし、引き続き対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないと考えていること等を理由として、再度公開買付価格の再考を依頼したとのことです。
その後も公開買付者との間で、対象者のファイナンシャル・アドバイザーを通じて、継続的に協議及び交渉を行い、その結果、本特別委員会は、2021年9月24日、公開買付者から、本公開買付価格を4,750円とすることを含む提案を受けるに至ったとのことです。
また、対象者及び本特別委員会は、公開買付者らとの間で、本新株予約権買付価格についても、協議・交渉を行っているとのことです。具体的には、対象者は、公開買付者らより、上記の2021年8月10日付の提案書において、本新株予約権買付価格について、新株予約権1個につき1円とする提案を受けたとのことです。これに対し、本特別委員会は、2021年8月13日、公開買付者らに対し、当該新株予約権は、対象者役職員に対する報酬制度として付与しているものであり、特に、当該新株予約権の内、現時点では行使不可であるものの、保有者に多大な経済的価値が見込まれる新株予約権を適切な価格で買い取らないとすると、保有者である対象者従業員のモチベーションが大きく低下し、非公開化後の経営統合プロセスに支障をきたす事が想定されることから、権利行使をした場合に利益が出る状態にある新株予約権については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とするように再考を依頼したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、新株予約権に係る買付価格については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とする旨の提案を受けるに至ったとのことです。
以上の検討・交渉過程において本特別委員会は、まず、大和証券による対象者株式の価値算定の基礎ともなる2022年3月期から2027年3月期までの事業計画(以下「本事業計画」といいます。)の内容、重要な前提条件及び作成経緯等の合理性について、対象者から説明を受け、確認及び承認しているとのことです。また、公開買付者から公開買付価格を含む本取引の条件についての提案を受領する都度、本特別委員会は、大和証券から受けた財務的見地からの助言を踏まえ、公開買付者からより高い価格を引き出すために、相互に独立した第三者間のM&Aで行われる一般的な交渉プロセスに即して十分な交渉を実施することを含む交渉方針について審議・検討した上で、公開買付者と直接書面のやり取りを行うこと等により、公開買付者との間で公開買付価格に関する協議・交渉を行っているとのことです。当該協議を踏まえた本特別委員会の答申の概要については、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「① 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。
その後、対象者は、2021年9月29日付で大和証券より株式価値算定書(以下「大和証券株式価値算定書」といいます。)を取得し、2021年9月30日、本特別委員会から、(a)対象者取締役会は、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨するべきであると考えられ、(b)対象者取締役会が、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を決定することは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられ、また、対象者取締役会が、本取引において予定されている方法によることを前提に、本公開買付け成立後の本株式併合による対象者の非公開化についての決定をすることは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられる旨の答申書(以下「本答申書」といいます。)の提出を受けているとのことです(なお、本答申書の概要については、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「① 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)。
その上で、対象者取締役会は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点についての法的助言、大和証券から受けた財務的見地からの助言及び大和証券株式価値算定書の内容を踏まえつつ、本特別委員会から取得した本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引により対象者の企業価値の向上を図ることができるか、公開買付価格を含む本取引における諸条件は妥当なものであるか等の観点から慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
上記の検討及び交渉の結果、対象者は、2021年9月30日、本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、引き続き対象者とヤフーとの間の資本関係を維持することにより対象者とヤフーとの間の協業関係を継続して発展させつつ、公開買付者との間の連携を強化し、協業を推進することにより、以下のシナジーを見込むことができ、対象者の収益基盤と事業競争力の強化が図られ、中長期的にも対象者の企業価値の向上に資するとの結論に至ったとのことです。
まず、対象者としては、競争の激しい国内電子書籍市場において、国内取扱高No.1という対象者の目標を達成するためには、(a)競合他社を上回る規模・効率での広告・販促活動や投資の継続、(b)対象者が競合他社と比較して補強が必要であると認識している領域(サービスに対する認知の向上、若年層利用者の取り込み、電子書籍アプリの強化、先行・独占・オリジナル等のコンテンツ強化等)への投資、(c)消費者ニーズの変化に対する迅速な対応(スマートフォンに特化した縦スクロールのカラーコンテンツの拡充、無料で読めるコンテンツの拡充等)及び(d)今後成長が見込まれるグローバル市場への積極的な展開といった各課題を解決していく必要があるものと認識しているとのことです。これらの各課題については、早期の解決を図っていくことが必要であるものの、他方、現状のヤフー及びZホールディングスとの間の提携関係のみでは、その実現に相応の期間が必要となるものと考えており、対象者としても、外部企業との間の資本提携を含むパートナーシップの構築の必要性について検討を行っていたとのことです。そのような状況下、上記のとおり、2021年6月1日、公開買付者との間で、本業務提携を開始いたしましたが、対象者としては、公開買付者との間には資本関係はなく独立した当事者間の協業であることや上場を維持することにより一般株主の皆様の利益に配慮する必要性があること等から、本業務提携に関し、経営資源・人材の相互活用や意思決定のスピードなどにおいて、一定の限界があるものと認識しているとのことです。そこで、対象者は、本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、以下のメリットをより効率的に享受できることが見込まれ、対象者の収益基盤と事業競争力の強化に繋がり、中長期的にも対象者の企業価値の持続的な向上に資するとの結論に至ったとのことです。
(ⅰ) バックエンド業務の共通化による経営の強化
公開買付者との間で、既に2021年6月、公開買付者が運営する「LINEマンガ」のバックエンド業務の一部を対象者が受託する本業務提携を実施しているとのことです。本業務提携におけるバックエンド業務は、電子書籍配信に関するバックエンドシステムの開発・運用、配信コンテンツの入稿、書誌データ管理に関するオペレーション、電子書籍コンテンツの調達及び提供を指しており、「LINEマンガ」の同業務を対象者が受託するとともに、「ebookjapan」の同業務との共通化を進めることを目指しているとのことです。本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、意思決定の迅速化や公開買付者と対象者間での人員交流等が促進され、バックエンド業務の共通化に向けた連携がより強固なものとなり、取扱規模の拡大及び出版社窓口の一本化の結果、事業効率の改善及び出版社への営業力の強化、並びにコンテンツ力の向上を着実に図ることを見込んでいるとのことです。
(ⅱ) 販売作品数の増加によるユーザーの獲得
公開買付者が運営する「LINEマンガ」は、配信作品数約60万点の国内最大級のコミックサービスであり、特にオリジナル・独占・先行配信作品を480タイトル以上取り揃えているとのことです。グローバル市場で多くのユーザーの人気を得ている縦スクロールのカラー作品であるWEBTOON等、対象者には少ないオリジナル作品を多数有しており、これらを「ebookjapan」でも販売可能とすることにより、ユーザーの獲得並びに収益の拡大に繋がると考えているとのことです。
(ⅲ) マーケットにおける利用者層の拡大
「LINEマンガ」は主にiOS、Androidアプリで多くの利用者を獲得しているのに対し、「ebookjapan」は WEB ブラウザで多くの利用者を獲得しており、また、利用者層においても比較的若年層が多い「LINEマンガ」と、中高年層を含めた幅広い利用者を持つ「ebookjapan」とで、それぞれ異なる強みを持っているとのことです。これらは、相互に補完し合う関係にあり、今後両社が持つマーケティングソリューションを最大限活用し、統一されたブランドマーケティングを行うことで、WEBブラウザ、アプリの両方に強みを持ち、若年層から中高年層まで幅広い年齢層の利用者に支持される国内随一の電子書籍サービスグループとなることが可能と考えているとのことです。
以上の点を踏まえて、対象者は、2021年9月30日、本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、公開買付者との間で電子書籍事業の幅広い分野において互いの強みを活かし、さらなる連携強化を図ることは、対象者の中長期的な企業価値向上に資するものであるとの考えに至ったとのことです。
さらに、(a)本公開買付価格が、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の大和証券による対象者株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価平均法に基づく算定結果の上限を上回るものであり、かつ、以下DCF法に基づく評価レンジの範囲内であり、かつ中央値(DCF法による算定の基礎となる割引率及び永久成長率について、その感応度分析において用いた数値の中央値を使用して算出された対象者株式の1株当たりの株式価値)の4,788円と遜色ない価格であると認められること、(b)本公開買付価格が、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日(なお、対象者は、公開買付者らから、2021年6月1日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せているとの説明を受けていたとのことですが、対象者としては、当該可能性を合理的に検証することができないことから、他の同種の案件において一般的である、公表日の前営業日を基準とした一定期間の株価のプレミアムを考慮しているとのことです。)である2021年9月29日の直近1ヵ月間の終値単純平均値4,000円に対して18.75%のプレミアムを加えた価格、直近3ヵ月間の終値単純平均値3,697円に対して28.48%のプレミアムを加えた価格、直近6ヵ月間の終値単純平均値3,274円に対して45.08%のプレミアムを加えた価格であり、このうち、直近1ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアム率を取り上げると、直近約2年間(2019年8月以降)に公表された公開買付けを利用した支配株主による完全子会社化事例におけるプレミアム水準(中央値が36%程度から41%程度)に照らして、必ずしも高い水準であるとは言い難いものの、直近3ヵ月間の終値単純平均値及び直近6ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアムに鑑みれば、本公開買付価格は相応のプレミアムが付された価格であると評価できること、(c)本公開買付価格は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値4,510円に対して5.32%のプレミアムを加えた価格であり、当該プレミアムについては、非公開化を目的とした他の公開買付けの事例におけるプレミアム水準との比較において低水準であると考えられるものの、2021年9月27日以降、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日までの3日間において対象者株式の株価が急激に変動していること、及び、本公開買付価格は、対象者が2011年10月に東京証券取引所マザーズ市場にその株式を上場して以来の市場株価の最高値を超える水準であることを勘案すると、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日における対象者株式の終値に対するプレミアムが低水準であることをもって、本公開買付価格の合理性が欠けることになるものではないと考えられること、(d) 本公開買付価格の決定に際しては、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置が採られており、少数株主の利益への配慮がなされていると認められること、(d)本公開買付価格が、上記の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置が採られた上で、公開買付者らと対象者との間で、それぞれ独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が行われた上で決定された価格であること等を踏まえ、対象者は、2021年9月30日、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
同様に、本新株予約権買付価格についても、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者株式数(第10回新株予約権及び第11回新株予約権については200、第12回新株予約権ないし第17回新株予約権については100)を乗じた金額をもとに算定されているものであるため、本公開買付けは、対象者の新株予約権者の皆様に対して合理的な本新株予約権の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
以上より、対象者は、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。対象者取締役会決議の詳細については、下記「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
③ 本公開買付け後の経営方針
本公開買付け後の対象者の事業に係る公開買付者らの戦略や将来の事業戦略については、上記「① 本公開買付けの目的及び背景」の(ⅰ)ないし(ⅳ)の期待される事業シナジーをもとに、公開買付者らと対象者との間で今後協議の上、決定していくことになります。なお、公開買付者らは、本公開買付け後も、対象者の事業の特性や対象者の強みを十分に活かした経営を行い、対象者の事業の強化を図ってまいります。また、公開買付者らは、本公開買付け後の対象者の経営体制に関して、現状の対象者の経営体制を尊重しつつ、これを維持すること及びこれに加えて公開買付者らから対象者への役員の派遣を想定しておりますが、公開買付者らから対象者へ派遣する役員の人数等を含め現時点で具体的に決定された事実はございません。
下記「(4) 本公開買付けに関する重要な合意」に記載のとおり、公開買付者、NAVER及びZホールディングスは、本公開買付けの成立後、今後の「ebookjapan」の運営につき、その見直し・改定の要否を含め、誠実に協議する予定です。
(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
本書提出日現在において、対象者は公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当いたしませんが、公開買付者は、本公開買付け後、本書提出日現在対象者株式2,443,600株(所有割合43.18%)を所有し対象者を連結子会社としているヤフーを株主として残して、本スクイーズアウトを実施することを予定していることから、対象者の少数株主と利害が一致しない可能性があることを踏まえ、公開買付者及び対象者は、対象者の少数株主の皆様への影響に配慮し、本公開買付価格の公正性を担保しつつ、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、以下のような措置を実施いたしました。
なお、以下の記載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。また、公開買付者は、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」の応募を本公開買付け成立の条件とはしておりませんが、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、ヤフーは、本書提出日現在、対象者株式を2,443,600株(所有割合:43.18%)所有していることから、本公開買付けにおいて、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」の買付予定数の下限を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応募することを希望する一般株主の皆様の利益に資さない可能性もあるものと考えております。また、公開買付者及び対象者において以下①ないし⑤の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
① 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、2021年6月9日、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、東京証券取引所に独立役員として届け出ている対象者の社外取締役及び社外監査役のうち、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立した、寺田航平氏(対象者独立社外取締役、寺田倉庫株式会社代表取締役社長)、小林雅人氏(対象者独立社外取締役、シティユーワ法律事務所パートナー)、高橋鉄氏(対象者独立社外監査役、ITN法律事務所代表パートナー)の3名から構成される本特別委員会を設置したとのことです。なお、本特別委員会の委員は設置当初から変更されていないとのことです。本特別委員会の委員長については、対象者取締役会の構成員として経営判断に直接関与する立場にあり、対象者の事業に相当程度の知見を有していること、また、本公開買付けを含む本取引を検討する見識・適格性を有すること等を踏まえ、委員の互選に基づき、寺田航平氏が就任しているとのことです。また、本特別委員会の委員の報酬については、取引の成否にかかわらず時間単位の報酬のみとされており、本取引の成立を条件とする成功報酬は含まれていないとのことです。対象者取締役会は、本特別委員会設置の決定に資し、本特別委員会に対し、(a)本公開買付けについて対象者取締役会が賛同するべきか否か、及び、対象者の株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨するべきか否かを検討し、対象者取締役会に勧告を行うこと、(b)本非公開化取引についての対象者取締役会による決定((ⅰ)本公開買付けに賛同の意見を表明し、対象者の株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決定、及び、(ⅱ)本公開買付け後に行われる株式の併合等による非公開化手続きに係る決定をいう。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでないかを検討し、対象者取締役会に意見を述べること(上記の勧告及び意見に際しては、①本非公開化取引の目的が正当性を有するか、②本非公開化取引に係る手続きの公正性が確保されているか、③本非公開化取引の取引条件の妥当性が担保されているかについて検討するものとする。また、本非公開化取引に関する交渉状況等に応じて、本特別委員会が必要又は適切と認める場合は、本特別委員会は、上記諮問事項を追加又は変更することができる。)を諮問(以下「本諮問事項」といいます。)し、これらの点についての答申書を対象者に提出することを委嘱したとのことです。また、対象者は、2021年6月9日付の上記取締役会において、(a)取締役会における本取引に関する意思決定は、本公開買付けへの賛否及び応募推奨の有無を含め、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うこと、(b)本特別委員会が本非公開化取引の取引条件が妥当でないと判断した場合、対象者取締役会は本取引の承認を行わないこととすることを併せて決議しているとのことです。さらに、対象者は、上記取締役会において、本特別委員会に対し、(a)対象者が公開買付者らとの間で行う交渉の過程に実質的に関与すること(必要に応じて公開買付者らとの交渉方針に関して指示又は要請を行うこと、及び、自ら公開買付者らとの交渉を行うことを含みます。)、(b)本諮問事項に関する答申を行うに際し、必要に応じ、自らの財務もしくは法務等に関するアドバイザーを選任し(この場合の費用は対象者が負担する。)、又は、対象者の財務もしくは法務等に関するアドバイザーを指名しもしくは承認(事後承認を含みます。)すること、(c)必要に応じ、対象者の役職員から本非公開化取引に関する検討及び判断に必要な情報を受領すること及び(d)その他本非公開化取引に関する検討及び判断に際して必要と本特別委員会が認める事項に関する権限を付与したとのことです。
本特別委員会は、2021年6月16日より2021年9月30日までの間に合計20回、合計約24時間開催され、本諮問事項についての協議及び検討が慎重に行われたとのことです。具体的には、本特別委員会は、対象者の第三者算定機関かつファイナンシャル・アドバイザーである大和証券及びリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所につき、いずれも独立性及び専門性に問題がないことから、それぞれ対象者のファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザーとして承認したとのことです。
その後の具体的な審議状況として、本特別委員会は、①対象者に対して質問事項を提示し、対象者との間で、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等についてインタビュー形式により質疑応答を実施し、②別の会合において、NAVERに対して質問事項を提示し、同社との間で、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等についてインタビュー形式により質疑応答を実施したとのことです。
また、本特別委員会は、対象者が作成した本事業計画について、対象者からその内容及び作成経緯等について説明を受けるとともに、これらの事項について合理性を確認しているとのことです。そして、大和証券からの、本事業計画を基礎として行った株式価値算定の内容、DCF法及びDCF法における割引率の計算根拠を含む重要な前提条件についての説明も踏まえて、質疑応答及び審議・検討を行った上で、これらの事項について合理性を確認しております。
さらに、本特別委員会は、対象者、大和証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、本取引の手続面における公正性を担保するための措置並びに本取引に係る対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の利益相反を回避するための措置の内容について説明を受け、本取引において手続きの公正性を確保するために講じるべき措置について審議・検討を行っているとのことです。
また、本特別委員会は、大和証券から受けた財務的見地からの助言を踏まえ、公開買付者からより高い価格を引き出すために、相互に独立した第三者間のM&Aで行われる一般的な交渉プロセスに即して十分な交渉を実施することを含む交渉方針について審議・検討するとともに、本特別委員会が公開買付者らから公開買付価格に関する提案を受領する都度、大和証券から受けた財務的見地からの助言も踏まえて公開買付者らに対する交渉方針を審議・検討した上で、公開買付者らと直接書面のやり取りを行うこと等により、公開買付者らとの間で公開買付価格に関する協議・交渉を行ったとのことです。
具体的には、2021年8月10日に公開買付者らより公開買付価格を1株当たり4,000円とすることを含む提案書を受領したのに対し、本特別委員会は、大和証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から聴取した意見を踏まえて検討を行った上で、提案された公開買付価格は公正な価格に達しておらず、対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないとして、公開買付者らに対し公開買付価格の再検討を要請したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、公開買付価格を1株当たり4,250円とする提案を受領したとのことです。当該提案を受け、対象者は、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである大和証券を通じて、公開買付者らとの間で協議を継続いたしましたが、本特別委員会は、当該大和証券を通じた協議の内容並びに大和証券からの財務的見地からの助言及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的見地からの助言を踏まえ、NAVERに対し、上記の提案価格は、大和証券によりDCF法に基づき算定される株式価値の水準に照らし、引き続き対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないと考えていること等を理由として、再度公開買付価格の再考を依頼したとのことです。その後も公開買付者らとの間で、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである大和証券を通じて、継続的に協議及び交渉を行い、その結果、本特別委員会は、2021年9月24日、公開買付者らから、本公開買付価格を4,750円とすることを含む最終提案を受けるに至ったとのことです。
また、本特別委員会は、公開買付者らとの間で、本新株予約権買付価格についても、協議・交渉を行っているとのことです。具体的には、対象者は、公開買付者らより、上記の2021年8月10日付の提案書において、本新株予約権買付価格について、新株予約権1個につき1円とする提案を受けたとのことです。これに対し、本特別委員会は、2021年8月13日、公開買付者らに対し、当該新株予約権は、対象者役職員に対する報酬制度として付与しているものであり、特に、当該新株予約権の内、現時点では行使不可であるものの、保有者に多大な経済的価値が見込まれる新株予約権を適切な価格で買い取らないとすると、保有者である対象者従業員のモチベーションが大きく低下し、非公開化後の経営統合プロセスに支障をきたす事が想定されることから、権利行使をした場合に利益が出る状態にある新株予約権については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とするように再考を依頼したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、新株予約権に係る買付価格については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とする旨の提案を受けるに至ったとのことです。
本特別委員会は、以上の経緯の下、大和証券株式価値算定書等も考慮し、本諮問事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、2021年9月30日付で、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の答申書を提出しているとのことです。
(ⅰ) 答申内容
a 対象者取締役会は、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者株主及び本新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨するべきであると考えられる。
b 対象者取締役会が、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を決定することは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられる。また、対象者取締役会が、本取引において予定されている方法によることを前提に、本公開買付け成立後の本株式併合による対象者の非公開化についての決定をすることは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられる。
(ⅱ) 答申理由
ⅰ 本取引が対象者の企業価値向上に資するものであり、その目的は正当なものであると認められるかについて
・世界的にみても市場規模が大きく、また、エンターテインメントサービスの源泉となる知的財産権が多く存在する日本の電子コミック市場は、多数の競合他社が存在する極めて競争環境の厳しい市場である。対象者は、かかる厳しい競争環境を勝ち抜き、電子書籍分野での国内取扱高No.1を獲得するためには、収益基盤と事業競争力の強化がその経営課題であると認識し、現在、Zホールディングスグループとのシナジー強化に取り組んでいる。もっとも、対象者によれば、競争の激しい国内電子コミック市場において、国内取扱高No.1という対象者の目標を達成するためには、(a)競合他社を上回る規模・効率での広告・販促活動や投資の継続、(b)対象者が競合他社と比較して補強が必要であると認識している領域(サービスに対する認知の向上、若年層利用者の取り込み、電子書籍アプリの強化、先行・独占・オリジナル等のコンテンツ強化等)への投資、(c)消費者ニーズの変化に対する迅速な対応(スマートフォンに特化した縦スクロールのカラーコンテンツの拡充、無料で読めるコンテンツの拡充等)及び(d)今後成長が見込まれるグローバル市場への積極的な展開といった各課題を解決していく必要があり、これらの各課題については、早期の解決を図っていくことが必要である一方で、現状のヤフー及びZホールディングスとの間の提携関係のみでは、その実現に相応の期間が必要となるものと考えており、外部企業との間の資本提携を含むパートナーシップの構築の必要性について検討を行っていたとのことである。
・公開買付者らの提案する、①公開買付者及び対象者の利用者の拡大、②人気IPの創出と獲得、③マーケティング戦略の統一と効率化、④サービス開発、インフラ基盤の安定と強化等の本取引によるシナジー及び本取引後の企業価値向上施策は、上記の対象者の経営課題の解決に資するものである。また、アプリを通じたコンテンツ配信に強みを持つ公開買付者とWEBを通じたコンテンツ配信に強みを持つ対象者が相互補完的に互いのプラットフォームを活用しつつ、より効率的に潜在的な顧客を獲得すると同時に、日本における優良マンガコンテンツの配信を行う対象者がコンテンツ配信を海外で展開する公開買付者らのグループに加入することで日本の優良マンガコンテンツのグローバルでの存在感の向上が可能であり、より広範な顧客層を対象として対象者のコンテンツ配信が可能になるという公開買付者らの説明は合理的であり、対象者にとって、本取引は、国内市場における競争力強化のみならず、グローバル市場への展開にも資するものと評価し得る。
・本取引後の各施策については、対象者は既に公開買付者との間でバックエンド業務に関する業務提携を実施しており、現在の資本構成の下でも実施可能なのではないかとの点が問題となり得るが、対象者によれば、公開買付者との間には資本関係はなく独立した当事者間の協業であることや上場を維持することにより一般株主の利益に配慮する必要性があること等から、当該業務提携に関しては、経営資源・人材の相互活用や意思決定のスピードなどにおいて、中長期的な成長を実現する上で一定の限界があると認識していたとのことである。本取引を実施して対象者が公開買付者の完全子会社となり、バックエンド業務に限らない分野も含めて両社がより密接に連携することで、上記のような厳しい市場環境において、対象者の収益基盤と事業競争力の強化に繋がり、スピード感をもって中長期的にも両社の成長戦略及び企業価値向上策を一体的に実現していくことが可能になるとのことである。
・公開買付者らの提案に対し、対象者の経営陣からは、①本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、意思決定の迅速化や公開買付者と対象者間での人員交流等が促進され、バックエンド業務の共通化に向けた連携がより強固なものとなり、取扱規模の拡大及び出版社窓口の一本化の結果、事業効率の改善及び出版社への営業力の強化、並びにコンテンツ力の向上を着実に図ることができること、②公開買付者が運営する「LINEマンガ」のオリジナル作品を「ebookjapan」でも販売可能とすることにより、ユーザーの獲得及び収益の拡大に繋がること、③アプリで多くの利用者を獲得し、利用者層においても比較的若年層が多い「LINEマンガ」と、WEB ブラウザで多くの利用者を獲得し、中高年層を含めた幅広い利用者を持つ「ebookjapan」は利用者層が異なり、相互に補完し合う関係にあるところ、今後両社が持つマーケティングソリューションを最大限活用し、統一されたブランドマーケティングを行うことで、WEBブラウザ、アプリの両方に強みを持ち、若年層から中高年層まで幅広い年齢層の利用者に支持される国内随一の電子書籍サービスグループとなることが可能となること等から、本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、公開買付者との間で電子書籍事業の幅広い分野において互いの強みを活かし、さらなる連携強化を図ることは、対象者の中長期的な企業価値の向上に資するものと考えているとの見解が示された。
・公開買付者らによれば、対象者及び公開買付者らの間でのシナジーを最大限発揮していく観点からは、対象者と密接な競業関係にあるヤフー及びその親会社であるZホールディングスとこれまで以上に緊密に連携していくことが不可欠であり、本取引後もヤフー及びZホールディングスと対象者の既存の協業関係は維持・継続する方針とのことである。
・対象者の親会社であるヤフーは本公開買付けに応募しないことが予定されているが、公開買付者らによれば、その目的は、本取引後もWEBTOON Entertainmentへの出資を間接的に継続し、本取引の実行により対象者に生まれるシナジーの一部を享受することができるZホールディングスグループと、本取引により対象者の株主ではなくなる一般株主との間で同一の価格で対象者株式を評価することは一般株主に不利益をもたらすとの考えから、ヤフーが所有する対象者株式を本公開買付価格より低い価格で評価するため、公開買付者がまず対象者が所有する自己株式及びヤフーの所有する株式を除く対象者株式の全てを本公開買付け及び株式併合により取得し、その後ヤフーが所有する対象者株式を本三角株式交換により取得するスキームを採用することとしたものであり、かかる説明に特段不合理な点は認められない。
・対象者は、本取引によって対象者は非公開化されることとなるが、韓国最大のインターネット・サービス企業である公開買付者らのグループの一員として十分な社会的信用力、知名度を維持するものであるから、資本市場からのエクイティによる資金調達の容易性が失われることによる影響や優れた人材の確保及び取引先の拡大等に与える影響は限定的であり、対象者の企業価値を毀損するものではないと考えられる。
ⅱ 本取引に係る手続きの公正性は確保されていると認められるかについて
・本取引においては、公開買付者、対象者、NAVER、ヤフー及びZホールディングスから独立した本特別委員会が、本取引に係る取引条件等の形成過程の初期段階から設置され、アドバイザー等の選任・承認権限や本取引の取引条件等の交渉過程に実質的に関与する権限が付与された上、本特別委員会の答申内容を最大限尊重して本取引に係る意思決定を行うものと決議されているところ、本特別委員会はこれらの権限を行使して、直接の交渉主体として、公開買付者との間の取引条件に関する交渉を行った。
・本特別委員会及び対象者は、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、各種のアドバイスを受けている。
・特別委員会及び対象者は、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したファイナンシャル・アドバイザーである大和証券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼し、2021年9月29日付で大和証券株式価値算定書を取得している。
・対象者においては、利害関係を有する取締役等を本取引の検討・交渉過程から除外し、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立した立場で検討・交渉等を行うことができる体制が構築されていたものと認められる。
・本公開買付けにおいては、いわゆる間接的なマーケット・チェックが行われているものと認められる。
・本公開買付けにおいては、公開買付期間が法令に定められた最短期間である20営業日を超える31営業日に設定されている。
・本公開買付けにおいては、一般株主による十分な情報に基づく適切な判断の機会が確保される予定であると認められる。
・本取引においては、本公開買付けの決済完了後、公開買付者は速やかに本株式併合にかかる臨時株主総会の開催を対象者に要請し、また、本株式併合に際して株主に交付される予定の金銭の額を本公開買付価格と同額に設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定であることから、強圧性が排除されているものと認められる。
・本公開買付けにおいては、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)条件が設定されていないものの、本公開買付けが成立した場合に公開買付者及びヤフーが対象者の議決権数の3分の2以上を所有することとなるようにするため、1,328,800株(所有割合:23.48%)が買付予定数の下限として設定される予定である。かかる下限は、相当程度の一般株主の応募がなければ本公開買付けが成立しないという意味において、一定程度の公正性担保措置として機能すると考えられ、また、本取引においては、他に十分な公正性担保措置が講じられていることからすれば、マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)が設定されていないとしても、それのみにより本取引における手続きの公正性が損なわれるものではないと考えられる。
ⅲ 一般株主の利益を図る観点から、取引条件の妥当性は確保されていると認められるかについて
・本取引の買収の方法について、一段階目として本公開買付けを行い、二段階目として本株式併合を行う方法は、本取引のような非公開化の取引においては一般的に採用されている方法である。
・本取引の取引条件に係る協議・交渉過程においては、公開買付者らによる最終意向表明書の提出後も、本特別委員会の要請に基づき、これ以上の価格交渉が困難であると判断されるまで協議・交渉を繰り返し、結果として公開買付者らから有意な譲歩(当初の4,000円から750円(18.7%)増額された4,750円という提案)を引き出した本公開買付価格が提案されている等、本特別委員会の実質的な関与のもと、企業価値を高めつつ少数株主にとってできる限り有利な取引条件で本取引が行われることを目指した合理的な努力が行われる状況が確保されていたものと認められる。
・大和証券株式価値算定書におけるDCF法に基づく算定の基礎とされている対象者の事業計画の策定目的、策定手続及び内容につき特に不合理な点はないと認められる。対象者によれば、本業務提携の具体的な業務は開始していないため、その影響については引き続き精査中であること、また、本取引が実施されないとの前提を置く場合、本業務提携が解消される可能性もあることから、本業務提携が対象者の業績に与える影響については、本事業計画には織り込まれていないとのことであるが、本取引が実施されないとの前提を置く場合に本業務提携が解消される可能性があるとの対象者の説明に不合理な点はなく、リーガル・アドバイザー、ファイナンシャル・アドバイザーの助言も経た上で、対象者のスタンドアロンベースの事業計画において本業務提携の影響が織り込まれていないことに不合理な点はないと認められる。
・大和証券株式価値算定書の内容は、算定の方法及び内容のいずれにおいても不合理な点は認められず、信用できるものと判断するところ、本公開買付価格は、大和証券株式価値算定書の市場株価平均法に基づく算定結果の上限を上回り、DCF法に基づく評価レンジの範囲内にあり、かつ中央値(DCF法による算定の基礎となる割引率及び永久成長率について、その感応度分析において用いた数値の中央値を使用して算出された対象者株式の1株当たりの株式価値)の4,788円と遜色ない価格であると認められる。
・本公開買付価格は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日の直近1ヵ月間の終値単純平均値4,000円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値について同じです。)に対して18.75%のプレミアムを加えた価格、直近3ヵ月間の終値単純平均値3,697円に対して28.48%のプレミアムを加えた価格、直近6ヵ月間の終値単純平均値3,274円に対して45.08%のプレミアムを加えた価格であり、このうち、直近1ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアム率を取り上げると、直近約2年間(2019年8月以降)に公表された公開買付けを利用した支配株主による完全子会社化事例におけるプレミアム水準(中央値が36%程度から41%程度)に照らして、必ずしも高い水準であるとは言い難いものの、直近3ヵ月間の終値単純平均値及び直近6ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアムに鑑みれば、本公開買付価格は相応のプレミアムが付された価格であると評価できると考えられる。他方で、本公開買付価格は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値4,510円に対して5.32%のプレミアムを加えた価格であり、当該プレミアムについては、非公開化を目的とした他の公開買付けの事例におけるプレミアム水準との比較においてプレミアムが低水準であると考えられるものの、2021年9月27日以降、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日までの3日間において対象者株式の株価が急激に変動していること、及び、本公開買付価格は、対象者が2011年10月に東京証券取引所マザーズ市場にその株式を上場して以来の市場株価の最高値を超える水準であることを勘案すると、公表日の前営業日における対象者株式の終値に対するプレミアムが低水準であることをもって、本公開買付価格の合理性が欠けることになるものではないと認められる。
・本新株予約権買付価格は、それぞれ、本公開買付価格と行使価格の差額に目的株式数を乗じた額とされており、本公開買付価格と同等の水準にあると認められる。
・(a)本三角株式交換における株式交換比率は、①ヤフーの所有する対象者株式の1株当たり価値を、本公開買付け価格において公開買付者が市場価格に対して反映するプレミアムを考慮せず、3,529円(本公開買付価格の最終提案日である2021年9月24日までの過去1ヵ月間(2021年8月25日から2021年9月24日まで)における対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値単純平均値に対して公開買付者ら及びZホールディングス間で協議して定めた一定のディスカウントを行った価格とすること、②本三角株式交換の対価として交付されるWEBTOON Entertainment株式の1株当たり価値を、NAVERが行うWEBTOON Entertainmentへの出資における1株当たり払込価格と同額として定めること、並びに、(b)本三角株式交換の効力発生後にNAVERが所有するWEBTOON Entertainment株式及び議決権と、Zホールディングスグループが所有するWEBTOON Entertainment株式及び議決権の比率が、本公開買付け公表日における当該比率である66.6%:33.4%と等しくなるように調整し、もって本取引を通じたNAVER及びZホールディングスグループによるWEBTOON Entertainment株式の取得が出資比率に応じた比例的なものとなることが予定されており、それにより、NAVER及びZホールディングスグループの間で利益移転が生じないように配慮されており、本三角株式交換が対象者の一般株主に比して有利なものとならないことが確保されるものと評価できる。
・本公開買付価格、本新株予約権買付価格及び本三角株式交換における株式交換比率以外の本取引の取引条件に関しても、対象者の一般株主の犠牲のもとに、公開買付者ら及びZホールディングスグループが不当に利益を得るものと認めるべき事由は確認されておらず、本取引の取引条件の妥当性を害する事情は見当たらない。
・以上のとおり、対象者の一般株主の利益を図る観点から、本取引の取引条件の妥当性は確保されていると考えられる。
ⅳ 対象者取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行うことの是非について
・上記ⅰのとおり、本取引は対象者の企業価値向上に資するものと認められ、本取引の目的は正当なものと考えられるため、対象者取締役会は、本公開買付けについて賛同すべきであると考えられる。
・また、上記ⅱのとおり、本取引においては、一般株主利益を確保するための公正な手続きが実施されており、上記ⅲのとおり、本取引の取引条件の妥当性は確保されていると考えられるため、対象者取締役会は、本公開買付けへの応募を推奨すべきであると考えられる。
ⅴ 上記ⅰからⅳを踏まえて、本取引が対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考えられるかについて
・上記ⅰからⅳを踏まえれば、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を決定することは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられ、また、対象者取締役会が、本取引において予定されている方法によることを前提に、本公開買付け成立後の本株式併合についての決定をすることは、対象者の一般株主にとって不利益ではないと考えられる。
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書・意見書の取得
(ⅰ) 対象者株式に係る算定の概要
対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者から提示された本公開買付価格を検討し、本公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨を行うにあたり、公正性を担保するための措置として、対象者、ヤフー及び公開買付者から独立した第三者算定機関である大和証券に対して、対象者株式の株式価値算定を依頼し、大和証券から2021年9月29日付で大和証券株式価値算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、大和証券から本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。
大和証券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者株式が東京証券取引所市場第一部に上場していることから市場株価平均法を、対象者業績の内容や予想等を評価に反映するためにDCF法を用いて対象者株式の株式価値の算定を行い、対象者は大和証券から2021年9月29日付で、大和証券株式価値算定書を取得しているとのことです。
大和証券によれば、対象者株式の株式価値算定にあたり、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。
市場株価平均法 3,274円から4,510円
DCF法 4,043円から5,814円
市場株価平均法では、2021年9月29日を算定基準日として、対象者株式の東京証券取引所市場第一部における基準日終値4,510円、直近1ヵ月間の終値単純平均値4,000円、直近3ヵ月間の終値単純平均値3,697円及び直近6ヵ月間の終値単純平均値3,274円をもとに、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲は、3,274円から4,510円までと算定しているとのことです。
DCF法では、対象者が作成した本事業計画に基づく収益予測や投資計画等、合理的と考えられる前提を考慮した上で、対象者が2022年3月期第2四半期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を分析し、1株当たりの株式価値の範囲は、4,043円から5,814円までと算定しているとのことです。なお、割引率は9.1%~11.1%を採用しており、継続価値の算定については永久成長法を採用し、永久成長率を0.0%~1.0%として算定しているとのことです。
大和証券がDCF法において前提とした本事業計画に基づく財務予測は以下のとおりとのことです。なお、本事業計画には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2022年3月期から2027年3月期にかけて、電子書籍事業の市場拡大を背景とした電子書籍サービス「ebookjapan」の取扱高拡大により、継続的な増益を見込んでいるとのことです。2022年3月期から2024年3月期にかけては、グループシナジーのさらなる深化や広告宣伝を中心とした積極的なマーケティング投資によるユーザー獲得拡大を想定しており、アプリ及びウェブサイトの機能改善、オリジナル作品のラインアップ拡大等も相まって、継続的な取扱高の拡大を見込んでいるとのことです。その結果としての限界利益の増加、及び事業規模拡大に伴う固定費負担の軽減を踏まえ、2022年3月期及び2024年3月期は、大幅な増益を見込んでいるとのことです。その後、2025年3月期においては、ユーザー獲得のためのマーケティング投資が一巡する事に伴い売上高広告宣伝費率を抑制することで、大幅な増益を見込んでいるとのことです。また、本取引実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、本事業計画には加味していないとのことです。なお、本業務提携が業績に与える影響については、本業務提携に基づく取り組みの範囲、時期等について当事者間で協議中であり、その影響についても引き続き精査中であること、また、本取引が実施されないとの前提を置く場合には、本業務提携が解消される可能性もあることから、本事業計画には織り込んでおりません。
(単位:百万円)
| 2022年 3月期 (9ヵ月) | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | |
| 売上高(新収益認識基準) | 25,928 | 41,736 | 51,672 | 59,441 | 67,992 | 77,276 |
| 営業利益 | 1,022 | 1,593 | 2,493 | 3,708 | 4,474 | 5,347 |
| EBITDA | 1,277 | 1,971 | 2,860 | 4,064 | 4,865 | 5,702 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 186 | 75 | 405 | 1,493 | 1,982 | 2,455 |
(ⅱ) 本新株予約権に係る算定の概要
本新株予約権買付価格に関しては、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者株式数(第10回新株予約権及び第11回新株予約権については200、第12回新株予約権ないし第17回新株予約権については100)を乗じた金額をもとに算定されているものであるため、本公開買付けは、対象者の本新株予約権者の皆様に対して合理的な本新株予約権の売却の機会を提供するものであると判断しているとのことです。
なお、本新株予約権はいずれも、譲渡による取得については対象者取締役会の承認を要するものとされておりますが、対象者は、本新株予約権の譲渡が可能となるよう、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けの成立を条件として、本新株予約権の新株予約権者の皆様が、その所有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより公開買付者に対して譲渡することについて包括的に承認すること、及び譲渡を希望する本新株予約権者との間では新株予約権割当契約の内容を変更し譲渡可能な内容とする旨を決議しているとのことです。
③ 対象者における独立した法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定過程における透明性及び合理性を確保するため、2021年6月上旬、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けにおける意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けにおける意思決定にあたっての留意点について、必要な法的助言を受けているとのことです。また、アンダーソン・毛利・友常法律事務所は対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。
④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
対象者プレスリリースによれば、対象者は、大和証券から取得した大和証券株式価値算定書、本特別委員会から提出された答申書、アンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的助言その他の関連資料を踏まえ、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件について、慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
その結果、対象者は、2021年9月30日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
当該取締役会においては、対象者の取締役のうち、津留崎耕平氏及び秀誠氏は、ヤフーの執行役員兼任者であること、高橋将峰氏は、ヤフーの出身者(2019年4月付で対象者に転籍)であることから、利益相反のおそれを回避し、本取引の公正性を担保する観点から、(ア)まず対象者の取締役5名のうち、津留崎耕平氏、秀誠氏及び高橋将峰氏を除く、2名の取締役において審議の上、その全員一致により上記の決議を行い、さらに、対象者取締役会の定足数を確保する観点から、(イ)高橋将峰氏を加えた3名の取締役において改めて審議の上、その全員一致で再度上記の決議を行うという二段階の決議を経ているとのことです。また、上記の取締役会に出席した監査役(監査役3名中、出席監査役2名(うち社外監査役2名))の全員が上記決議につき異議はない旨の意見を述べているとのことです。
なお、対象者の取締役のうち、津留崎耕平氏及び秀誠氏の2名は、本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題による影響を受けるおそれを排除する観点から、上記2021年9月30日開催の対象者取締役会を含む本取引に係る対象者取締役会の審議及び決議には参加しておらず、かつ、対象者の立場において、本取引に係る検討並びに公開買付者との協議及び交渉に参加していないとのことです。
また、高橋将峰氏は、取締役会の定足数を確保する観点から上記取締役会の二段階目の審議及び決議に参加したものの、ヤフーの出身者であることから、利益相反のおそれを回避し、本取引の公正性を担保する観点から、対象者の立場において本取引に関する検討並びに公開買付者との協議及び交渉には参加していないとのことです。
また、対象者の監査役である鬼塚ひろみ氏はヤフーの監査役を兼務していることから、上記の取締役会の審議には一切参加しておらず、上記の取締役会の決議に対して意見を述べることを差し控えているとのことです。
⑤ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、比較的長期間である31営業日としております。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主及び新株予約権者の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、本公開買付価格の適正性も担保することを企図しております。さらに、公開買付者と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定と合わせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保にも配慮しております。
(4) 本公開買付けに関する重要な合意
本公開買付けの実施に際して、公開買付者は、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、NAVER及びZホールディングスとの間で、2021年9月30日付で本取引契約を締結しております。
本取引契約においては、①本不応募株式について、ヤフーをして本公開買付けに応募させないこと、②本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの公開買付期間末日以後、決済の開始日前にNAVERがWEBTOON Entertainmentを通じて公開買付者に対して本出資を行うこと、③本公開買付けの成立後に、本株式併合により対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとすること、④本スクイーズアウトの完了後に、本三角株式交換を実行すること、⑤本三角株式交換の対価は下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり決定とすること、⑥本三角株式交換の効力発生後に、本グループ内移転を行うこと、⑦本三角株式交換の効力発生後に、本追加出資を行うこと、⑧本公開買付けの成立後、各当事者は対象者及びヤフーの間の2021年3月23日付「プラットフォームサービスの提供等に関する契約書」(「ebookjapan」の運営に関して必要となる事項を含みます。)につき、その見直し・改定の要否を含め、誠実に協議すること、⑨各当事者は、本取引の実行に関して必要となる各国における競争法令等及び投資規制法令等上の手続き(許認可等の取得及び必要な待機期間又は審査期間の経過を含みます。)を、実務上可能な限り速やかに完了させるために合理的な範囲で各自努力し、互いに協力すること、⑩Zホールディングスが、本取引契約の締結日から本取引完了日までの間、本不応募株式に係る株主としての権利に基づき合理的に可能な範囲において、本取引契約において企図される取引を除き、対象者をして、従前の慣行に従った通常の業務の範囲内において、その業務を行わせるとともに、一定の行為を実施させないこと(注1)、⑪NAVERが、本取引契約の締結日から本取引完了日までの間、本取引契約において企図される取引を除き、WEBTOON Entertainment及びその子会社をして、従前の慣行に従った通常の業務の範囲内において、その業務を行わせること、⑫各当事者は、本取引完了日をもって、対象者及びヤフーの間の2016年6月9日付「資本業務提携契約」を終了させることを相互に確認し、Zホールディングスはヤフーをして、公開買付者は対象者をして、当該終了に係る合意を行わせることを合意しております。
(注1) 対象者による実施が制限される「一定の行為」とは、(ⅰ)定款その他の重要な社内規程の変更、(ⅱ)自己株式又は自己新株予約権の取得、(ⅲ)株式、新株予約権又は社債(新株予約権付社債を含む。)の発行又は自己株式の処分、(ⅳ)株式の分割もしくは併合、又は株式もしくは新株予約権の無償割当て、(ⅴ)役員報酬等の総額の決定又は変更、(ⅵ)合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、事業の全部又は重要な一部の譲渡又は譲受その他これらに準じる行為(対象者において適時開示を要しないものを除く。)、(ⅶ)資本金もしくは準備金の額の減少、会社法第450条第1項に定める資本金の額の増加、会社法第451条第1項に定める準備金の額の増加又は会社法第452条に定める剰余金の処分、(ⅷ)剰余金の配当、(ⅸ)これらのほか、通常の業務の範囲外の行為であって、かつ、本取引の実施に重要な影響を与え、又は本取引の目的の達成を著しく困難とするおそれのあるものをいいます。
加えて、本取引契約においては、各当事者は、上記のほか、自らについての表明保証(注2)を行い、契約違反時の補償義務、秘密保持義務、本取引契約上の権利義務の譲渡禁止に係る義務、本取引契約に定めのない事項についての誠実協議義務を負担しております。
(注2) 本取引契約において、公開買付者は、(a)公開買付者の設立及び存続、(b)本取引契約の締結及び履行に係る権限の保有並びに法令及び定款その他の社内規則上必要な社内手続きの履践、(c)本取引契約の締結の有効性及び強制執行可能性、(d)本取引契約の法令、定款その他社内規則又は政府機関の判断等(政府機関等の判決、決定、命令、裁判上の和解、許可、認可、免許、承認、勧告、指導、指示その他の判断を総称していいます。以下同じです。)への違反の不存在、(e)反社会的勢力ではないことをZホールディングスに対して、NAVERは、(a)NAVERの設立及び存続、(b)本取引契約の締結及び履行に係る権限の保有並びに法令及び定款その他の社内規則上必要な社内手続の履践、(c)本取引契約の締結の有効性及び強制執行可能性、(d)本取引契約の法令、定款その他社内規則又は政府機関の判断等への違反の不存在、(e)反社会的勢力ではないことをZホールディングスに対して、Zホールディングスは、(a)Zホールディングスの設立及び存続、(b)本取引契約の締結及び履行に係る権限の保有並びに法令及び定款その他の社内規則上必要な社内手続きの履践、(c)本取引契約の締結の有効性及び強制執行可能性、(d)本取引契約の法令、定款その他社内規則又は政府機関の判断等への違反の不存在、(e)反社会的勢力ではないこと、(f)ヤフーは対象者株式を2,443,600株所有しており、Zホールディングス及びその子会社は対象者株式、新株予約権、新株予約権付社債その他当該発行会社の株式を取得できる権利を保有していないことを公開買付者及びNAVERに対して、それぞれ表明し、保証しております。
(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者は、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより、本対象者株式及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、対象者に対して以下の一連の手続きの実行を要請し、対象者の株主を公開買付者及びヤフーのみとするための一連の手続きを実施することを予定しております。
具体的には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を対象者に要請する予定です。なお、公開買付者及びヤフーは本臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。また、公開買付者及びヤフーは、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの成立後速やかに、対象者に対して本臨時株主総会に関する基準日設定公告(本書提出日現在においては、基準日を2021年12月上旬とすることを予定しております。)を行うことを要請する予定です。
本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認いただいた場合には、対象者の株主は、本株式併合がその効力を生ずる日において、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することになります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続きに従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります(以下「本端数処理」といいます。)。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。
また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者及びヤフーのみが対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者、ヤフー及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定です。
また、本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、株式併合がなされた場合であって、株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、対象者の株主の皆様は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求できる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められております。上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者、ヤフー及び対象者を除きます。)が所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の株主は、上記申立てを行うことができることになる予定です。
上記手続きについては、関係法令についての改正、施行及び当局の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買付者及びヤフーの株券等所有割合及び公開買付者以外の対象者の株主の対象者株式の所有状況等によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。もっとも、本株式併合についての株式買取請求に関する価格の決定の申立てがなされた場合において、対象者株式の売買価格又は株式買取請求に関する価格は、最終的に裁判所が判断することになります。
以上の各場合における具体的な手続き及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
なお、公開買付者は、本公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されず残存した場合には、対象者に対して、本新株予約権の取得、本新株予約権者に対する本新株予約権の放棄の勧奨その他本取引の実行に合理的な手続きを実施することを要請し、又は実施する予定です。
加えて、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の賛同を勧誘するものではありません。本公開買付けへの応募又は上記の各手続きにおける税務上の取扱いについては、対象者の株主が自らの責任にて税務専門家にご確認ください。
また、公開買付者及び対象者は、本スクイーズアウトの完了後、法第24条第1項但書に基づき対象者の有価証券報告書提出義務の中断申請に対する承認が得られた後に、対象者との間で本三角株式交換に係る株式交換契約を締結し、公開買付者を株式交換完全親会社、対象者を株式交換完全子会社とし、WEBTOON Entertainment株式を対価とする三角株式交換を実施することを予定しております。
本三角株式交換においては、法定の必要手続きを踏むことにより本スクイーズアウトの完了後に存在する不応募株式はWEBTOON Entertainment株式と交換され、WEBTOON Entertainment株式の1株以上が割り当てられた対象者の株主(ヤフーを意味します。)は、公開買付者の親会社であるWEBTOON Entertainmentの株主となります。
公開買付者が本三角株式交換の対価として交付するWEBTOON Entertainment株式につき、その総数は、(A)本スクイーズアウトの効力発生の直前時に存在する不応募株式数に(B)市場価格を基準に定める対象者株式1株当たりの評価額を乗じた金額から(C)本スクイーズアウトにおける本端数処理の過程でヤフーに対して交付される金銭の金額を控除し、上記で算出された金額を(D)WEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額で除して算出することを予定しております。この対価として交付する株式数の算定に際しては、本三角株式交換が本公開買付けにおける対象者の少数株主に比して有利なものとならないよう、また、その妥当性を確保するため、公開買付者は、(B)市場価格を基準に定める対象者株式1株当たりの評価額については、3,529円(本公開買付価格の最終提案日である2021年9月24日までの過去1ヵ月間(2021年8月25日から2021年9月24日まで)における対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値単純平均値に対して公開買付者ら及びZホールディングス間で協議して定めた一定のディスカウントを行った価格)とすることで本公開買付け価格において公開買付者が市場価格に対して反映するプレミアムを考慮せず、また、(D)WEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額については、WEBTOON EntertainmentがNAVER及びZホールディングスグループの合弁会社であることに鑑み、本取引の各段階におけるWEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額次第で、NAVER及びZホールディングスグループの間で利益移転が生じることがないよう、本取引を通じてNAVER及びZホールディングスグループがWEBTOON Entertainment株式を出資比率に応じて同一額で取得することが必要であるとの考えから、本出資においてNAVERからその子会社であるWEBTOON Entertainmentへの払込みを行う際の1株当たりの払込金額と同額を使用する予定です。
なお、公開買付者による本三角株式交換の効力発生後、本三角株式交換の対価としてヤフーに交付されたWEBTOON Entertainment株式は、現物配当その他の方法により、ヤフーからZホールディングスへと移転される予定です。
また、公開買付者らは、公開買付者による本三角株式交換の効力発生後、WEBTOON Entertainmentの株主である(ⅰ)NAVER及び(ⅱ)Zホールディングスグループ間のWEBTOON Entertainmentへの出資比率が本公開買付け公表日における(ⅰ)NAVER及び(ⅱ)Zホールディングスグループ間の出資比率である(ⅰ):(ⅱ)=66.6%:33.4%と等しくなるように調整し、もって本取引を通じたNAVER及びZホールディングスグループによるWEBTOON Entertainment株式の取得が出資比率に応じた比例的なものとなることを確保するため、NAVERは、WEBTOON Entertainmentに対する追加出資を実施する予定です(本追加出資)。NAVERによる追加出資の金額は、(A)本三角株式交換の対価として交付されたWEBTOON Entertainment株式数に66.6/33.4(=1.994)を乗じたものから、(B)本出資によりNAVERが取得したWEBTOON Entertainment株式数を減じ、当該計算により算出された株式数に(C)WEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額を乗じたものとなる予定です。当該(C)WEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額についても、本取引の各段階におけるWEBTOON Entertainment株式1株当たりの評価額次第で、NAVER及びZホールディングスグループの間で利益移転が生じることがないよう、本取引を通じてNAVER及びZホールディングスグループがWEBTOON Entertainment株式を出資比率に応じて同一額で取得することが必要であるとの考えから、本出資においてNAVERからその子会社であるWEBTOON Entertainmentへの払込みを行う際の1株当たりの払込金額と同額を使用する予定です。
(6) 上場廃止となる見込み及びその事由
対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従って、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。
また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後、上記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、公開買付者は、本スクイーズアウトを実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできません。
届出当初の期間
| 買付け等の期間 | 2021年10月1日(金曜日)から2021年11月15日(月曜日)まで(31営業日) |
| 公告日 | 2021年10月1日(金曜日) |
| 公告掲載新聞名 | 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 電子公告アドレス (https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/) |
買付け等の価格
| 株券 | 普通株式1株につき金4,750円 |
| 新株予約権証券 | 第10回新株予約権 1個につき金714,600円 第11回新株予約権 1個につき金714,600円 第12回新株予約権 1個につき金205,600円 第13回新株予約権 1個につき金204,000円 第14回新株予約権 1個につき金353,800円 第15回新株予約権 1個につき金397,900円 第16回新株予約権 1個につき金246,000円 第17回新株予約権 1個につき金169,700円 |
| 新株予約権付社債券 | ― |
| 株券等信託受益証券 ( ) | ― |
| 株券等預託証券 ( ) | ― |
| 算定の基礎 | ① 普通株式 公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際して、対象者が開示している財務情報、対象者に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、対象者の事業及び財務状況を多面的かつ総合的に分析いたしました。 また、公開買付者は、対象者株式が金融商品取引所を通じて取引されていることに鑑み、本公開買付けの公表日の前営業日である2021年9月29日の対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値4,510円、過去1ヵ月間(2021年8月30日から2021年9月29日まで)の終値単純平均値4,000円、過去3ヵ月間(2021年6月30日から2021年9月29日まで)の終値単純平均値3,697円及び過去6ヵ月間(2021年3月30日から2021年9月29日まで)の終値単純平均値3,274円を参考にいたしました。さらに、対象者との協議・交渉の結果、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けに対する応募の見通しを総合的に勘案し、最終的に2021年9月30日において本公開買付価格を1株当たり4,750円とすることを決定いたしました。 本公開買付価格である4,750円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2021年9月29日の対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値4,510円に対して5.32%、過去1ヵ月間(2021年8月30日から2021年9月29日まで)の終値単純平均値4,000円に対して18.75%、過去3ヵ月間(2021年6月30日から2021年9月29日まで)の終値単純平均値3,697円に対して28.48%、過去6ヵ月間(2021年3月30日から2021年9月29日まで)の終値単純平均値3,274円に対して45.08%のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。また、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、本公開買付価格である4,750円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である2,589円に対して83.47%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して79.58%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して81.16%のプレミアムをそれぞれ付した水準です。さらに、本公開買付価格4,750円は、本書提出日の前営業日である2021年9月30日の対象者株式の終値である4,540円に対して4.63%のプレミアムを加えた価格です。 なお、公開買付者は、上記の諸要素を総合的に考慮しつつ、対象者との協議・交渉を踏まえて本公開買付価格を決定したため、第三者算定機関からの株式価値算定書は取得しておりません。 |
| ② 新株予約権 本新株予約権については、本書提出日現在において、対象者株式1株当たりの行使価額(第10回新株予約権:1,177円、第11回新株予約権:1,177円、第12回新株予約権:2,694円、第13回新株予約権:2,710円、第14回新株予約権:1,212円、第15回新株予約権:771円、第16回新株予約権:2,290円及び第17回新株予約権:3,053円)が本公開買付価格(4,750円)を下回っております。そこで、公開買付者は、本新株予約権買付価格を、本公開買付価格である4,750円と各本新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額に当該本新株予約権の目的となる普通株式数(第10回新株予約権及び第11回新株予約権については200、第12回新株予約権ないし第17回新株予約権については100)を乗じた金額とすることを決定いたしました。具体的には、第10回新株予約権については対象者株式1株当たりの行使価額1,177円との差額である3,573円に200を乗じた金額である714,600円、第11回新株予約権については対象者株式1株当たりの行使価額1,177円との差額である3,573円に200を乗じた金額である714,600円、第12回新株予約権については対象者株式1株当たりの行使価額2,694円との差額である2,056円に100を乗じた金額である205,600円、第13回新株予約権については対象者株式1株当たりの行使価額2,710円との差額である2,040円に100を乗じた金額である204,000円、第14回新株予約権については対象者株式1株当たりの行使価額1,212円との差額である3,538円に100を乗じた金額である353,800円、第15回新株予約権については対象者株式1株当たりの行使価額771円との差額である3,979円に100を乗じた金額である397,900円、第16回新株予約権については対象者株式1株当たりの行使価額2,290円との差額である2,460円に100を乗じた金額である246,000円及び第17回新株予約権については対象者株式1株当たりの行使価額3,053円との差額である1,697円に100を乗じた金額である169,700円とそれぞれ決定いたしました。 なお、本新株予約権はいずれも、譲渡による取得について対象者取締役会の承認を要するものとされておりますが、対象者は、本新株予約権の譲渡が可能となるよう、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けの成立を条件として、本新株予約権者の皆様が、その所有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより公開買付者に対して譲渡することについて包括的に承認すること、及び譲渡を希望する本新株予約権者との間では新株予約権割当契約の内容を変更し譲渡可能な内容とする旨を決議したとのことです。 なお、公開買付者は、本新株予約権買付価格の決定に際し、本公開買付価格をもとに算定していることから、第三者算定機関からの算定書は取得しておりません。 | |
| 算定の経緯 | (本公開買付価格の決定に至る経緯) 上記「3 買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けを実施するに至った背景、目的並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの目的及び背景」に記載のとおり、公開買付者らは、公開買付者と対象者の市場における競争力強化及び両社の企業価値の向上を図る観点から、2021年6月18日付で対象者に対し公開買付者による対象者株式の公開買付け及びそれに引き続くスクイーズアウト手続きを通じて対象者の全株式を取得する旨の初期的な意向表明書を提出いたしました。 その後、公開買付者らは、2021年6月下旬から、対象者の事業・財務・税務・法務等に関するデュー・ディリジェンス(2021年8月中旬に終了しております。)や対象者の経営陣との面談等を実施いたしました。公開買付者らはその過程で取得した情報等を踏まえて、本取引の意義、買収ストラクチャー、本取引の実現可能性等について、さらなる分析及び検討を進めるとともに、対象者との間で本公開買付価格を含む本取引の諸条件について引き続き協議を行っておりました。その結果、2021年7月下旬に、公開買付者らは、対象者、対象者の親会社でありプラットフォームの提供を通じて対象者の事業運営上重要な役割を果たすヤフー、及び公開買付者の三者が保有する経営資源を対象者において共同活用し、互恵的にシナジーを享受するためには、公開買付者とヤフーを対象者の唯一の株主とし、さらにそれに引き続き公開買付者を対象者の唯一の株主とするための取引を実施することで、公開買付者と対象者が資本関係を共通にして両社が競争関係から脱却し、バックエンド業務に限らない分野も含めてより密接に連携することが不可欠であると認識するに至りました。 |
| そして、2021年8月上旬に、公開買付者らは、本三角株式交換後の本取引のスキームについては対象者の完全親会社であるZホールディングスとの間で継続協議することを前提として、対象者が所有する自己株式及び本不応募株式を除く対象者株式の全てについて、①本公開買付け及びその後の②本株式併合を通じて取得し、③本不応募株式については、本株式併合の効力発生後に公開買付者を株式交換完全親会社、対象者を株式交換完全子会社とし、WEBTOON Entertainment株式を対価とする三角株式交換を実施して取得する段階的買収スキームを対象者に提案することを決定いたしました。そして、2021年8月10日に、公開買付者らは、本特別委員会に対して、対象者株式については、2021年8月10日の過去1ヵ月間(2021年7月12日から2021年8月10日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である3,525円に対して13.48%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年5月11日から2021年8月10日まで)の終値単純平均値3,184円に対して25.63%、過去6ヵ月間(2021年2月12日から2021年8月10日まで)の終値単純平均値2,910円に対して37.46%のプレミアムをそれぞれ付した水準となる4,000円を本公開買付価格とする内容を含む提案を行いました。なお、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、同提案の中で本公開買付価格としていた4,000円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である2,589円に対して54.50%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して51.23%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して52.56%のプレミアムであることを考慮したものです。上記の公開買付価格提案において、公開買付者らは、対象者に対するデュー・ディリジェンス、対象者の財務状況及び対象者より2021年7月14日付で開示された事業計画を分析の上、過去における上場会社を完全子会社とすることを企図した類似取引におけるプレミアム水準、本公開買付けへの応募見込み、等を総合的に勘案いたしました。また、この提案の中では、公開買付者らは、対象者が発行していた本新株予約権について、本新株予約権は対象者の役職員に対するストック・オプションとして付与されたもので、権利行使の時点において、対象者又は対象者の関係会社の役職員の地位にあることが権利行使の条件とされているため、公開買付者が本新株予約権を取得したとしてもこれらを行使することができないことから、その全てを1個につき1円で買い取ることを提案しました。これに対し、本取引の交渉において対象者の窓口機能を担っていた本特別委員会は、公開買付者らの提案した普通株式1株当たりの公開買付価格である4,000円は公正な価格に達しておらず、対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないことに加え、対象者が発行している新株予約権を1円で買い取ることは、新株予約権者である従業員にとってモチベーションの低下に繋がり本取引実施後の経営にも影響を与える可能性があるため、行使条件を考慮してもなお受け入れられないとして、2021年8月13日付で公開買付者らに対し提案内容の再考を求める連絡を行いました。以降、公開買付者らと対象者は、公開買付価格について継続的に協議・交渉を行いました。 |
| そして、2021年9月3日に、公開買付者らは対象者に対して、対象者株式については、2021年9月3日の過去1ヵ月間(2021年8月4日から2021年9月3日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である3,736円に対して13.76%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年6月4日から2021年9月3日まで)の終値単純平均値3,479円に対して22.16%のプレミアム、過去6ヵ月間(2021年3月4日から2021年9月3日まで)の終値単純平均値3,077円に対して38.12%のプレミアムをそれぞれ付した水準となる4,250円を本公開買付価格とする内容を含む提案を再度行いました。なお、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、同提案の中で本公開買付価格としていた4,250円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である2,589円に対して64.16%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して60.68%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して62.09%のプレミアムであることを考慮したものです。また、公開買付者らはこの提案の中で、行使条件が付されているために公開買付者が買付けを行った後には行使不能となる本新株予約権につき、それらを実質的に行使可能とすることで新株予約権者の経済的利益を担保するため、その全てを1個につき対象者株式の公開買付価格と種類ごとの行使価格の差額に目的株式数を乗じた価格で買付けを行うことを提案いたしました。このように、公開買付者らは、2021年9月3日に公開買付者が行った価格提案に際して、公開買付者らによる対象者に対する評価を十分に価格に織り込みつつ、対象者の少数株主並びに新株予約権者が経済的に不利益を被らないように配慮を行いました。しかし、本特別委員会は公開買付価格の再考を要請し公開買付者らと対象者の間で本公開買付価格についての合意には至りませんでした。このように、対象者からは2021年9月3日に行った提案に対しての回答が得られなかったため、公開買付者らは、本特別委員会からの再考の要請を受けて、本公開買付価格についての合意を取得するべく、2021年9月上旬から中旬にかけて、本取引実施後に実現されるであろう公開買付者と対象者のより強固な業務上の協力関係の帰結について再度検討を行い、過去2回の提案における価格提示を再度見直しました。そして、2021年9月24日に、公開買付者らは対象者に対して、新株予約権の買付価格については2021年9月3日に公開買付者が前提とした全ての本新株予約権1個につき対象者株式の公開買付価格と種類ごとの行使価格の差額に目的株式数を乗じた価格とするという価格試算の考え方を変更しない一方で、対象者株式1株当たり4,750円を本公開買付価格とする内容を含む最終提案を行いました。本提案における対象者株式1株当たり4,750円は、2021年9月24日の過去1ヵ月間(2021年8月25日から2021年9月24日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である3,872円に対して22.68%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年6月25日から2021年9月24日まで)の終値単純平均値3,653円に対して30.03%のプレミアム、過去6ヵ月間(2021年3月25日から2021年9月24日まで)の終値単純平均値3,231円に対して47.01%のプレミアムをそれぞれ付した水準です。また、対象者が上記2021年6月1日付で公表した本業務提携に関するプレスリリースにおいて、バックエンド業務の共通化以外の協業についても今後協議を進めていく旨の記載を行っていたことから、同日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せていたとの理解のもと、同提案の中で本公開買付価格としていた4,750円は、本業務提携を公表した2021年6月1日を基準日とした過去1ヵ月間(2021年5月6日から2021年6月1日まで)の東京証券取引所市場第一部における対象者株式終値単純平均値である2,589円に対して83.47%のプレミアム、過去3ヵ月間(2021年3月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,645円に対して79.58%のプレミアム、過去6ヵ月間(2020年12月2日から2021年6月1日まで)の終値単純平均値2,622円に対して81.16%のプレミアムを考慮したものです。 |
| (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置) 本書提出日現在において、対象者は公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当いたしませんが、公開買付者は、本公開買付け後、本書提出日現在対象者株式2,443,600株(所有割合43.18%)を所有し対象者を連結子会社としているヤフーを株主として残して、本スクイーズアウトを実施することを予定していることから、対象者の少数株主と利害が一致しない可能性があることを踏まえ、公開買付者及び対象者は、対象者の少数株主の皆様への影響に配慮し、本公開買付価格の公正性を担保しつつ、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、以下のような措置を実施いたしました。 なお、以下の記載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。また、公開買付者は、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」の応募を本公開買付け成立の条件とはしておりませんが、上記「(1) 本公開買付けの概要」に記載のとおり、ヤフーは、本書提出日現在、対象者株式を2,443,600株(所有割合:43.18%)所有していることから、本公開買付けにおいて、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)」の買付予定数の下限を設定すると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本公開買付けに応募することを希望する一般株主の皆様の利益に資さない可能性もあるものと考えております。また、公開買付者及び対象者において以下①ないし⑤の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。 |
| ① 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、2021年6月9日、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、東京証券取引所に独立役員として届け出ている対象者の社外取締役及び社外監査役のうち、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立した、寺田航平氏(対象者独立社外取締役、寺田倉庫株式会社代表取締役社長)、小林雅人氏(対象者独立社外取締役、シティユーワ法律事務所パートナー)、高橋鉄氏(対象者独立社外監査役、ITN法律事務所代表パートナー)の3名から構成される本特別委員会を設置したとのことです。なお、本特別委員会の委員は設置当初から変更されていないとのことです。本特別委員会の委員長については、対象者取締役会の構成員として経営判断に直接関与する立場にあり、対象者の事業に相当程度の知見を有していること、また、本公開買付けを含む本取引を検討する見識・適格性を有すること等を踏まえ、委員の互選に基づき、寺田航平氏が就任しているとのことです。また、本特別委員会の委員の報酬については、取引の成否にかかわらず時間単位の報酬のみとされており、本取引の成立を条件とする成功報酬は含まれていないとのことです。対象者取締役会は、本特別委員会設置の決定に資し、本特別委員会に対し、(a)本公開買付けについて対象者取締役会が賛同するべきか否か、及び、対象者の株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨するべきか否かを検討し、対象者取締役会に勧告を行うこと、(b) 本非公開化取引についての対象者取締役会による決定((i)本公開買付けに賛同の意見を表明し、対象者の株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決定、及び、(ii)本公開買付け後に行われる株式の併合等による非公開化手続きに係る決定をいう。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでないかを検討し、対象者取締役会に意見を述べること(上記の勧告及び意見に際しては、①本非公開化取引の目的が正当性を有するか、②本非公開化取引に係る手続きの公正性が確保されているか、③本非公開化取引の取引条件の妥当性が担保されているかについて検討するものとする。また、本非公開化取引に関する交渉状況等に応じて、本特別委員会が必要又は適切と認める場合は、本特別委員会は、上記諮問事項を追加又は変更することができる。)を諮問し、これらの点についての答申書を対象者に提出することを委嘱したとのことです。また、対象者は、2021年6月9日付の上記取締役会において、(a) 取締役会における本取引に関する意思決定は、本公開買付けへの賛否及び応募推奨の有無を含め、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して行うこと、(b) 本特別委員会が本非公開化取引の取引条件が妥当でないと判断した場合、対象者取締役会は本取引の承認を行わないこととすることを併せて決議しているとのことです。さらに、対象者は、上記取締役会において、本特別委員会に対し、(a) 対象者が公開買付者らとの間で行う交渉の過程に実質的に関与すること(必要に応じて公開買付者らとの交渉方針に関して指示又は要請を行うこと、及び、自ら公開買付者らとの交渉を行うことを含みます。)、(b)本諮問事項に関する答申を行うに際し、必要に応じ、自らの財務もしくは法務等に関するアドバイザーを選任し(この場合の費用は対象者が負担する。)、又は、対象者の財務もしくは法務等に関するアドバイザーを指名しもしくは承認(事後承認を含みます。)すること、(c) 必要に応じ、対象者の役職員から本非公開化取引に関する検討及び判断に必要な情報を受領すること及び(d) その他本非公開化取引に関する検討及び判断に際して必要と本特別委員会が認める事項に関する権限を付与したとのことです。 本特別委員会は、2021年6月16日より2021年9月30日までの間に合計20回、合計約24時間開催され、本諮問事項についての協議及び検討が慎重に行われたとのことです。具体的には、本特別委員会は、対象者の第三者算定機関かつファイナンシャル・アドバイザーである大和証券及びリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所につき、いずれも独立性及び専門性に問題がないことから、それぞれ対象者のファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザーとして承認したとのことです。 |
| その後の具体的な審議状況として、本特別委員会は、①対象者に対して質問事項を提示し、対象者との間で、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等についてインタビュー形式により質疑応答を実施し、②別の会合において、NAVERに対して質問事項を提示し、同社との間で、本取引の目的及び背景、本取引後の経営方針等についてインタビュー形式により質疑応答を実施したとのことです。 また、本特別委員会は、対象者が作成した本事業計画について、対象者からその内容及び作成経緯等について説明を受けるとともに、これらの事項について合理性を確認しているとのことです。そして、大和証券からの、本事業計画を基礎として行った株式価値算定の内容、DCF法及びDCF法における割引率の計算根拠を含む重要な前提条件についての説明も踏まえて、質疑応答及び審議・検討を行った上で、これらの事項について合理性を確認しております。 さらに、本特別委員会は、対象者、大和証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、本取引の手続面における公正性を担保するための措置並びに本取引に係る対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の利益相反を回避するための措置の内容について説明を受け、本取引において手続きの公正性を確保するために講じるべき措置について審議・検討を行っているとのことです。 また、本特別委員会は、大和証券から受けた財務的見地からの助言を踏まえ、公開買付者からより高い価格を引き出すために、相互に独立した第三者間のM&Aで行われる一般的な交渉プロセスに即して十分な交渉を実施することを含む交渉方針について審議・検討するとともに、本特別委員会が公開買付者らから公開買付価格に関する提案を受領する都度、大和証券から受けた財務的見地からの助言も踏まえて公開買付者らに対する交渉方針を審議・検討した上で、公開買付者らと直接書面のやり取りを行うこと等により、公開買付者らとの間で公開買付価格に関する協議・交渉を行ったとのことです。 具体的には、2021年8月10日に公開買付者らより公開買付価格を1株当たり4,000円とすることを含む提案書を受領したのに対し、本特別委員会は、大和証券及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所から聴取した意見を踏まえて検討を行った上で、提案された公開買付価格は公正な価格に達しておらず、対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないとして、公開買付者らに対し公開買付価格の再検討を要請したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、公開買付価格を1株当たり4,250円とする提案を受領したとのことです。当該提案を受け、対象者は、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである大和証券を通じて、公開買付者らとの間で協議を継続いたしましたが、本特別委員会は、当該大和証券を通じた協議の内容並びに大和証券からの財務的見地からの助言及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的見地からの助言を踏まえ、NAVERに対し、上記の提案価格は、大和証券によりDCF法に基づき算定される株式価値の水準に照らし、引き続き対象者の少数株主の利益に十分に配慮できていないと考えていること等を理由として、再度公開買付価格の再考を依頼したとのことです。その後も公開買付者らとの間で、対象者のファイナンシャル・アドバイザーである大和証券を通じて、継続的に協議及び交渉を行い、その結果、本特別委員会は、2021年9月24日、公開買付者らから、本公開買付価格を4,750円とすることを含む最終提案を受けるに至ったとのことです。 |
| また、本特別委員会は、公開買付者らとの間で、本新株予約権買付価格についても、協議・交渉を行っているとのことです。具体的には、対象者は、公開買付者らより、上記の2021年8月10日付の提案書において、本新株予約権買付価格について、新株予約権1個につき1円とする提案を受けたとのことです。これに対し、本特別委員会は、2021年8月13日、公開買付者らに対し、当該新株予約権は、対象者役職員に対する報酬制度として付与しているものであり、特に、当該新株予約権の内、現時点では行使不可であるものの、保有者に多大な経済的価値が見込まれる新株予約権を適切な価格で買い取らないとすると、保有者である対象者従業員のモチベーションが大きく低下し、非公開化後の経営統合プロセスに支障をきたす事が想定されることから、権利行使をした場合に利益が出る状態にある新株予約権については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とするように再考を依頼したとのことです。その後、本特別委員会は、2021年9月3日、公開買付者より、NAVERを通じて、新株予約権に係る買付価格については、本公開買付価格と当該新株予約権に係る行使価格の差額とする旨の提案を受けるに至ったとのことです。 本特別委員会は、以上の経緯の下、大和証券株式価値算定書等も考慮し、本諮問事項について慎重に協議及び検討を重ねた結果、2021年9月30日付で、対象者取締役会に対し、委員全員の一致で、大要以下の内容の答申書を提出しているとのことです。 (ⅰ) 答申内容 a 対象者取締役会は、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨するべきであると考えられる。 b 対象者取締役会が、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を決定することは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられる。また、対象者取締役会が、本取引において予定されている方法によることを前提に、本公開買付け成立後の本株式併合による対象者の非公開化についての決定をすることは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられる。 (ⅱ) 答申理由 ⅰ 本取引が対象者の企業価値向上に資するものであり、その目的は正当なものであると認められるかについて ・世界的にみても市場規模が大きく、また、エンターテインメントサービスの源泉となる知的財産権が多く存在する日本の電子コミック市場は、多数の競合他社が存在する極めて競争環境の厳しい市場である。対象者は、かかる厳しい競争環境を勝ち抜き、電子コミック分野での国内取扱高No.1を獲得するためには、収益基盤と事業競争力の強化がその経営課題であると認識し、現在、Zホールディングスグループとのシナジー強化に取り組んでいる。もっとも、対象者によれば、競争の激しい国内電子コミック市場において、国内取扱高No.1という対象者の目標を達成するためには、(a)競合他社を上回る規模・効率での広告・販促活動や投資の継続、(b)対象者が競合他社と比較して補強が必要であると認識している領域(サービスに対する認知の向上、若年層利用者の取り込み、電子書籍アプリの強化、先行・独占・オリジナル等のコンテンツ強化等)への投資、(c)消費者ニーズの変化に対する迅速な対応(スマートフォンに特化した縦スクロールのカラーコンテンツの拡充、無料で読めるコンテンツの拡充等)及び(d)今後成長が見込まれるグローバル市場への積極的な展開といった各課題を解決していく必要があり、これらの各課題については、早期の解決を図っていくことが必要である一方で、現状のヤフー及びZホールディングスとの間の提携関係のみでは、その実現に相応の期間が必要となるものと考えており、外部企業との間の資本提携を含むパートナーシップの構築の必要性について検討を行っていたとのことである。 |
| ・公開買付者らの提案する、①公開買付者及び対象者の利用者の拡大、②人気IPの創出と獲得、③マーケティング戦略の統一と効率化、④サービス開発、インフラ基盤の安定と強化等の本取引によるシナジー及び本取引後の企業価値向上施策は、上記の対象者の経営課題の解決に資するものである。また、アプリを通じたコンテンツ配信に強みを持つ公開買付者とWEBを通じたコンテンツ配信に強みを持つ対象者が相互補完的に互いのプラットフォームを活用しつつ、より効率的に潜在的な顧客を獲得すると同時に、日本における優良マンガコンテンツの配信を行う対象者がコンテンツ配信を海外で展開する公開買付者らのグループに加入することで日本の優良マンガコンテンツのグローバルでの存在感の向上が可能であり、より広範な顧客層を対象として対象者のコンテンツ配信が可能になるという公開買付者らの説明は合理的であり、対象者にとって、本取引は、国内市場における競争力強化のみならず、グローバル市場への展開にも資するものと評価し得る。 ・本取引後の各施策については、対象者は既に公開買付者との間でバックエンド業務に関する業務提携を実施しており、現在の資本構成の下でも実施可能なのではないかとの点が問題となり得るが、対象者によれば、公開買付者との間には資本関係はなく独立した当事者間の協業であることや上場を維持することにより一般株主の利益に配慮する必要性があること等から、当該業務提携に関しては、経営資源・人材の相互活用や意思決定のスピードなどにおいて、中長期的な成長を実現する上で一定の限界があると認識していたとのことである。本取引を実施して対象者が公開買付者の完全子会社となり、バックエンド業務に限らない分野も含めて両社がより密接に連携することで、上記のような厳しい市場環境において、対象者の収益基盤と事業競争力の強化に繋がり、スピード感をもって中長期的にも両社の成長戦略及び企業価値向上策を一体的に実現していくことが可能になるとのことである。 | |
| ・公開買付者らの提案に対し、対象者の経営陣からは、①本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、意思決定の迅速化や公開買付者と対象者間での人員交流等が促進され、バックエンド業務の共通化に向けた連携がより強固なものとなり、取扱規模の拡大及び出版社窓口の一本化の結果、事業効率の改善及び出版社への営業力の強化、並びにコンテンツ力の向上を着実に図ることができること、②公開買付者が運営する「LINEマンガ」のオリジナル作品を「ebookjapan」でも販売可能とすることにより、ユーザーの獲得及び収益の拡大に繋がること、③アプリで多くの利用者を獲得し、利用者層においても比較的若年層が多い「LINEマンガ」と、WEBブラウザで多くの利用者を獲得し、中高年層を含めた幅広い利用者を持つ「ebookjapan」は利用者層が異なり、相互に補完し合う関係にあるところ、今後両社が持つマーケティングソリューションを最大限活用し、統一されたブランドマーケティングを行うことで、WEBブラウザ、アプリの両方に強みを持ち、若年層から中高年層まで幅広い年齢層の利用者に支持される国内随一の電子書籍サービスグループとなることが可能となること等から、本取引を実施して公開買付者の完全子会社となることにより、公開買付者との間で電子書籍事業の幅広い分野において互いの強みを活かし、さらなる連携強化を図ることは、対象者の中長期的な企業価値の向上に資するものと考えているとの見解が示された。 ・公開買付者らによれば、対象者及び公開買付者らの間でのシナジーを最大限発揮していく観点からは、対象者と密接な競業関係にあるヤフー及びその親会社であるZホールディングスとこれまで以上に緊密に連携していくことが不可欠であり、本取引後もヤフー及びZホールディングスと対象者の既存の協業関係は維持・継続する方針とのことである。 |
| ・対象者の親会社であるヤフーは本公開買付けに応募しないことが予定されているが、公開買付者らによれば、その目的は、本取引後もWEBTOON Entertainmentへの出資を間接的に継続し、本取引の実行により対象者に生まれるシナジーの一部を享受することができるZホールディングスグループと、本取引により対象者の株主ではなくなる一般株主との間で同一の価格で対象者株式を評価することは一般株主に不利益をもたらすとの考えから、ヤフーが所有する対象者株式を本公開買付価格より低い価格で評価するため、公開買付者がまず対象者が所有する自己株式及びヤフーの所有する株式を除く対象者株式の全てを本公開買付け及び株式併合により取得し、その後ヤフーが所有する対象者株式を本三角株式交換により取得するスキームを採用することとしたものであり、かかる説明に特段不合理な点は認められない。 ・対象者は、本取引によって対象者は非公開化されることとなるが、韓国最大のインターネット・サービス企業である公開買付者らのグループの一員として十分な社会的信用力、知名度を維持するものであるから、資本市場からのエクイティによる資金調達の容易性が失われることによる影響や優れた人材の確保及び取引先の拡大等に与える影響は限定的であり、対象者の企業価値を毀損するものではないと考えられる。 ⅱ 本取引に係る手続きの公正性は確保されていると認められるかについて ・本取引においては、公開買付者、対象者、NAVER、ヤフー及びZホールディングスから独立した本特別委員会が、本取引に係る取引条件等の形成過程の初期段階から設置され、アドバイザー等の選任・承認権限や本取引の取引条件等の交渉過程に実質的に関与する権限が付与された上、本特別委員会の答申内容を最大限尊重して本取引に係る意思決定を行うものと決議されているところ、本特別委員会はこれらの権限を行使して、直接の交渉主体として、公開買付者との間の取引条件に関する交渉を行った。 ・本特別委員会及び対象者は、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、各種のアドバイスを受けている。 ・特別委員会及び対象者は、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したファイナンシャル・アドバイザーである大和証券に対して、対象者の株式価値の算定を依頼し、2021年9月29日付で大和証券株式価値算定書を取得している。 ・対象者においては、利害関係を有する取締役等を本取引の検討・交渉過程から除外し、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立した立場で検討・交渉等を行うことができる体制が構築されていたものと認められる。 ・本公開買付けにおいては、いわゆる間接的なマーケット・チェックが行われているものと認められる。 ・本公開買付けにおいては、公開買付期間が法令に定められた最短期間である20営業日を超える31営業日に設定されている。 ・本公開買付けにおいては、一般株主による十分な情報に基づく適切な判断の機会が確保される予定であると認められる。 ・本取引においては、本公開買付けの決済完了後、公開買付者は速やかに本株式併合にかかる臨時株主総会の開催を対象者に要請し、また、本株式併合に際して株主に交付される予定の金銭の額を本公開買付価格と同額に設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定であることから、強圧性が排除されているものと認められる。 |
| ・本公開買付けにおいては、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)条件が設定されていないものの、本公開買付けが成立した場合に公開買付者及びヤフーが対象者の議決権数の3分の2以上を所有することとなるようにするため、1,328,800株(所有割合:23.48%)が買付予定数の下限として設定される予定である。かかる下限は、相当程度の一般株主の応募がなければ本公開買付けが成立しないという意味において、一定程度の公正性担保措置として機能すると考えられ、また、本取引においては、他に十分な公正性担保措置が講じられていることからすれば、マジョリティ・オブ・マイノリティ(Majority of Minority)が設定されていないとしても、それのみにより本取引における手続きの公正性が損なわれるものではないと考えられる。 ⅲ 一般株主の利益を図る観点から、取引条件の妥当性は確保されていると認められるかについて ・本取引の買収の方法について、一段階目として本公開買付けを行い、二段階目として本株式併合を行う方法は、本取引のような非公開化の取引においては一般的に採用されている方法である。 ・本取引の取引条件に係る協議・交渉過程においては、公開買付者らによる最終意向表明書の提出後も、本特別委員会の要請に基づき、これ以上の価格交渉が困難であると判断されるまで協議・交渉を繰り返し、結果として公開買付者らから有意な譲歩(当初の4,000円から750円(18.7%)増額された4,750円という提案)を引き出した本公開買付価格が提案されている等、本特別委員会の実質的な関与のもと、企業価値を高めつつ少数株主にとってできる限り有利な取引条件で本取引が行われることを目指した合理的な努力が行われる状況が確保されていたものと認められる。 ・大和証券株式価値算定書におけるDCF法に基づく算定の基礎とされている対象者の事業計画の策定目的、策定手続及び内容につき特に不合理な点はないと認められる。対象者によれば、本業務提携の具体的な業務は開始していないため、その影響については引き続き精査中であること、また、本取引が実施されないとの前提を置く場合、本業務提携が解消される可能性もあることから、本業務提携が対象者の業績に与える影響については、本事業計画には織り込まれていないとのことであるが、本取引が実施されないとの前提を置く場合に本業務提携の具体的な業務の開始が解消される可能性があるとの対象者の説明に不合理な点はなく、リーガル・アドバイザー、ファイナンシャル・アドバイザーの助言も経た上で、対象者のスタンドアロンベースの事業計画において本業務提携の影響が織り込まれていないことに不合理な点はないと認められる。 ・大和証券株式価値算定書の内容は、算定の方法及び内容のいずれにおいても不合理な点は認められず、信用できるものと判断するところ、本公開買付価格は、大和証券株式価値算定書の市場株価平均法に基づく算定結果の上限を上回り、DCF法に基づく評価レンジの範囲内にあり、かつ中央値(DCF法による算定の基礎となる割引率及び永久成長率について、その感応度分析において用いた数値の中央値を使用して算出された対象者株式の1株当たりの株式価値)の4,788円と遜色ない価格であると認められる。 |
| ・本公開買付価格は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日(なお、対象者は、公開買付者らから、2021年6月1日以降の対象者の株価は、本業務提携によるシナジー以外にも、本取引によらなければ実現できないシナジーが本業務提携に引き続いて実現する可能性があるとの期待を先取りして上昇を見せているとの説明を受けていたが、対象者としては、当該可能性を合理的に検証することができないことから、他の同種の案件において一般的である、公表日の前営業日を基準とした一定期間の株価のプレミアムを考慮している。)である2021年9月29日の直近1ヵ月間の終値単純平均値4,000円に対して18.75%のプレミアムを加えた価格、直近3ヵ月間の終値単純平均値3,697円に対して28.48%のプレミアムを加えた価格、直近6ヵ月間の終値単純平均値3,274円に対して45.08%のプレミアムを加えた価格であり、このうち、直近1ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアム率を取り上げると、直近約2年間(2019年8月以降)に公表された公開買付けを利用した支配株主による完全子会社化事例におけるプレミアム水準(中央値が36%程度から41%程度)に照らして、必ずしも高い水準であるとは言い難いものの、直近3ヵ月間の終値単純平均値及び直近6ヵ月間の終値単純平均値に対するプレミアムに鑑みれば、本公開買付価格は相応のプレミアムが付された価格であると評価できると考えられる。他方で、本公開買付価格は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値4,510円に対して5.32%のプレミアムを加えた価格であり、当該プレミアムについては、非公開化を目的とした他の公開買付けの事例におけるプレミアム水準との比較においてプレミアムが低水準であると考えられるものの、2021年9月27日以降、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2021年9月29日までの3日間において対象者株式の株価が急激に変動していること、及び、本公開買付価格は、対象者が2011年10月に東京証券取引所マザーズ市場にその株式を上場して以来の市場株価の最高値を超える水準であることを勘案すると、公表日の前営業日における対象者株式の終値に対するプレミアムが低水準であることをもって、本公開買付価格の合理性が欠けることになるものではないと認められる。 ・本新株予約権買付価格は、それぞれ、本公開買付価格と行使価格の差額に目的株式数を乗じた額とされており、本公開買付価格と同等の水準にあると認められる。 |
| ・(a)本三角株式交換における株式交換比率は、①ヤフーの所有する対象者株式の1株当たり価値を、本公開買付け価格において公開買付者が市場価格に対して反映するプレミアムを考慮せず、3,529円(本公開買付価格の最終提案日である2021年9月24日までの過去1ヵ月間(2021年8月25日から2021年9月24日まで)における対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値単純平均値に対して公開買付者ら及びZホールディングス間で協議して定めた一定のディスカウントを行った価格とすること、②本三角株式交換の対価として交付されるWEBTOON Entertainment株式の1株当たり価値を、NAVERが行うWEBTOON Entertainmentへの出資における1株当たり払込価格と同額として定めること、並びに、(b)本三角株式交換の効力発生後にNAVERが所有するWEBTOON Entertainment株式及び議決権と、Zホールディングスグループが所有するWEBTOON Entertainment株式及び議決権の比率が、本公開買付け公表日における当該比率である66.6%:33.4%と等しくなるように調整し、もって本取引を通じたNAVER及びZホールディングスグループによるWEBTOON Entertainment株式の取得が出資比率に応じた比例的なものとなることが予定されており、それにより、NAVER及びZホールディングスグループの間で利益移転が生じないように配慮されており、本三角株式交換が対象者の一般株主に比して有利なものとならないことが確保されるものと評価できる。 ・本公開買付価格、本新株予約権買付価格及び本三角株式交換における株式交換比率以外の本取引の取引条件に関しても、対象者の一般株主の犠牲のもとに、公開買付者ら及びZホールディングスグループが不当に利益を得るものと認めるべき事由は確認されておらず、本取引の取引条件の妥当性を害する事情は見当たらない。 ・以上のとおり、対象者の一般株主の利益を図る観点から、本取引の取引条件の妥当性は確保されていると考えられる。 ⅳ 対象者取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行うことの是非について ・上記ⅰのとおり、本取引は対象者の企業価値向上に資するものと認められ、本取引の目的は正当なものと考えられるため、対象者取締役会は、本公開買付けについて賛同すべきであると考えられる。 ・また、上記ⅱのとおり、本取引においては、一般株主利益を確保するための公正な手続きが実施されており、上記ⅲのとおり、本取引の取引条件の妥当性は確保されていると考えられるため、対象者取締役会は、本公開買付けへの応募を推奨すべきであると考えられる。 |
| ⅴ 上記ⅰからⅳを踏まえて、本取引が対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考えられるかについて ・上記ⅰからⅳを踏まえれば、本公開買付けについて賛同するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を決定することは、対象者の少数株主にとって不利益ではないと考えられ、また、対象者取締役会が、本取引において予定されている方法によることを前提に、本公開買付け成立後の本株式併合についての決定をすることは、対象者の一般株主にとって不利益はないと考えられる。 ② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書・意見書の取得 (ⅰ) 対象者株式に係る算定の概要 対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者から提示された本公開買付価格を検討し、本公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨を行うにあたり、公正性を担保するための措置として、対象者、ヤフー及び公開買付者から独立した第三者算定機関である大和証券に対して、対象者株式の株式価値算定を依頼し、大和証券から2021年9月29日付で大和証券株式価値算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、大和証券から本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。 大和証券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者株式が東京証券取引所市場第一部に上場していることから市場株価平均法を、対象者業績の内容や予想等を評価に反映するためにDCF法を用いて対象者株式の株式価値の算定を行い、対象者は大和証券から2021年9月29日付で、大和証券株式価値算定書を取得しているとのことです。 大和証券によれば、対象者株式の株式価値算定にあたり、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。 市場株価平均法 3,274円から4,510円 DCF法 4,043円から5,814円 市場株価平均法では、2021年9月29日を算定基準日として、対象者株式の東京証券取引所市場第一部における基準日終値4,510円、直近1ヵ月間の終値単純平均値4,000円、直近3ヵ月間の終値単純平均値3.697円及び直近6ヵ月間の終値単純平均値3,274円をもとに、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲は、3,274円から4,510円までと算定しているとのことです。 DCF法では、対象者が作成した本事業計画に基づく収益予測や投資計画等、合理的と考えられる前提を考慮した上で、対象者が2022年3月期第2四半期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を分析し、1株当たりの株式価値の範囲は、4,043円から5,814円までと算定しているとのことです。なお、割引率は9.1%~11.1%を採用しており、継続価値の算定については永久成長法を採用し、永久成長率を0.0%~1.0%として算定しているとのことです。 |
| 大和証券がDCF法において前提とした本事業計画に基づく財務予測は以下のとおりとのことです。なお、本事業計画には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2022年3月期から2027年3月期にかけて、電子書籍事業の市場拡大を背景とした電子書籍サービス「ebookjapan」の取扱高拡大により、継続的な増益を見込んでいるとのことです。2022年3月期から2024年3月期にかけては、グループシナジーのさらなる深化や広告宣伝を中心とした積極的なマーケティング投資によるユーザー獲得拡大を想定しており、アプリ及びウェブサイトの機能改善、オリジナル作品のラインアップ拡大等も相まって、継続的な取扱高の拡大を見込んでいるとのことです。その結果としての限界利益の増加、及び事業規模拡大に伴う固定費負担の軽減を踏まえ、2022年3月期及び2024年3月期は、大幅な増益を見込んでいるとのことです。その後、2025年3月期においては、ユーザー獲得のためのマーケティング投資が一巡する事に伴い売上高広告宣伝費率を抑制することで、大幅な増益を見込んでいるとのことです。また、本取引実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、本事業計画には加味していないとのことです。なお、本業務提携が業績に与える影響については、本業務提携に基づく取り組みの範囲、時期等について当事者間で協議中であり、その影響についても引き続き精査中であること、また、本取引が実施されないとの前提を置く場合には、本業務提携が解消される可能性もあることから、本事業計画には織り込んでおりません。 (単位:百万円)
(ⅱ) 本新株予約権に係る算定の概要 本新株予約権買付価格に関しては、本公開買付価格と各本新株予約権の対象者株式1株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権1個の目的となる対象者株式数(第10回新株予約権及び第11回新株予約権については200、第12回新株予約権ないし第17回新株予約権については100)を乗じた金額をもとに算定されているものであるため、本公開買付けは、対象者の本新株予約権者の皆様に対して合理的な本新株予約権の売却の機会を提供するものであると判断しているとのことです。 なお、本新株予約権はいずれも、譲渡による取得については対象者取締役会の承認を要するものとされておりますが、対象者は、本新株予約権の譲渡が可能となるよう、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けの成立を条件として、本新株予約権者の皆様が、その所有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより公開買付者に対して譲渡することについて包括的に承認すること、及び譲渡を希望する本新株予約権者との間では新株予約権割当契約の内容を変更し譲渡可能な内容とする旨を決議しているとのことです。 |
| ③ 対象者における独立した法律事務所からの助言 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に関する対象者取締役会の意思決定過程における透明性及び合理性を確保するため、2021年6月上旬、対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けにおける意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けにおける意思決定にあたっての留意点について、必要な法的助言を受けているとのことです。また、アンダーソン・毛利・友常法律事務所は対象者、NAVER、Zホールディングス、ヤフー、及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。 ④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見 対象者プレスリリースによれば、対象者は、大和証券から取得した大和証券株式価値算定書、本特別委員会から提出された答申書、アンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的助言その他の関連資料を踏まえ、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件について、慎重に協議及び検討を行ったとのことです。 その結果、対象者は、2021年9月30日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。 当該取締役会においては、対象者の取締役のうち、津留崎耕平氏及び秀誠氏は、ヤフーの執行役員兼任者であること、高橋将峰氏は、ヤフーの出身者(2019年4月付で対象者に転籍)であることから、利益相反のおそれを回避し、本取引の公正性を担保する観点から、(ア)まず対象者の取締役5名のうち、津留崎耕平氏、秀誠氏及び高橋将峰氏を除く、2名の取締役において審議の上、その全員一致により上記の決議を行い、さらに、対象者取締役会の定足数を確保する観点から、(イ)高橋将峰氏を加えた3名の取締役において改めて審議の上、その全員一致で再度上記の決議を行うという二段階の決議を経ているとのことです。また、上記の取締役会に出席した監査役(監査役3名中、出席監査役2名(うち社外監査役2名))の全員が上記決議につき異議はない旨の意見を述べているとのことです。 なお、対象者の取締役のうち、津留崎耕平氏及び秀誠氏の2名は、本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題による影響を受けるおそれを排除する観点から、上記2021年9月30日開催の対象者取締役会を含む本取引に係る対象者取締役会の審議及び決議には参加しておらず、かつ、対象者の立場において、本取引に係る検討並びに公開買付者との協議及び交渉に参加していないとのことです。 また、高橋将峰氏は、取締役会の定足数を確保する観点から上記取締役会の二段階目の審議及び決議に参加したものの、ヤフーの出身者であることから、利益相反のおそれを回避し、本取引の公正性を担保する観点から、対象者の立場において本取引に関する検討並びに公開買付者との協議及び交渉には参加していないとのことです。 また、対象者の監査役である鬼塚ひろみ氏はヤフーの監査役を兼務していることから、上記の取締役会の審議には一切参加しておらず、上記の取締役会の決議に対して意見を述べることを差し控えているとのことです。 ⑤ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置 公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、比較的長期間である31営業日としております。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主及び新株予約権者の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、本公開買付価格の適正性も担保することを企図しております。さらに、公開買付者と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定と合わせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保にも配慮しております。 |
買付予定の株券等の数
| 株券等の種類 | 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
| 普通株式 | 3,354,482(株) | 1,328,800(株) | ―(株) |
| 合計 | 3,354,482(株) | 1,328,800(株) | ―(株) |
(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,328,800株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注2) 単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
(注4) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりません。そのため買付予定数は、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数(3,354,482株)を記載しております。当該最大数は、対象者第1四半期決算短信に記載された2021年6月30日現在の発行済株式総数(5,712,700株)に、同日以降本書提出日までに行使された第10回新株予約権(7個)、第12回新株予約権(10個)の目的となる対象者株式数(2,400株)を加え、本新株予約権の目的となる対象者株式の数の合計(163,500株)を加算した株式数(5,878,600株)から、対象者が所有する自己株式数(80,518株)及び本不応募株式(2,443,600株)を控除した株式数(3,354,482株)になります。
(注5) 公開買付期間末日までに新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象とします。
買付け等を行った後における株券等所有割合
| 区分 | 議決権の数 |
| 買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) | 33,544 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | 1,635 |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | ― |
| 公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2021年10月1日現在)(個)(d) | ― |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | ― |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | ― |
| 特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2021年10月1日現在)(個)(g) | 24,436 |
| gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) | ― |
| hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i) | ― |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2021年3月31日現在)(個)(j) | 56,280 |
| 買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 (a/j) (%) | 57.85 |
| 買付け等を行った後における株券等所有割合 ((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100) (%) | 100.00 |
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本新株予約権の目的となる対象者株式の数の合計(163,500株)に係る議決権の数を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2021年10月1日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注4) 「対象者の総株主等の議決権の数(2021年3月31日現在)(個)(j)」は、対象者が2021年8月11日に提出した第22期第1四半期報告書に記載された2021年3月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び本新株予約権についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第1四半期決算短信に記載された2021年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(5,712,700株)に、同日以降本書提出日までに行使された新株予約権(対象者によれば第10回新株予約権(7個)及び第12回新株予約権(10個))の目的となる対象者株式数(2,400株)を加え、2021年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(80,518株)を控除した株式数(5,632,182株)に、本書提出日現在の本新株予約権(1,597個)の目的となる対象者株式数(163,500株)を加えた株式数(5,798,082株)に係る議決権の数(57,980個)を分母として計算しております。
(注5) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本新株予約権の目的となる対象者株式の数の合計(163,500株)に係る議決権の数を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2021年10月1日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注4) 「対象者の総株主等の議決権の数(2021年3月31日現在)(個)(j)」は、対象者が2021年8月11日に提出した第22期第1四半期報告書に記載された2021年3月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び本新株予約権についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第1四半期決算短信に記載された2021年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(5,712,700株)に、同日以降本書提出日までに行使された新株予約権(対象者によれば第10回新株予約権(7個)及び第12回新株予約権(10個))の目的となる対象者株式数(2,400株)を加え、2021年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(80,518株)を控除した株式数(5,632,182株)に、本書提出日現在の本新株予約権(1,597個)の目的となる対象者株式数(163,500株)を加えた株式数(5,798,082株)に係る議決権の数(57,980個)を分母として計算しております。
(注5) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本新株予約権の目的となる対象者株式の数の合計(163,500株)に係る議決権の数を記載しております。
(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2021年10月1日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注4) 「対象者の総株主等の議決権の数(2021年3月31日現在)(個)(j)」は、対象者が2021年8月11日に提出した第22期第1四半期報告書に記載された2021年3月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び本新株予約権についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第1四半期決算短信に記載された2021年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(5,712,700株)に、同日以降本書提出日までに行使された新株予約権(対象者によれば第10回新株予約権(7個)及び第12回新株予約権(10個))の目的となる対象者株式数(2,400株)を加え、2021年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(80,518株)を控除した株式数(5,632,182株)に、本書提出日現在の本新株予約権(1,597個)の目的となる対象者株式数(163,500株)を加えた株式数(5,798,082株)に係る議決権の数(57,980個)を分母として計算しております。
(注5) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
株券等の種類
普通株式
根拠法令
① 外国為替及び外国貿易法
公開買付者は、本公開買付けによる対象者株式の取得について、2021年9月10日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月13日受理されております。当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月28日より公開買付者による対象者株式の取得が可能となっております。
次に、本公開買付けによる対象者株券等の取得自体が制限されるものではありませんが、WEBTOON Entertainmentは、本出資の際のWEBTOON Entertainmentによる公開買付者株式の取得について、2021年9月10日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月13日受理されております。当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月28日よりWEBTOON Entertainmentによる公開買付者株式の取得が可能となっております。
さらに、本公開買付けによる対象者株券等の取得自体が制限されるものではありませんが、NAVER WEBTOONは、本出資の際のNAVER WEBTOONによる公開買付者株式の取得について、2021年9月16日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月21日受理されております。当該届出の受理後、NAVER WEBTOONが公開買付者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月30日よりNAVER WEBTOONによる公開買付者株式の取得が可能となっております。
加えて、本公開買付けによる対象者株券等の取得自体が制限されるものではありませんが、公開買付者は、本公開買付けの成立後に本株式併合を実施することによって対象者株式に生じる1株に満たない端数について、会社法第235条その他の関係法令の定める手続きに従い、当該端数の合計数に相当する対象者株式を公開買付者が取得する際の、公開買付者による対象者株式の取得について、2021年9月10日付で、外為法第27条第1項及び第28条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月13日受理されております(本①冒頭の本公開買付けによる対象者株式の取得にかかる届出が、上記の外為法第27条第1項に基づく届出を兼ねております。)。当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月28日より公開買付者による対象者株式の取得が可能となっております。
このほか、本公開買付けによる対象者株券等の取得自体が制限されるものではありませんが、公開買付者は、本公開買付けの成立後に本三角株式交換を実施することにより公開買付者が対象者株式を公開買付者が取得することについて、2021年9月10日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月13日受理されております(本①冒頭の本公開買付けによる対象者株式の取得にかかる届出が、上記の届出を兼ねております。)。当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月28日より公開買付者による対象者株式の取得が可能となっております。
② 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取得(以下「本株式取得」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により事前届出が受理された日から30日(短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令を発令しようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、かかる意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2021年9月29日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されております。その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2021年10月6日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」を2021年10月8日付で受領したため、2021年10月6日をもって措置期間は終了しております。また、公開買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日から7日間に短縮する旨の2021年10月6日付「禁止期間の短縮の通知書」を2021年10月8日付で受領したため、2021年10月6日の経過をもって取得禁止期間は終了しております。
公開買付者は、本公開買付けによる対象者株式の取得について、2021年9月10日付で、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月13日受理されております。当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月28日より公開買付者による対象者株式の取得が可能となっております。
次に、本公開買付けによる対象者株券等の取得自体が制限されるものではありませんが、WEBTOON Entertainmentは、本出資の際のWEBTOON Entertainmentによる公開買付者株式の取得について、2021年9月10日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月13日受理されております。当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月28日よりWEBTOON Entertainmentによる公開買付者株式の取得が可能となっております。
さらに、本公開買付けによる対象者株券等の取得自体が制限されるものではありませんが、NAVER WEBTOONは、本出資の際のNAVER WEBTOONによる公開買付者株式の取得について、2021年9月16日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月21日受理されております。当該届出の受理後、NAVER WEBTOONが公開買付者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月30日よりNAVER WEBTOONによる公開買付者株式の取得が可能となっております。
加えて、本公開買付けによる対象者株券等の取得自体が制限されるものではありませんが、公開買付者は、本公開買付けの成立後に本株式併合を実施することによって対象者株式に生じる1株に満たない端数について、会社法第235条その他の関係法令の定める手続きに従い、当該端数の合計数に相当する対象者株式を公開買付者が取得する際の、公開買付者による対象者株式の取得について、2021年9月10日付で、外為法第27条第1項及び第28条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月13日受理されております(本①冒頭の本公開買付けによる対象者株式の取得にかかる届出が、上記の外為法第27条第1項に基づく届出を兼ねております。)。当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月28日より公開買付者による対象者株式の取得が可能となっております。
このほか、本公開買付けによる対象者株券等の取得自体が制限されるものではありませんが、公開買付者は、本公開買付けの成立後に本三角株式交換を実施することにより公開買付者が対象者株式を公開買付者が取得することについて、2021年9月10日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月13日受理されております(本①冒頭の本公開買付けによる対象者株式の取得にかかる届出が、上記の届出を兼ねております。)。当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、当該待機期間は短縮され、2021年9月28日より公開買付者による対象者株式の取得が可能となっております。
② 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取得(以下「本株式取得」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により事前届出が受理された日から30日(短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令を発令しようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、かかる意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含みます。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2021年9月29日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理されております。その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2021年10月6日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」を2021年10月8日付で受領したため、2021年10月6日をもって措置期間は終了しております。また、公開買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日から7日間に短縮する旨の2021年10月6日付「禁止期間の短縮の通知書」を2021年10月8日付で受領したため、2021年10月6日の経過をもって取得禁止期間は終了しております。
許可等の日付及び番号
(3) 【許可等の日付及び番号】
| 国又は地域名 | 許可等をした機関の名称 | 許可等の日付 | 許可等の番号 |
| 日本 | 財務大臣及び事業所轄大臣 | 2021年9月27日 | JD第697号 |
| 2021年9月27日 | JD第698号 | ||
| 2021年9月27日 | JD第699号 | ||
| 2021年9月29日 | JD第733号 | ||
| 日本 | 公正取引委員会 | 2021年10月6日 (排除措置命令を行わない旨の通知及び禁止期間短縮の通知を受けたことによる) | 公経企第773号 (「排除措置命令を行わない旨の通知書」の番号) 公経企第774号 (「禁止期間の短縮の通知書」の番号) |
応募の方法
① 公開買付代理人
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1)
オンラインサービス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)による応募に関しては、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)にて公開買付期間末日の15時30分までに手続きを行ってください。なお、オンラインサービスによる応募には、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)におけるオンラインサービスのご利用申込みが必要です。(注2)
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。
③ 株式の応募の受付にあたっては、応募株主等口座に、応募する予定の株式が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続きを完了していただく必要があります。
④ 本新株予約権には譲渡制限が付されておりますので、新株予約権の応募にあたっては、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「新株予約権譲渡承認請求書 兼 新株予約権名義書換請求書等」を「公開買付応募申込書」とともにご提出ください。また、新株予約権者であることの確認書類として、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「新株予約権原簿記載事項証明書 兼 新株予約権譲渡承認通知書」をご提出ください。なお、オンラインサービスにおいては、新株予約権の応募の受付は行いません。
⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑥ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。オンラインサービスにおいては、外国の居住者は応募できません。
⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
⑧ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
・ 個人の場合
マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類
マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1] マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2] 本人確認書類が必要です。
[1] マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。
[2] 本人確認書類
[A] 顔写真付の本人確認書類
・ 有効期間内の原本のコピーの提出が必要
旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
[B] 顔写真のない本人確認書類
・ 発行から6ヵ月以内の原本又はコピーの提出が必要
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書
・ 有効期間内の原本のコピーの提出が必要
健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)
※ 本人確認書類(原本・コピー)は、以下2点を確認できる必要があります。
① 本人確認書類そのものの有効期限
② 申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※ 野村證券株式会社の店舗でお手続きをされる場合は、原本をご提示いただき、その場での確認とさせていただきます。
※ コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。
※ 野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
※ 新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。
・ 法人の場合
登記事項証明書、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要になります。
※ 本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
※ 法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。
・ 外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。
(注2) オンラインサービスのご利用には、お申込みが必要です。オンラインサービスをお申込み後、パスワードがご登録住所に到着するまで約1週間かかりますのでお早めにお手続きください。公開買付期間末日近くである場合は、お取引店からの応募申込みの方がお手続きに時間を要しません。
・ 個人の場合:オンラインサービスのログイン画面より新規申込を受付しております。もしくは、お取引店又はオンラインサービスサポートダイヤルまでご連絡ください。
・ 法人の場合:お取引店までご連絡ください。なお、法人の場合は代理人等のご登録がない法人に限りオンラインサービスによる応募が可能です。
(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1)
オンラインサービス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)による応募に関しては、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)にて公開買付期間末日の15時30分までに手続きを行ってください。なお、オンラインサービスによる応募には、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)におけるオンラインサービスのご利用申込みが必要です。(注2)
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。
③ 株式の応募の受付にあたっては、応募株主等口座に、応募する予定の株式が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続きを完了していただく必要があります。
④ 本新株予約権には譲渡制限が付されておりますので、新株予約権の応募にあたっては、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「新株予約権譲渡承認請求書 兼 新株予約権名義書換請求書等」を「公開買付応募申込書」とともにご提出ください。また、新株予約権者であることの確認書類として、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「新株予約権原簿記載事項証明書 兼 新株予約権譲渡承認通知書」をご提出ください。なお、オンラインサービスにおいては、新株予約権の応募の受付は行いません。
⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑥ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。オンラインサービスにおいては、外国の居住者は応募できません。
⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
⑧ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
・ 個人の場合
マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類
マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1] マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2] 本人確認書類が必要です。
[1] マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。
[2] 本人確認書類
| マイナンバー(個人番号)を 確認するための書類 | 必要な本人確認書類 |
| 個人番号カード | 不要 |
| 通知カード | [A]のいずれか1点、 又は[B]のうち2点 |
| マイナンバー(個人番号)の記載された 住民票の写し | [A]又は[B]のうち、 「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点 |
| マイナンバー(個人番号)の記載された 住民票記載事項証明書 |
[A] 顔写真付の本人確認書類
・ 有効期間内の原本のコピーの提出が必要
旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
[B] 顔写真のない本人確認書類
・ 発行から6ヵ月以内の原本又はコピーの提出が必要
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書
・ 有効期間内の原本のコピーの提出が必要
健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)
※ 本人確認書類(原本・コピー)は、以下2点を確認できる必要があります。
① 本人確認書類そのものの有効期限
② 申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※ 野村證券株式会社の店舗でお手続きをされる場合は、原本をご提示いただき、その場での確認とさせていただきます。
※ コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。
※ 野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
※ 新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。
・ 法人の場合
登記事項証明書、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要になります。
※ 本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
※ 法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。
・ 外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。
(注2) オンラインサービスのご利用には、お申込みが必要です。オンラインサービスをお申込み後、パスワードがご登録住所に到着するまで約1週間かかりますのでお早めにお手続きください。公開買付期間末日近くである場合は、お取引店からの応募申込みの方がお手続きに時間を要しません。
・ 個人の場合:オンラインサービスのログイン画面より新規申込を受付しております。もしくは、お取引店又はオンラインサービスサポートダイヤルまでご連絡ください。
・ 法人の場合:お取引店までご連絡ください。なお、法人の場合は代理人等のご登録がない法人に限りオンラインサービスによる応募が可能です。
(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。
契約の解除の方法
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
オンラインサービスで応募された契約の解除は、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)上の操作又は解除書面の交付もしくは送付により行ってください。オンラインサービス上の操作による場合は当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手続きを行ってください。なお、お取引店で応募された契約の解除に関しては、オンラインサービス上の操作による解除手続きを行うことはできません。解除書面の交付又は送付による場合は、予め解除書面をお取引店に請求したうえで、公開買付期間末日の15時30分までにお取引店に交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。
解除書面を受領する権限を有する者
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)
オンラインサービスで応募された契約の解除は、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)上の操作又は解除書面の交付もしくは送付により行ってください。オンラインサービス上の操作による場合は当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手続きを行ってください。なお、お取引店で応募された契約の解除に関しては、オンラインサービス上の操作による解除手続きを行うことはできません。解除書面の交付又は送付による場合は、予め解除書面をお取引店に請求したうえで、公開買付期間末日の15時30分までにお取引店に交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。
解除書面を受領する権限を有する者
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)
株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法
応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続き終了後速やかに、下記「10 決済の方法」の「(4) 株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。
株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
買付け等に要する資金等
| 買付代金(円)(a) | 15,933,789,500 |
| 金銭以外の対価の種類 | ― |
| 金銭以外の対価の総額 | ― |
| 買付手数料(b) | 100,000,000 |
| その他(c) | 15,000,000 |
| 合計(a)+(b)+(c) | 16,048,789,500 |
(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(3,354,482株)に本公開買付価格(4,750円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
その他資金調達方法
| 内容 | 金額(千円) |
| WEBTOON Entertainmentによる出資 | 11,234,300 |
| NAVER WEBTOONによる出資 | 4,814,700 |
| 計(d) | 16,049,000 |
(注) 公開買付者は、上記金額の出資の裏付けとして、2021年9月30日付で、WEBTOON Entertainmentから、11,234,300千円を限度として公開買付者に対して出資を行う用意がある旨の証明書及びNAVER WEBTOONから4,814,700千円を限度として公開買付者に対して出資を行う用意がある旨の証明書を取得しております。公開買付者は、WEBTOON EntertainmentがNAVERから取得したNAVERがWEBTOON Entertainmentへ16,049,000千円を限度として、出資を行う用意がある旨の証明書及びNAVERの直近の貸借対照表その他の財務資料を確認する方法等によりその資力を確認しており、上記のWEBTOON Entertainmentからの出資についての懸念はないものと考えております。
買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計
16,049,000千円((a)+(b)+(c)+(d))
買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
決済の開始日
2021年11月22日(月曜日)
決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付け等は、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。
買付け等は、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。
株券等の返還方法、決済の方法
下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日の翌営業日)以後速やかに、返還すべき株券等を返還します。株式については、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株式を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株式を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。新株予約権については、新株予約権の応募に際して提出された書類(上記の「7 応募及び契約の解除の方法」の「(1) 応募の方法」④に記載した書類)をそれぞれ応募株主等の指示により応募株主等への交付又は応募株主等の住所への郵送により返還します。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ(https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。
法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,328,800株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,328,800株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
令第14条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法
法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
応募株主等の契約の解除権についての事項
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続き終了後速やかに上記「10 決済の方法」の「(4) 株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
買付条件等の変更をした場合の開示の方法
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条第2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
訂正届出書を提出した場合の開示の方法
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。
公開買付けの結果の開示の方法
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。
その他、その他買付け等の条件及び方法
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商又は国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等又は公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等又は公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
会社の沿革
| 年月 | 事項 |
| 2013年4月 | LINE株式会社の一事業として「LINEマンガアプリ」をリリース |
| 2018年7月 | LINE株式会社の新設分割により公開買付者(LINE Digital Frontier株式会社)を設立。LINE株式会社において運営していた「LINEマンガ及びLINEコミックスに関する事業」を公開買付者に承継し、以後公開買付者において同事業を運営 |
| 2020年8月 | LINE株式会社が所有していた公開買付者の株式70%を、WEBTOON Entertainment Inc.(本社:米国カリフォルニア州)に全部譲渡 |
会社の目的及び事業の内容、公開買付者の状況
通信ネットワーク及び電子技術を利用した電子漫画サービス
資本金の額及び発行済株式の総数
2021年10月1日現在
| 資本金の額 | 発行済株式の総数 |
| 100,000,000円 | 10,000株 |
大株主、公開買付者の状況
| 2021年10月1日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所又は所在地 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| WEBTOON Entertainment Inc. | 5750 Wilshire Blvd. Ste 640, LA, CA 90036, USA | 7,000 | 70.00 |
| NAVER WEBTOON Ltd. | 6 Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, South Korea | 3,000 | 30.00 |
| 計 | - | 10,000 | 100.00 |
役員の職歴及び所有株式の数
2021年10月1日現在
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | ― | 金俊九 | 1977年5月12日 | 2004年 | NHN(株)入社 | ― |
| 2015年 | NAVER WEBTOON&WEBNOVEL 役員 | |||||
| NAVER WEBTOON&WEBNOVEL CIC(Company in Company)責任代表 | ||||||
| 2017年 | NAVER WEBTOON株式会社代表取締役(現職) | |||||
| 2020年 | LINE Digital Frontier株式会社代表取締役(現職) | |||||
| 取締役 | ― | 金信培 | 1982年12月14日 | 2013年 | LINEプラス株式会社入社(東南アジア事業チーム) | ― |
| 2017年 | LINEプラス株式会社インドネシアStrategy&Growthリーダー | |||||
| NAVER WEBTOON株式会社戦略企画リーダー | ||||||
| 2020年 | NAVER WEBTOON株式会社事業リーダー兼任 | |||||
| LINE Digital Frontier株式会社取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | ― | 舛田淳 | 1977年4月22日 | 2007年 | 百度(株)(現バイドゥ(株))取締役 Vice President of Products and Marketing | ― |
| 2008年 | ネイバージャパン(株)(2012年1月にNHN Japan(株)と経営統合)入社 事業戦略室長 | |||||
| 2012年 | NHN Japan(株)(2013年4月LINE(株)に商号変更、現Aホールディングス(株))執行役員 事業戦略室長 | |||||
| 2014年 | 同社上級執行役員CSMO | |||||
| LINE Ventures(株)(現Z Venture Capital(株))代表取締役 | ||||||
| LINE MUSIC(株)代表取締役CEO(現職) | ||||||
| 2015年 | LINE(株)(現Aホールディングス(株))取締役CSMO | |||||
| 2016年 | 夢の街創造委員会(株)(現(株)出前館)取締役(現職) | |||||
| 2020年 | LINE Digital Frontier株式会社取締役(現職) | |||||
| 2021年 | LINE(株)(旧LINE分割準備(株))取締役CSMO(現職) | |||||
| Zホールディングス株式会社取締役 専務執行役員(現職) | ||||||
| Z Entertainment(株)代表取締役社長CPO(最高プロダクト責任者)(現職) | ||||||
| 監査役 | ― | 金成鍾 | 1971年5月9日 | 1999年 | ハンビッネット入社 | ― |
| 2000年 | レッツィ情報通信入社 | |||||
| 2001年 | フューチャーバレー入社 | |||||
| 2002年 | NHN(株)入社 | |||||
| 2020年 | LINE Digital Frontier株式会社監査役(現職) | |||||
| 計 | ― | |||||
経理の状況、公開買付者の状況
公開買付者の第3期事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。)に基づいて作成しております。
なお、公開買付者の第3事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)の財務諸表は、監査法人又は公認会計士の監査を受けておりません。また、公開買付者には子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。
① 貸借対照表
(単位:千円)
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
(単位:千円)
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
② 損益計算書
(単位:千円)
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
③ 株主資本等変動計算書
第3期事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
注記事項
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(1) 資産の評価基準及び評価方法
たな卸し資産の評価基準及び評価方法
商品…移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。
② 株式給付費用引当金
従業員に対する将来の公開買付者親会社のLINEの株式を売却して得た資金の給付に備えるため、株式給付規程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を基礎として計上しております。
③ ポイント引当金
販売促進を図るために付与したポイントについて、将来のポイントの利用により発生する費用に備えるため、当該費用見積額を計上しております。
(3) 収益及び費用の計上基準
公開買付者は役務の提供に応じて収益を認識しております。
(4) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(株主資本等変動計算書に関する注記)
(1) 発行済み株式の種類及び総数に関する事項
なお、公開買付者の第3事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)の財務諸表は、監査法人又は公認会計士の監査を受けておりません。また、公開買付者には子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。
① 貸借対照表
(単位:千円)
| 第3期事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,221,315 |
| 売掛金 | 3,481,483 |
| 商品 | 30,522 |
| 未収入金 | 6,578,251 |
| 前払費用 | 41,008 |
| 未収還付法人税等 | 359,001 |
| 未収還付消費税等 | 253,625 |
| 流動資産合計 | 15,965,208 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 工具器具備品 | 141 |
| 有形固定資産合計 | 141 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社株式 | 156,000 |
| 長期前払費用 | 131,706 |
| 繰延税金資産 | 120,232 |
| 投資その他の資産合計 | 407,939 |
| 固定資産合計 | 408,080 |
| 資産合計 | 16,373,288 |
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
(単位:千円)
| 第3期事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,909,550 |
| 未払金 | 5,841,320 |
| 未払費用 | 681,757 |
| 未払法人税等 | 3,800 |
| 預り金 | 87,116 |
| 前受収益 | 60,333 |
| 前受金 | 13,648 |
| 賞与引当金 | 4,829 |
| ポイント引当金 | 212,042 |
| 株式給付費用引当金 | 6,302 |
| 流動負債合計 | 8,820,701 |
| 固定負債 | |
| 株式給付費用引当金 | 1,435 |
| 固定負債合計 | 1,435 |
| 負債合計 | 8,822,137 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 4,300,000 |
| その他資本剰余金 | 4,897,813 |
| 資本剰余金合計 | 9,197,813 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | △1,746,662 |
| 利益剰余金合計 | △1,746,662 |
| 株主資本合計 | 7,551,151 |
| 純資産合計 | 7,551,151 |
| 負債及び純資産合計 | 16,373,288 |
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
② 損益計算書
(単位:千円)
| 第3期事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 売上高 | 7,192,152 |
| 売上原価 | 3,750,892 |
| 売上総利益 | 3,441,259 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,408,564 |
| 営業損失 | △2,967,304 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 90 |
| 仮想通貨失効益 | 12,271 |
| 為替差益 | 13 |
| その他 | △528 |
| 営業外収益合計 | 11,847 |
| 営業外費用 | |
| 為替差損 | 157 |
| その他 | 1,189 |
| 営業外収益合計 | 1,347 |
| 経常損失 | △2,956,804 |
| 税引前当期純損失 | △2,956,804 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,310 |
| 当期純損失 | △2,962,115 |
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
③ 株主資本等変動計算書
第3期事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 2019年12月31日残高 | 100,000 | 4,300,000 | 4,897,813 | 9,197,813 | 1,215,453 | 1,215,453 | 10,513,266 |
| 当期中の変動額 | |||||||
| 当期純利益 | - | - | - | - | △2,962,115 | △2,962,115 | △2,962,115 |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △2,962,115 | △2,962,115 | △2,962,115 |
| 2020年12月31日残高 | 100,000 | 4,300,000 | 4,897,813 | 9,197,813 | △1,746,662 | △1,746,662 | 7,551,151 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
| 2019年12月31日残高 | - | - | 10,513,266 |
| 当期中の変動額 | |||
| 当期純利益 | - | - | △2,962,115 |
| 当期変動額合計 | - | - | △2,962,115 |
| 2020年12月31日残高 | - | - | 7,551,151 |
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
注記事項
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(1) 資産の評価基準及び評価方法
たな卸し資産の評価基準及び評価方法
商品…移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 引当金の計上基準
① 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。
② 株式給付費用引当金
従業員に対する将来の公開買付者親会社のLINEの株式を売却して得た資金の給付に備えるため、株式給付規程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を基礎として計上しております。
③ ポイント引当金
販売促進を図るために付与したポイントについて、将来のポイントの利用により発生する費用に備えるため、当該費用見積額を計上しております。
(3) 収益及び費用の計上基準
公開買付者は役務の提供に応じて収益を認識しております。
(4) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(株主資本等変動計算書に関する注記)
(1) 発行済み株式の種類及び総数に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度 期首の株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 末の株式数 |
| 普通株式 | 10,000株 | - | - | 10,000株 |
継続開示会社たる公開買付者に関する事項
① 【公開買付者が提出した書類】
イ 【有価証券報告書及びその添付書類】
ロ 【四半期報告書又は半期報告書】
ハ 【訂正報告書】
② 【上記書類を縦覧に供している場所】
イ 【有価証券報告書及びその添付書類】
ロ 【四半期報告書又は半期報告書】
ハ 【訂正報告書】
② 【上記書類を縦覧に供している場所】
公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計
| (2021年10月1日現在) | |||
| 所有する株券等の数 | 令第7条第1項第2号 に該当する株券等の数 | 令第7条第1項第3号 に該当する株券等の数 | |
| 株券 | 24,436(個) | ―(個) | ―(個) |
| 新株予約権証券 | ― | ― | ― |
| 新株予約権付社債券 | ― | ― | ― |
| 株券等信託受益証券 ( ) | ― | ― | ― |
| 株券等預託証券 ( ) | ― | ― | ― |
| 合計 | 24,436 | ― | ― |
| 所有株券等の合計数 | 24,436 | ― | ― |
| (所有潜在株券等の合計数) | (―) | ― | ― |
特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)
| (2021年10月1日現在) | |||
| 所有する株券等の数 | 令第7条第1項第2号 に該当する株券等の数 | 令第7条第1項第3号 に該当する株券等の数 | |
| 株券 | 24,436(個) | ―(個) | ―(個) |
| 新株予約権証券 | ― | ― | ― |
| 新株予約権付社債券 | ― | ― | ― |
| 株券等信託受益証券 ( ) | ― | ― | ― |
| 株券等預託証券 ( ) | ― | ― | ― |
| 合計 | 24,436 | ― | ― |
| 所有株券等の合計数 | 24,436 | ― | ― |
| (所有潜在株券等の合計数) | (―) | ― | ― |
特別関係者
| (2021年10月1日現在) | |
| 氏名又は名称 | ヤフー株式会社 |
| 住所又は所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 |
| 職業又は事業の内容 | インターネット上の広告事業、イーコマース事業、会員サービス事業及びその他事業 |
| 連絡先 | 連絡者 ヤフー株式会社 常務執行役員 最高財務責任者 坂上 亮介 連絡場所 東京都千代田区紀尾井町1番3号 電話番号03-6898-8200 |
| 公開買付者との関係 | 公開買付者との間で、共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者 |
所有株券等の数
ヤフー株式会社
| (2021年10月1日現在) | |||
| 所有する株券等の数 | 令第7条第1項第2号 に該当する株券等の数 | 令第7条第1項第3号 に該当する株券等の数 | |
| 株券 | 24,436(個) | ―(個) | ―(個) |
| 新株予約権証券 | ― | ― | ― |
| 新株予約権付社債券 | ― | ― | ― |
| 株券等信託受益証券 ( ) | ― | ― | ― |
| 株券等預託証券 ( ) | ― | ― | ― |
| 合計 | 24,436 | ― | ― |
| 所有株券等の合計数 | 24,436 | ― | ― |
| (所有潜在株券等の合計数) | (―) | ― | ― |
当該株券等に関して締結されている重要な契約
公開買付者は、2021年9月30日付で、NAVER及びZホールディングスとの間で本取引契約を締結しており、ヤフーが所有する本不応募株式について、ヤフーをして本公開買付けに応募させないことについて合意しております。本取引契約の詳細につきましては、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(4) 本公開買付けに関する重要な合意」をご参照ください。
公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
(1) 公開買付者と対象者の役員との間の合意の有無及び内容
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けに関し、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に対しては、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2) 本公開買付けを実施するに至った背景、目的並びに本公開買付け後の経営方針
上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けを実施するに至った背景、目的並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。
対象者プレスリリースによれば、対象者は、2021年9月30日開催の取締役会において、本公開買付けに関し、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に対しては、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。詳細については、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2) 本公開買付けを実施するに至った背景、目的並びに本公開買付け後の経営方針
上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2) 本公開買付けを実施するに至った背景、目的並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。
株価の状況
(単位:円)
(注) 届出日の属する月の初日から届出日の前日までの期間の株価については、届出日が月初にあたるため記載しておりません。
| 金融商品取引所名 又は認可金融商品 取引業協会名 | 東京証券取引所 市場第一部 | ||||||
| 月別 | 2021年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 最高株価 | 2,911 | 2,729 | 3,635 | 3,540 | 4,135 | 4,585 | ― |
| 最低株価 | 2,524 | 2,416 | 2,570 | 3,135 | 3,120 | 3,685 | ― |
(注) 届出日の属する月の初日から届出日の前日までの期間の株価については、届出日が月初にあたるため記載しておりません。
継続開示会社たる対象者に関する事項
(1) 【対象者が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第20期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月23日関東財務局長に提出
事業年度 第21期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月22日関東財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第22期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月11日関東財務局長に提出
事業年度 第22期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月10日関東財務局長に提出予定
③ 【臨時報告書】
該当事項はありません。
④ 【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社イーブックイニシアティブジャパン
(東京都千代田区麹町一丁目12番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第20期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月23日関東財務局長に提出
事業年度 第21期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月22日関東財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第22期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月11日関東財務局長に提出
事業年度 第22期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月10日関東財務局長に提出予定
③ 【臨時報告書】
該当事項はありません。
④ 【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
株式会社イーブックイニシアティブジャパン
(東京都千代田区麹町一丁目12番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
その他、対象者の状況
(1) 「特別損失の計上に関するお知らせ」の公表
対象者は、2021年9月30日に、「特別損失の計上に関するお知らせ」を公表しております。当該公表によれば、対象者は、2022年3月期において本公開買付けに関連する公開買付関連費用(アドバイザリー手数料、株式価値算定費用、弁護士費用等)を特別損失としてを累計で200百万円(2022年3月期第2四半期で140百万円を計上見込み)を計上する見込みとのことです。なお、2022年3月期の業績予想の変更はないとのことです。詳細については、対象者の当該公表の内容をご参照ください。
対象者は、2021年9月30日に、「特別損失の計上に関するお知らせ」を公表しております。当該公表によれば、対象者は、2022年3月期において本公開買付けに関連する公開買付関連費用(アドバイザリー手数料、株式価値算定費用、弁護士費用等)を特別損失としてを累計で200百万円(2022年3月期第2四半期で140百万円を計上見込み)を計上する見込みとのことです。なお、2022年3月期の業績予想の変更はないとのことです。詳細については、対象者の当該公表の内容をご参照ください。