四半期報告書-第160期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1) 業績の状況
当社グループは、「次の成長に向けた事業基盤の強化」を目標に、第6次中期経営計画(2019年度から2021年度)をスタートさせました。安全・品質・コンプライアンス・環境を当社グループのコアバリューとした上で、第5次中期経営計画(2016年度から2018年度)で掲げた「オペレーショナル・エクセレンス(競争力の不断の追求)」と「イノベーションへのチャレンジ(あたらしい価値の創造)」の2つの方針を継続し、成長への新たな仕掛け、経営資源の強化、環境・社会への貢献の3つの経営課題に取り組んでいます。
当第2四半期連結累計期間の世界経済を概観すると、第1四半期は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響を受け、各国において景気は急速に悪化しました。その後、経済活動の再開が段階的に進められるなかで、第2四半期には持ち直しの動きがみられ始めました。
日本は、個人消費の一部に足踏みもみられるなど依然として厳しい状況にありますが、世界的に自動車市場などが回復に転じたことにより輸出が増加しました。米国及び欧州では感染再拡大の懸念があるものの、生産活動が持ち直し、設備投資には下げ止まりの兆しがみられました。中国では生産活動がいち早く再開したことに加えて、政府の景気対策によって自動車販売が回復するなど持ち直しています。
このような経済環境下、当第2四半期連結累計期間の売上高は3,158億92百万円と前年同期に比べて27.4%の減収となりました。営業損失は106億36百万円(前年同期は157億65百万円の利益)、税引前四半期損失は106億71百万円(前年同期は155億52百万円の利益)、親会社の所有者に帰属する四半期損失は122億87百万円(前年同期は118億16百万円の利益)となりました。
当社グループのセグメントごとの業績は次のとおりです。
① 産業機械事業
産業機械事業は、第1四半期には新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の収縮を背景にグローバルで設備投資に慎重な動きが見られました。第2四半期は緩やかな回復基調にあるものの、当第2四半期連結累計期間では対前年同期比で減収となりました。
地域別では、日本は工作機械向けを中心に需要が低迷し減収となりました。米州では半導体製造装置向けの販売は増加しましたが、アフターマーケット向けの減少や為替影響などにより減収となりました。欧州はアフターマーケット向けや工作機械向けの販売が減少し減収となりました。一方、中国では風力発電や鉄道向けの需要が堅調に推移し増収となりました。
この結果、産業機械事業の売上高は1,045億41百万円(前年同期比△12.6%)、営業利益は中国を除く各地域で販売が減少した影響により12億25百万円(前年同期比△85.3%)となりました。
当事業では、足元の市場環境は厳しい状況ではありますが、今後も需要動向の変化に機動的な対応をしていきます。また、IoTをはじめ、ロボティクスや再生可能エネルギーなどの社会的ニーズが高まる中、これらの成長分野に対応した新たな事業基盤の構築を進めていくことで、市場におけるプレゼンスの中長期的な向上と、収益を伴う事業の拡大を図っていきます。
② 自動車事業
自動車事業は、第1四半期には新型コロナウイルスの流行による移動制限、サプライチェーンの混乱及び生産活動停止の影響を受け、世界的に自動車生産台数が大幅に減少しました。第2四半期に入り自動車市場は回復に転じましたが、第1四半期での落ち込みが影響して、当第2四半期連結累計期間では対前年同期比で減収となりました。
地域別では、日本は自動車市場の需要低迷により減収となりました。米州及び欧州では経済活動の制限により自動車販売が落ち込み減収となりました。中国はオートマチックトランスミッション(AT)関連製品が増加したものの、電動パワーステアリング(EPS)の減少や為替影響により減収となりました。
この結果、自動車事業の売上高は2,022億67百万円(前年同期比△33.1%)となりました。営業損失は日本を中心に各地域で販売が減少した影響により141億13百万円(前年同期は70億61百万円の利益)となりました。
当事業では、グローバル自動車市場の先行きは不透明な状況ではありますが、ATの搭載率向上や多段化、自動車の電動化などへ対応することでパワートレインビジネスの拡大を図るとともに、ステアリングビジネスの再成長や、搭載の義務化が期待される電動ブレーキシステムにも注力していきます。さらに、これまで蓄積してきた技術と新たに取り組む技術開発によって、電動化・自動運転といった自動車の技術革新への貢献を目指します。また、生産性向上や固定費抑制を進めることで、収益力の改善を図っていきます。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、現金及び現金同等物、その他の金融資産(非流動)の増加、有形固定資産の減少等により前連結会計年度末に比べ471億53百万円増加し、1兆770億37百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、その他の金融負債(流動)の増加等により前連結会計年度末に比べ491億30百万円増加し、5,524億95百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の資本合計は、5,245億41百万円となり、親会社の所有者に帰属する四半期損失や剰余金の配当等により前連結会計年度末に比べて19億76百万円減少しました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,874億1百万円となり、前連結会計年度末に比べて501億3百万円増加しました。また、前年同期末に比べて548億41百万円増加しました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税引前四半期損失106億71百万円から減価償却費及び償却費、運転資本等の加減算を行った結果、前年同期に比べて262億86百万円減少し、139億45百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて77億26百万円減少し、189億10百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出195億91百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて618億44百万円増加し、542億32百万円の収入となりました。主な収入の内訳は、短期借入金の純増減額523億63百万円、長期借入れによる収入97億27百万円です。一方で主な支出の内訳は、配当金の支払額51億25百万円です。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
当社は、資本市場に公開された株式会社であるため、当社株式の大量の買付行為がなされた場合にそれに応じるべきか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきであると考えます。
しかしながら、株式の大量の買付行為の中には、株主の皆様に対する必要十分な情報開示や熟慮のための機会が与えられることなく、あるいは当社取締役会が意見表明を行い、代替案を提示するための情報や時間が提供されずに、突如として強行されるものもあり得ます。このような株式の大量の買付行為の中には、真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する買付行為もあり得ます。
かかる当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する当社株式の大量の買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
② 基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
(イ)中期経営計画等による企業価値の向上への取り組み
当社グループは、MOTION & CONTROLを通じた社会への価値提供を続けていくために、2026年に中長期的な持続的成長を可能にする企業基盤を確立することを目指していきます。その達成に向けて2020年3月期から2022年3月期までの3ヵ年を第6次中期経営計画としてスタートさせました。
第6次中期経営計画として掲げる目標は、「次の成長に向けた事業基盤の強化」です。安全・品質・コンプライアンスそして環境を当社グループのコアバリューとした上で、第5次中期経営計画で据えた「オペレーショナル・エクセレンス(競争力の不断の追求)」と「イノベーションへのチャレンジ(あたらしい価値の創造)」の2つの方針を継続し、成長への新たな仕掛け、経営資源の強化、環境・社会への貢献の3つの経営課題に取り組んでいきます。
3つの経営課題と取り組み内容は以下のとおりです。
1.成長への新たな仕掛けとして、
・IoT、電動化、自動化、環境の成長セグメントでNSKコア製品を伸ばします。
・成長セグメントへの新製品の市場化による成長を目指します。
・EPSビジネスは製品ラインナップを充実させ再成長を目指します。
2.経営資源の強化として、
・教育体系の再構築や働き方改革、健康経営の促進、ダイバーシティ&インクルージョンの推進に
よってヒトづくりを進化させます。
・IoTの活用によってモノつくりを進化させます。
・NSKコア技術の徹底追求やオープンイノベーションの更なる活用によって技術開発を進化させます。
3.環境・社会への貢献として、
・事業活動や環境貢献型の製品開発によるCO2排出量の削減及び資源の有効活用を目指します。
・市場、お客様へ安全・安心を与える品質づくりと安全文化づくりを目指します。
・社会から信頼され、働きがいのある会社づくりを目指します。
・グループガバナンスを強化しステークホルダーとの対話を深めていきます。
当社グループは、以上の取り組みによってたゆまぬ成長を目指すとともに、将来にわたって、企業理念に基づいた企業活動とMOTION & CONTROLの進化を通じ、社会的課題の解決と社会の持続的発展へ貢献し続けていきます。また、SDGsに定められた17の目標を尊重するとともに、当社グループの事業に関連した目標を重点課題として積極的に取り組んでいきます。
(ロ)コーポレートガバナンスに関する取り組み
当社は、社会的責任を果たし、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、持続的に向上させるため、経営に関する意思決定の透明性と健全性の向上に積極的に取り組んできました。2004年に当時の委員会等設置会社に移行する以前から、執行役員制度の導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の設置をしてきました。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞれ社内取締役と過半数を占める社外取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性の確保に大きな役割を果たしています。
なお、当社の社外取締役については全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取り組みの概要
当社は、2020年6月30日開催の当社定時株主総会決議に基づき当社株式の大量買付行為に関する対応策(以下「本プラン」という。)を継続しています。なお、本プランの有効期間は2023年6月に開催予定の当社定時株主総会の終結時までとしています。
本プランは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為等(以下「大量買付行為」という。)を行い又は行おうとする者(以下「大量買付者」という。)に対して、本プラン所定の手続(以下「大量買付ルール」という。)を遵守することを求めています。大量買付ルールは、大量買付者が事前に大量買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価、検討等のために必要かつ十分な情報を提供した上で、当社取締役会による評価等のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)満了後に大量買付行為を開始できることを原則的な手続としています。
大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、仮に当該大量買付行為に反対であったとしても、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は発動しません。但し、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがあると合理的に認められる場合には、取締役会評価期間満了後に株主総会を開催し、対抗措置を発動すべきか否かを株主の皆様のご判断に委ねることができるものとします。また、大量買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合、大量買付者の提案する買収の方法が、いわゆる強圧的二段階買付けに代表される、構造上株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株券等の売却を強要するおそれがある場合等、大量買付行為が所定の5類型のいずれかに該当し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると合理的に認められる場合には、例外的に当社取締役会決議により対抗措置を発動することがあります。
これに対して、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、対抗措置を発動する場合があります。但し、当社取締役会が、株主の皆様のご意思を確認することが実務上可能であり、かつ、株主の皆様のご意思を確認するために株主総会を開催し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様にご判断いただくことが適切であると合理的に判断した場合には、取締役会評価期間満了後に株主総会を開催し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様のご判断に委ねるものとします。
当社取締役会が、上記の株主総会を開催する場合には、大量買付者は、当該株主総会終結時まで、大量買付行為を開始してはならないものとします。
また、当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性及び公正性を担保するために、次の手続を経ることとします。まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、当社取締役会から独立した組織である独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものとします。また、対抗措置の発動に係る当社取締役会の決議は、当社取締役全員が出席する取締役会において、全会一致により行うものとします。なお、当社は、本プランにおける対抗措置として、新株予約権無償割当てを行います。
本プランに係る手続の流れの概要については、次ページに記載のとおりです。また、本プランの詳細につきましては当社ウェブサイト(https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html)に掲載しています、2020年6月2日付「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご参照ください。
④ 上記の取り組みについての取締役会の判断及びその理由
上記②の取り組みは、当社の中長期的な企業価値の向上のための基本的な取り組みの一環であり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させることを目的として実施しているものです。
上記③の取り組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的として、大量買付者に対して、大量買付行為に関する必要な情報の提供、及び、その内容の評価等に必要な期間の確保を求めるために導入されるものであり、また、上記③記載のとおり、本プラン所定の一定の類型に該当する大量買付行為を防止することにより、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みです。さらに、上記③記載のとおり、対抗措置を発動しようとする場合には原則として株主総会を開催し、当社取締役会が対抗措置の発動を決議する場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、取締役全員が出席する当社取締役会において、全会一致により行うこととしており、当社取締役会の恣意的な判断を排し、その取り組みの合理性及び公正性を確保するための様々な制度及び手続が確保されています。
従いまして、上記②及び③の取り組みは上記①の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。
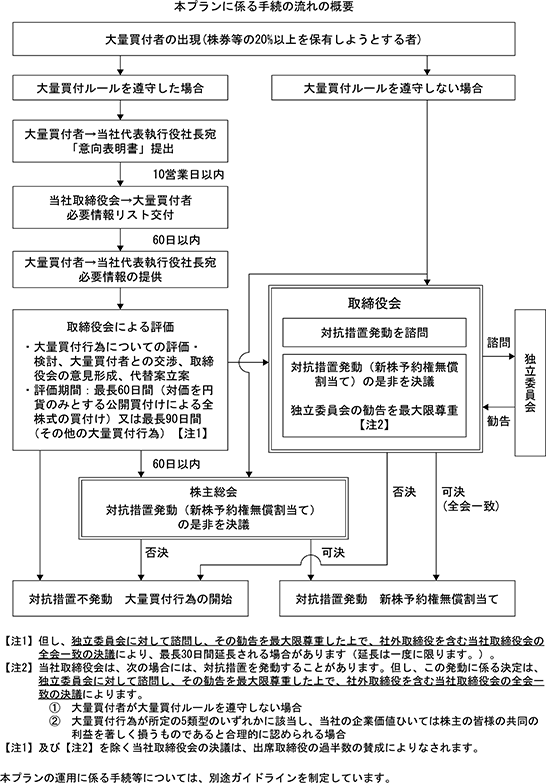
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、84億25百万円です。なお、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当社グループは、「次の成長に向けた事業基盤の強化」を目標に、第6次中期経営計画(2019年度から2021年度)をスタートさせました。安全・品質・コンプライアンス・環境を当社グループのコアバリューとした上で、第5次中期経営計画(2016年度から2018年度)で掲げた「オペレーショナル・エクセレンス(競争力の不断の追求)」と「イノベーションへのチャレンジ(あたらしい価値の創造)」の2つの方針を継続し、成長への新たな仕掛け、経営資源の強化、環境・社会への貢献の3つの経営課題に取り組んでいます。
当第2四半期連結累計期間の世界経済を概観すると、第1四半期は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響を受け、各国において景気は急速に悪化しました。その後、経済活動の再開が段階的に進められるなかで、第2四半期には持ち直しの動きがみられ始めました。
日本は、個人消費の一部に足踏みもみられるなど依然として厳しい状況にありますが、世界的に自動車市場などが回復に転じたことにより輸出が増加しました。米国及び欧州では感染再拡大の懸念があるものの、生産活動が持ち直し、設備投資には下げ止まりの兆しがみられました。中国では生産活動がいち早く再開したことに加えて、政府の景気対策によって自動車販売が回復するなど持ち直しています。
このような経済環境下、当第2四半期連結累計期間の売上高は3,158億92百万円と前年同期に比べて27.4%の減収となりました。営業損失は106億36百万円(前年同期は157億65百万円の利益)、税引前四半期損失は106億71百万円(前年同期は155億52百万円の利益)、親会社の所有者に帰属する四半期損失は122億87百万円(前年同期は118億16百万円の利益)となりました。
当社グループのセグメントごとの業績は次のとおりです。
① 産業機械事業
産業機械事業は、第1四半期には新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の収縮を背景にグローバルで設備投資に慎重な動きが見られました。第2四半期は緩やかな回復基調にあるものの、当第2四半期連結累計期間では対前年同期比で減収となりました。
地域別では、日本は工作機械向けを中心に需要が低迷し減収となりました。米州では半導体製造装置向けの販売は増加しましたが、アフターマーケット向けの減少や為替影響などにより減収となりました。欧州はアフターマーケット向けや工作機械向けの販売が減少し減収となりました。一方、中国では風力発電や鉄道向けの需要が堅調に推移し増収となりました。
この結果、産業機械事業の売上高は1,045億41百万円(前年同期比△12.6%)、営業利益は中国を除く各地域で販売が減少した影響により12億25百万円(前年同期比△85.3%)となりました。
当事業では、足元の市場環境は厳しい状況ではありますが、今後も需要動向の変化に機動的な対応をしていきます。また、IoTをはじめ、ロボティクスや再生可能エネルギーなどの社会的ニーズが高まる中、これらの成長分野に対応した新たな事業基盤の構築を進めていくことで、市場におけるプレゼンスの中長期的な向上と、収益を伴う事業の拡大を図っていきます。
② 自動車事業
自動車事業は、第1四半期には新型コロナウイルスの流行による移動制限、サプライチェーンの混乱及び生産活動停止の影響を受け、世界的に自動車生産台数が大幅に減少しました。第2四半期に入り自動車市場は回復に転じましたが、第1四半期での落ち込みが影響して、当第2四半期連結累計期間では対前年同期比で減収となりました。
地域別では、日本は自動車市場の需要低迷により減収となりました。米州及び欧州では経済活動の制限により自動車販売が落ち込み減収となりました。中国はオートマチックトランスミッション(AT)関連製品が増加したものの、電動パワーステアリング(EPS)の減少や為替影響により減収となりました。
この結果、自動車事業の売上高は2,022億67百万円(前年同期比△33.1%)となりました。営業損失は日本を中心に各地域で販売が減少した影響により141億13百万円(前年同期は70億61百万円の利益)となりました。
当事業では、グローバル自動車市場の先行きは不透明な状況ではありますが、ATの搭載率向上や多段化、自動車の電動化などへ対応することでパワートレインビジネスの拡大を図るとともに、ステアリングビジネスの再成長や、搭載の義務化が期待される電動ブレーキシステムにも注力していきます。さらに、これまで蓄積してきた技術と新たに取り組む技術開発によって、電動化・自動運転といった自動車の技術革新への貢献を目指します。また、生産性向上や固定費抑制を進めることで、収益力の改善を図っていきます。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、現金及び現金同等物、その他の金融資産(非流動)の増加、有形固定資産の減少等により前連結会計年度末に比べ471億53百万円増加し、1兆770億37百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、その他の金融負債(流動)の増加等により前連結会計年度末に比べ491億30百万円増加し、5,524億95百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の資本合計は、5,245億41百万円となり、親会社の所有者に帰属する四半期損失や剰余金の配当等により前連結会計年度末に比べて19億76百万円減少しました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,874億1百万円となり、前連結会計年度末に比べて501億3百万円増加しました。また、前年同期末に比べて548億41百万円増加しました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税引前四半期損失106億71百万円から減価償却費及び償却費、運転資本等の加減算を行った結果、前年同期に比べて262億86百万円減少し、139億45百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて77億26百万円減少し、189億10百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出195億91百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて618億44百万円増加し、542億32百万円の収入となりました。主な収入の内訳は、短期借入金の純増減額523億63百万円、長期借入れによる収入97億27百万円です。一方で主な支出の内訳は、配当金の支払額51億25百万円です。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
当社は、資本市場に公開された株式会社であるため、当社株式の大量の買付行為がなされた場合にそれに応じるべきか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきであると考えます。
しかしながら、株式の大量の買付行為の中には、株主の皆様に対する必要十分な情報開示や熟慮のための機会が与えられることなく、あるいは当社取締役会が意見表明を行い、代替案を提示するための情報や時間が提供されずに、突如として強行されるものもあり得ます。このような株式の大量の買付行為の中には、真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する買付行為もあり得ます。
かかる当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する当社株式の大量の買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
② 基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
(イ)中期経営計画等による企業価値の向上への取り組み
当社グループは、MOTION & CONTROLを通じた社会への価値提供を続けていくために、2026年に中長期的な持続的成長を可能にする企業基盤を確立することを目指していきます。その達成に向けて2020年3月期から2022年3月期までの3ヵ年を第6次中期経営計画としてスタートさせました。
第6次中期経営計画として掲げる目標は、「次の成長に向けた事業基盤の強化」です。安全・品質・コンプライアンスそして環境を当社グループのコアバリューとした上で、第5次中期経営計画で据えた「オペレーショナル・エクセレンス(競争力の不断の追求)」と「イノベーションへのチャレンジ(あたらしい価値の創造)」の2つの方針を継続し、成長への新たな仕掛け、経営資源の強化、環境・社会への貢献の3つの経営課題に取り組んでいきます。
3つの経営課題と取り組み内容は以下のとおりです。
1.成長への新たな仕掛けとして、
・IoT、電動化、自動化、環境の成長セグメントでNSKコア製品を伸ばします。
・成長セグメントへの新製品の市場化による成長を目指します。
・EPSビジネスは製品ラインナップを充実させ再成長を目指します。
2.経営資源の強化として、
・教育体系の再構築や働き方改革、健康経営の促進、ダイバーシティ&インクルージョンの推進に
よってヒトづくりを進化させます。
・IoTの活用によってモノつくりを進化させます。
・NSKコア技術の徹底追求やオープンイノベーションの更なる活用によって技術開発を進化させます。
3.環境・社会への貢献として、
・事業活動や環境貢献型の製品開発によるCO2排出量の削減及び資源の有効活用を目指します。
・市場、お客様へ安全・安心を与える品質づくりと安全文化づくりを目指します。
・社会から信頼され、働きがいのある会社づくりを目指します。
・グループガバナンスを強化しステークホルダーとの対話を深めていきます。
当社グループは、以上の取り組みによってたゆまぬ成長を目指すとともに、将来にわたって、企業理念に基づいた企業活動とMOTION & CONTROLの進化を通じ、社会的課題の解決と社会の持続的発展へ貢献し続けていきます。また、SDGsに定められた17の目標を尊重するとともに、当社グループの事業に関連した目標を重点課題として積極的に取り組んでいきます。
(ロ)コーポレートガバナンスに関する取り組み
当社は、社会的責任を果たし、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、持続的に向上させるため、経営に関する意思決定の透明性と健全性の向上に積極的に取り組んできました。2004年に当時の委員会等設置会社に移行する以前から、執行役員制度の導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の設置をしてきました。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞれ社内取締役と過半数を占める社外取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性の確保に大きな役割を果たしています。
なお、当社の社外取締役については全員を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取り組みの概要
当社は、2020年6月30日開催の当社定時株主総会決議に基づき当社株式の大量買付行為に関する対応策(以下「本プラン」という。)を継続しています。なお、本プランの有効期間は2023年6月に開催予定の当社定時株主総会の終結時までとしています。
本プランは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為等(以下「大量買付行為」という。)を行い又は行おうとする者(以下「大量買付者」という。)に対して、本プラン所定の手続(以下「大量買付ルール」という。)を遵守することを求めています。大量買付ルールは、大量買付者が事前に大量買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価、検討等のために必要かつ十分な情報を提供した上で、当社取締役会による評価等のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)満了後に大量買付行為を開始できることを原則的な手続としています。
大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、仮に当該大量買付行為に反対であったとしても、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は発動しません。但し、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがあると合理的に認められる場合には、取締役会評価期間満了後に株主総会を開催し、対抗措置を発動すべきか否かを株主の皆様のご判断に委ねることができるものとします。また、大量買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合、大量買付者の提案する買収の方法が、いわゆる強圧的二段階買付けに代表される、構造上株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株券等の売却を強要するおそれがある場合等、大量買付行為が所定の5類型のいずれかに該当し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると合理的に認められる場合には、例外的に当社取締役会決議により対抗措置を発動することがあります。
これに対して、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、対抗措置を発動する場合があります。但し、当社取締役会が、株主の皆様のご意思を確認することが実務上可能であり、かつ、株主の皆様のご意思を確認するために株主総会を開催し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様にご判断いただくことが適切であると合理的に判断した場合には、取締役会評価期間満了後に株主総会を開催し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様のご判断に委ねるものとします。
当社取締役会が、上記の株主総会を開催する場合には、大量買付者は、当該株主総会終結時まで、大量買付行為を開始してはならないものとします。
また、当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性及び公正性を担保するために、次の手続を経ることとします。まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、当社取締役会から独立した組織である独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものとします。また、対抗措置の発動に係る当社取締役会の決議は、当社取締役全員が出席する取締役会において、全会一致により行うものとします。なお、当社は、本プランにおける対抗措置として、新株予約権無償割当てを行います。
本プランに係る手続の流れの概要については、次ページに記載のとおりです。また、本プランの詳細につきましては当社ウェブサイト(https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html)に掲載しています、2020年6月2日付「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご参照ください。
④ 上記の取り組みについての取締役会の判断及びその理由
上記②の取り組みは、当社の中長期的な企業価値の向上のための基本的な取り組みの一環であり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させることを目的として実施しているものです。
上記③の取り組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的として、大量買付者に対して、大量買付行為に関する必要な情報の提供、及び、その内容の評価等に必要な期間の確保を求めるために導入されるものであり、また、上記③記載のとおり、本プラン所定の一定の類型に該当する大量買付行為を防止することにより、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みです。さらに、上記③記載のとおり、対抗措置を発動しようとする場合には原則として株主総会を開催し、当社取締役会が対抗措置の発動を決議する場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、取締役全員が出席する当社取締役会において、全会一致により行うこととしており、当社取締役会の恣意的な判断を排し、その取り組みの合理性及び公正性を確保するための様々な制度及び手続が確保されています。
従いまして、上記②及び③の取り組みは上記①の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。
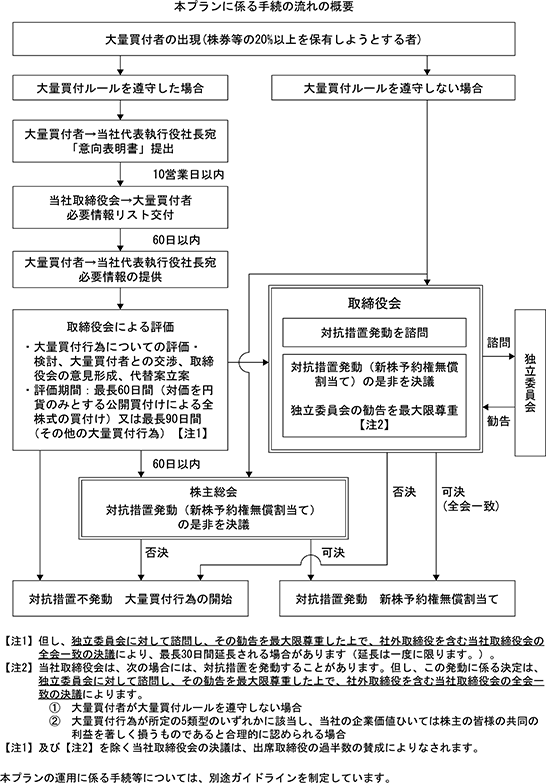
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、84億25百万円です。なお、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。